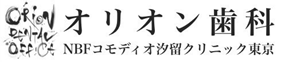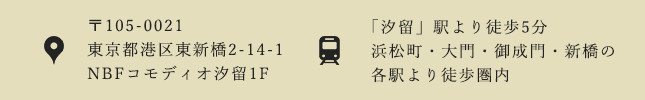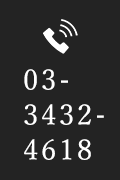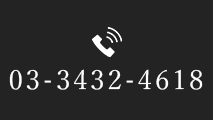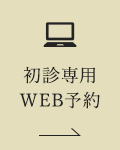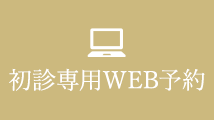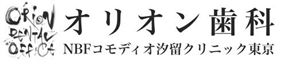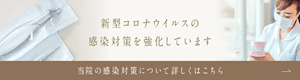鏡を見てふと気づく歯の長さ。更年期世代の女性が抱えるお口の悩み

「歯が長くなったように見える…」これって気のせい?
ふと鏡を見たとき、以前よりも歯が長くなったように感じたり、歯と歯の間に隙間ができてきたり…。それは、気のせいではありません。歯そのものが伸びているわけではなく、歯を支えている歯ぐきが痩せて下がり(歯肉退縮)、これまで隠れていた歯の根の部分が露出してきたために、歯が長く見えているのです。こうした「歯ぐき下がる」という現象は、40代後半から50代にかけての更年期世代の女性に多く見られるお悩みの一つです。加齢による自然な変化と諦めてしまう方もいらっしゃいますが、その背景には、女性ホルモンの変化と深く関連した、見過ごせないお口のトラブルが隠れている可能性があります。特に、痛みなどの自覚症状がないまま進行する歯周病が原因となっているケースも少なくありません。
冷たいものがしみる、食べ物が挟まりやすいと感じる方へ
歯ぐきが下がると、見た目の変化だけでなく、様々な不快な症状が現れ始めます。その代表的なものが「知覚過敏」です。歯ぐきが下がって露出した歯の根の部分(歯根)は、硬いエナメル質で覆われておらず、外部からの刺激が神経に伝わりやすい象牙質でできています。そのため、冷たい水や風、歯ブラシの毛先が触れただけでも、「キーン」と鋭い痛みを感じやすくなるのです。また、これまで歯ぐきで満たされていた歯と歯の間の隙間が大きくなるため、食事の際に食べ物が挟まりやすくなるのも、歯ぐきが下がってきたサインの一つです。食べ物が挟まると、不快なだけでなく、そこから虫歯や口臭が発生したり、さらに歯周病を悪化させたりする原因にもなります。これらの症状は、単なる不快症状ではなく、お口の健康のバランスが崩れ始めていることを示す重要な警告です。
お顔の印象まで変わってしまう「歯ぐき下がり」への不安
歯ぐき下がりは、お口の機能だけでなく、見た目の美しさ、ひいてはお顔全体の印象にも大きな影響を与えます。健康的で若々しい笑顔は、歯と歯の間の隙間を埋める、引き締まったピンク色の歯ぐきがあってこそ成り立ちます。歯ぐきが下がることで歯が長く見えたり、歯の根の黄色っぽい色が見えたり、歯と歯の間に三角形の黒い隙間(ブラックトライアングル)が目立つようになると、どうしても老けた印象や、不健康な印象を与えがちです。更年期を迎え、心身の変化に戸惑う中で、お顔の印象の変化は、女性にとって大きな精神的ストレスとなり得ます。しかし、この歯ぐき下がりは、その原因を正しく突き止め、適切な対処を行うことで、進行を食い止め、症状を改善させることが可能です。まずはその原因を正しく知ることから始めましょう。
「歯ぐきが下がる」とは?歯肉退縮のメカニズムを正しく知る

歯を支える「歯槽骨」が痩せることが、根本的な原因です
多くの方が、「歯ぐき下がる」という現象を、歯ぐきそのものが縮んでしまうことだと考えています。しかし、その根本的な原因は、歯ぐきの内側にある、歯を支えている骨「歯槽骨(しそうこつ)」が痩せてしまう(吸収される)ことにあります。歯ぐきはその下の歯槽骨の形に沿っているため、土台である骨が失われると歯ぐきも一緒に下がります。例えるなら、山の斜面の岩盤が崩れると、その上の土も一緒に崩れ落ちるようなものです。歯槽骨が失われる大きな原因は歯周病であり、歯周病菌の影響で炎症が進むと骨が徐々に吸収されていきます。その他、強すぎる力でのブラッシングや、加齢に伴う生理的な変化も原因となり得ますが、特に更年期世代の女性では、ホルモンバランスの変化が歯周病の進行に影響し、歯ぐき下がりのリスクを高める要因の一つと考えられています。
見た目だけの問題ではない、歯の根が露出するリスクとは
歯ぐきが下がると、これまで守られていた歯の根の部分「歯根(しこん)」が露出します。この歯根の露出は、単に歯が長く見えるという審美的な問題に留まらず、いくつかの深刻なリスクを伴います。まず、歯の頭の部分(歯冠)が硬いエナメル質で覆われているのに対し、歯根の表面は柔らかく酸に弱い「象牙質」でできています。そのため、歯根が露出すると、虫歯菌に対する抵抗力が著しく低下し、非常に虫歯になりやすい状態になります。これを「根面う蝕(こんめんうしょく)」と呼び、進行が早く治療も難しいのが特徴です。また、象牙質には神経に通じる無数の小さな管が通っているため、冷たいものや歯ブラシの刺激で「キーン」としみる、知覚過敏の症状も起こりやすくなります。歯ぐき下がりは、歯の健康寿命そのものを脅かす危険な状態なのです。
歯周病との関係性:歯ぐき下がりは歯周病のサイン?それとも結果?
「歯ぐき下がり」と「歯周病」は、非常に密接な、いわば”鶏と卵”のような関係にあります。多くの場合、歯ぐき下がりは、歯周病が進行した「結果」として現れます。歯周病によって歯を支える歯槽骨が溶かされると、それに伴って歯ぐきも下がり、歯根が露出してくるのです。この意味で、歯ぐき下がりは歯周病が進行していることを示す重要な「サイン」と言えます。一方で、一度下がってしまった歯ぐきは、歯周病をさらに悪化させる「原因」にもなり得ます。歯と歯の間に隙間ができて食べ物が詰まりやすくなったり、露出した歯根の複雑な形態によってプラークが溜まりやすくなったりするためです。このように、歯ぐき下がりと歯周病は、互いに悪影響を及ぼしあう悪循環の関係にあります。特にホルモンバランスが揺らぎやすい更年期の女性は、この悪循環に陥りやすいため、早期の対応が重要です。
更年期と歯ぐき下がり。女性ホルモン「エストロゲン」の減少が鍵

エストロゲンが持つ、骨と歯ぐきのコラーゲンを守る大切な働き
女性ホルモンの一種である「エストロゲン」は、妊娠や出産だけでなく、生涯を通じて女性の全身の健康を司る、非常に重要なホルモンです。お口の健康においても、エストロゲンは重要な「守護神」の役割を果たしています。まず、歯ぐきの大部分を構成するコラーゲン線維の生成を促し、組織のハリと弾力を保つ働きがあります。これにより、歯ぐきは引き締まり、細菌の侵入に対する抵抗力を維持しています。さらに、エストロゲンは骨の健康においても重要な役割を担っています。骨は、常に古い骨が壊され(骨吸収)、新しい骨が作られる(骨形成)という新陳代謝を繰り返していますが、エストロゲンは骨を壊す細胞(破骨細胞)の働きを穏やかに抑制する作用を持っています。この働きによって、歯を支える歯槽骨の密度も、若いうちは健康に保たれているのです。
ホルモン減少が引き起こす、歯周組織の脆弱化とは
女性が更年期を迎え、閉経すると、卵巣からのエストロゲンの分泌が急激に減少します。これまでお口の健康を守ってくれていたエストロゲンの加護が失われることで、「歯周組織(歯ぐきや歯槽骨など)」は一気に脆弱化し始めます。まず、骨を壊す破骨細胞の働きを抑制していたブレーキが外れるため、骨の破壊スピードが再生スピードを上回り、全身の骨密度が低下し始めます。この変化は、歯を支える歯槽骨も例外ではなく、歯周病に罹患している場合、その進行を著しく加速させ、「歯ぐき下がる」現象の直接的な原因となります。さらに、歯ぐき自体のコラーゲン生成も滞るため、組織はハリを失い、薄く、傷つきやすくなります。このように、更年期には歯周組織の「守る力」と「再生する力」の両方が低下するため、お口の中は歯周病菌に対して極めて無防備な状態に陥ってしまうのです。
骨粗しょう症と関連する「閉経後骨粗鬆症性歯周炎」というリスク
更年期以降の女性に多く見られる、全身の骨がもろくなる病気「骨粗しょう症」。この骨粗しょう症と歯周病が、エストロゲンの減少を共通の原因として、密接に関連しあっていることが近年の研究で明らかになっています。特に、骨粗しょう症を伴う閉経後の女性では、歯周病が急速に進行するケースがあり、『閉経後骨粗鬆症性歯周炎(PMOP)』と呼ばれることもあります。これは、全身的な骨密度の低下によって、顎の骨(歯槽骨)の土台そのものが弱くなっているところに、歯周病菌による局所的な攻撃が加わることで、相乗的に骨の破壊が進行してしまう状態です。骨粗しょう症と診断されている方や、そのリスクが高い方は、歯周病が重症化しやすく、歯を失うリスクが高いことが報告されています。更年期におけるお口のケアは、歯周病の管理だけでなく、全身の骨の健康を守るという観点からも非常に重要です。
口の乾燥「ドライマウス」も要注意。唾液のバリア機能低下

更年期に唾液が減少しやすくなるのはなぜ?
更年期を迎えた女性が「歯ぐき下がる」などのトラブルに見舞われやすくなる背景には、女性ホルモンの減少だけでなく、唾液の分泌量が減る「ドライマウス(口腔乾燥症)」が深く関わっています。唾液の分泌は、自律神経によってコントロールされていますが、更年期には女性ホルモン「エストロゲン」の急激な減少に伴い、この自律神経のバランスが乱れがちになります。その影響で、唾液腺への指令が正常に伝わりにくくなり、唾液の分泌量が減少してしまうのです。また、エストロゲンは体内の潤いを保つ働きも担っているため、エストロゲンの減少は、唾液腺の働きにも影響を与えると考えられています。さらに、この時期に多く見られるストレスや、高血圧などの治療薬の副作用によっても、唾液の分泌は抑制されることがあります。これらの複合的な要因により、更年期の女性のお口の中は、知らず知らずのうちに乾燥しやすい状態へと傾いていくのです。
唾液の減少が、虫歯や歯周病菌の活動を活発にする
唾液は、単なる水分ではありません。お口の健康を守るための、様々な機能を持つ「天然の防御システム」です。食べかすや細菌を洗い流す「洗浄作用」、食後の酸性に傾いたお口の中を中和する「緩衝作用」、細菌の増殖を抑える「抗菌作用」、そして初期の虫歯を修復する「再石灰化作用」。これら唾液の力が、私たちの歯を虫歯や歯周病から守ってくれています。しかし、ドライマウスによって唾液の分泌量が減少すると、この強力なバリア機能が一気に低下します。プラーク(歯垢)が洗い流されにくく、歯に付着しやすくなり、歯周病菌が活動しやすい環境が生まれます。これが、更年期に歯周病が悪化し、歯ぐき下がる現象を助長する一因となります。また、酸を中和する力が弱まるため、虫歯のリスク、特に歯ぐきが下がって露出した無防備な歯の根にできる「根面う蝕」のリスクが飛躍的に高まってしまいます。
お口のネバつき・口臭・味覚の変化は、ドライマウスのサインかも
ドライマウスは、単に「喉が渇く」という症状だけではありません。ご自身では気づきにくい、様々なサインとして現れることがあります。以下のような症状に心当たりはありませんか。
・お口の中がネバネバする:唾液が減ると、サラサラ感がなくなり、粘着性が高まります。
・口臭が強くなった:唾液の洗浄作用が低下し、細菌や剥がれた粘膜が溜まることで、臭いが強くなります。
・食べ物の味が分かりにくい:唾液は味を感じるためにも必要です。味が薄く感じたり、嫌な味がしたりすることがあります。
・乾いた食べ物が飲み込みにくい:パンやクッキーなどが、水分なしでは食べにくくなります。
・舌がヒリヒリと痛む:舌が乾燥して、表面がひび割れたり、赤くなったりして、痛みを感じることがあります。
これらのサインは、お口の防御機能が低下していることを示す重要な警告です。放置せず、歯科医師に相談しましょう。
骨粗しょう症と歯周病の密接な関係。顎の骨も例外ではない

全身の骨密度低下が、歯を支える骨の吸収を加速させる
歯ぐき下がる現象の根本原因は、歯を支える顎の骨「歯槽骨」が失われることにあるとご説明しました。更年期以降の女性が特に注意すべきなのは、全身の骨密度が低下する「骨粗しょう症」が、この歯槽骨の減少を著しく加速させてしまうという事実です。女性ホルモン(エストロゲン)の減少によって引き起こされる骨粗しょう症は、背骨や手足の骨だけでなく、お口の中の歯槽骨をも、もろく、痩せやすい状態にしてしまいます。いわば、歯が建っている「土地の地盤」そのものが弱くなってしまうのです。この弱った地盤に、歯周病菌による攻撃が加わるとどうなるでしょうか。健康な骨であれば耐えられたかもしれない炎症の波も、もろくなった歯槽骨は耐えきれず、通常よりも速いスピードで、そして広範囲にわたって骨の吸収が進んでしまいます。これが、更年期世代の女性において、歯周病が急速に悪化し、歯ぐき下がりが顕著になりやすい大きな理由の一つです。
歯周病が骨粗しょう症のリスクを高める?双方向の悪循環
かつては、骨粗しょう症が一方的に歯周病を悪化させると考えられていました。しかし近年の研究では、その逆、つまり「歯周病が骨粗しょう症を悪化させる」という、双方向に影響し合う悪循環がある可能性が指摘されています。歯周病は、お口の中だけの問題に留まらない、全身に影響を及ぼす慢性的な炎症性疾患です。歯周病に罹患した歯ぐきでは、「炎症性サイトカイン」と呼ばれる物質が大量に産生されます。この物質は、血流に乗って全身を巡り、骨の新陳代謝のバランスを乱して、骨を壊す細胞(破骨細胞)の働きを活性化させてしまうことが分かってきました。つまり、お口の中の慢性的な炎症が、全身の骨の破壊を促進し、骨粗しょう症の発症や進行のリスクを高める可能性があるのです。更年期の女性にとって、歯周病の管理は、歯を守るだけでなく、全身の骨の健康を守るという観点からも極めて重要と言えます。
骨粗しょう症のお薬(BP製剤など)と歯科治療における注意点
骨粗しょう症の治療で広く用いられているお薬に、「ビスフォスフォネート製剤(BP製剤)」や「デノスマブ(抗RANKLモノクローナル抗体製剤)」があります。これらのお薬は、骨の吸収を抑えて骨密度を保つために有効とされています。ただし、服用中に抜歯やインプラント手術などを受ける場合、ごく稀に『薬剤関連顎骨壊死(MRONJ)』が報告されています。そのため、骨粗しょう症の治療歴がある方は、必ず歯科医師にお伝えください。お薬の服用を自己判断で中断するのは危険です。私たちは、あなたのかかりつけ医と連携を取り、安全を最優先した治療計画を立案します。
下がった歯ぐきは元に戻る?歯周病の進行を食い止め、見た目を改善する方法

第一歩は歯周病の進行を止めること。徹底した原因除去治療
下がってしまった歯ぐきを改善するための治療を検討する上で、まず取り組むべき第一歩は、歯ぐき下がりの主な原因である『歯周病』の進行を食い止めることです。炎症が残ったままの不安定な土台に、再生治療などの高度な処置を行っても、良い結果は得られません。例えるなら、火事が起きている家にリフォームを施すようなものです。まずは、原因であるプラーク(歯垢)や歯石を徹底的に除去し、歯ぐきの炎症を鎮め、健康な状態を取り戻す「歯周基本治療」が不可欠です。歯科医院での専門的なクリーニング(スケーリング・ルートプレーニング)と、ご自身の毎日のセルフケアの質を高めるためのブラッシング指導。この原因除去治療を徹底することで、さらなる歯ぐき下がりを防ぎ、健康な土台を築くことができます。これだけでも、歯ぐきの腫れが引き締まり、ある程度の改善が見られることも少なくありません。
失われた組織を取り戻す「歯周組織再生療法」とは
歯周病によって一度失われてしまった歯槽骨などの歯周組織は、自然に元どおりになることはありません。しかし、近年の歯周病治療では、失われた組織の再生を目指す『歯周組織再生療法』という治療法が行われることもあります。これは、歯周外科手術の一環として行われる処置です。歯ぐきを剥離して歯の根を露出させ、徹底的に清掃した後、「メンブレン」と呼ばれる特殊な膜を設置したり、「リグロス®」などの成長因子を含んだ薬剤を塗布したりします。これにより、歯周組織が再生するための環境を整え、骨や歯根膜といった歯を支える組織の回復をサポートします。全ての症例に適応できるわけではなく、骨の失われ方など、いくつかの条件を満たす必要がありますが、この治療法によって、歯周病で失われた土台をある程度回復させ、歯の寿命を延ばすことが可能になります。
露出した歯の根を覆う「歯肉移植術(根面被覆術)」という選択肢
歯ぐき下がりによって露出してしまった歯の根は、見た目の問題だけでなく、知覚過敏の原因にもなります。こうした審美的な問題や知覚過敏を改善するために行われるのが、「歯肉移植術(根面被覆術)」です。これは、歯周形成外科という分野の、非常に繊細な技術を要する手術です。一般的には、上あごの口蓋から、ご自身の歯肉(結合組織)を少量採取し、それを歯ぐきが下がってしまった部分に移植します。移植された歯肉は、周囲の組織と結合して生着し、露出していた歯の根を覆い、厚みのある丈夫な歯ぐきを再生します。これにより、見た目が改善され、歯が長く見えるコンプレックスを解消できるほか、知覚過敏の症状も緩和されます。この治療は、特に前歯の見た目が気になる女性にとって、審美的な満足度が非常に高い治療法ですが、歯と歯の間の骨が失われていないなど、適応となる条件があります。
更年期だからと諦めない。健康な歯ぐきを保つための歯科医院との付き合い方

婦人科とも連携。全身の健康を考慮した歯科治療の重要性
更年期におけるお口のトラブルは、女性ホルモンの減少という全身的な変化と深く結びついています。そのため、歯や歯ぐきの問題だけを診るのではなく、全身の健康状態を考慮に入れた、包括的なアプローチが非常に重要になります。特に、骨粗しょう症の治療を受けている場合や、ホルモン補充療法(HRT)を行っている場合などは、その情報が歯科治療計画に大きく影響します。信頼できる歯科医院は、必要に応じて患者様の同意のもと、婦人科や内科のかかりつけ医と連携(医科歯科連携)を取ることを厭いません。例えば、骨粗しょう症のお薬が抜歯などの外科処置に与える影響を考慮したり、全身状態について主治医の意見を求めたりすることで、より安全で質の高い治療を提供することが可能になります。お口の健康は全身の健康の一部です。婦人科と歯科、両方の専門家と手を取り合って、この大切な時期を乗り越えていきましょう。
更年期女性の悩みに寄り添う、かかりつけ歯科医を見つける
更年期は、多くの女性にとって心身ともに様々な変化が訪れる、デリケートな時期です。「歯ぐきが下がる」「口が乾く」「見た目が老けたように感じる」といったお口の悩みも、その変化の一部であり、ご本人にとっては深刻な問題です。だからこそ、この時期の歯科医院選びは、単に技術力が高いだけでなく、あなたの不安や悩みに親身に寄り添ってくれる「かかりつけ歯科医」を見つけることが何よりも大切になります。更年期における女性の身体的・心理的変化への理解があり、「年のせいだから仕方ない」と突き放すのではなく、あなたの言葉に真摯に耳を傾けてくれる歯科医師。そして、歯周病の治療だけでなく、審美的な改善やドライマウスへの対処法など、幅広い選択肢を提示し、あなたと一緒に最適なゴールを目指してくれるパートナー。そんな信頼できる歯科医師との出会いが、更年期以降のお口の健康を大きく左右します。
定期メンテナンスで、お口のわずかな変化を早期に発見する
更年期は、お口の中が「歯周病リスクの高い状態」へと傾きやすい時期です。ホルモンバランスの変化、唾液の減少、骨密度の低下といった複数の要因が重なり、これまで問題がなかった方でも、気づかないうちに歯周病が進行し、歯ぐき下がる現象が始まっている可能性があります。このような変化を放置せず、早期に発見し対処するために不可欠なのが、歯科医院での「定期メンテナンス」です。これは、単なるお掃除ではありません。歯周ポケットの深さや歯ぐきの状態を定期的にチェックし、過去のデータと比較することで、ご自身では気づけないようなわずかな変化をも捉えることができます。そして、変化の兆候が見られた場合には、本格的な問題に発展する前に、予防的な介入を行うことが可能です。お口のトラブルは、早期発見・早期対応が鉄則です。人生100年時代、この先の長い人生を健康な歯で過ごすためにも、定期メンテナンスを生活習慣の一部として取り入れましょう。
【FAQ】更年期の歯ぐき下がりに関するよくあるご質問

Q. 歯ぐき下がりは、セルフケアだけで改善できますか?
A. 非常に重要なご質問です。結論から申し上げますと、一度下がってしまった歯ぐきを、セルフケアだけで元の位置まで「再生」させることはできません。なぜなら、歯ぐき下がりの根本原因は、歯を支える歯槽骨が失われていることにあり、歯磨きで骨を再生させることはできないからです。しかし、セルフケアには極めて重要な役割があります。それは、「これ以上歯ぐきが下がるのを防ぐ」という役割です。歯ぐき下がりの最大の原因である歯周病は、プラーク(歯垢)によって引き起こされます。毎日の丁寧なブラッシングやフロスでプラークを徹底的に除去することは、歯周病の進行にブレーキをかけ、現状を維持し、さらなる悪化を防ぐための最も強力な手段です。セルフケアは「守りのケア」、そして下がった歯ぐきの見た目を改善するには、歯科医院での専門的な「攻めの治療」が必要になるとお考えください。
Q. 歯磨き粉やサプリメントに効果はありますか?
A. 歯周病の進行を抑える有効成分(抗炎症成分や殺菌成分など)を配合した歯磨き粉や洗口剤は、日々のセルフケアを補助する上で、歯ぐきの炎症を和らげるなどの一定の効果が期待できます。しかし、それらはあくまで補助的な役割であり、歯周病の原因となる歯石を除去したり、失われた骨を再生させたりする力はありません。同様に、骨の健康に良いとされるカルシウムやビタミンD、コラーゲンなどのサプリメントも、全身の健康維持には役立ちますが、それだけで歯ぐき下がりが治るという科学的根拠は現時点では確立されていません。最も大切なのは、これらの製品に頼り切るのではなく、基本である「機械的なプラーク除去(正しい歯磨き)」と、歯科医院での「専門的な原因除去治療」を徹底することです。その上で、補助的に活用するのが賢明な付き合い方と言えるでしょう。
Q. 治療には健康保険が適用されますか?
A. 更年期の女性に見られる歯ぐき下がりへの治療は、その目的や内容によって、健康保険が適用されるものと、適用されない自由診療になるものに分かれます。まず、歯ぐき下がりの根本原因である歯周病の進行を食い止めるための治療、すなわち、歯周病の検査、歯石除去(スケーリング・ルートプレーニング)、歯周基本治療、そして基本的な歯周外科手術(フラップ手術など)は、健康保険の適用範囲内です。一方で、失われた骨や歯ぐきを再生させるための「歯周組織再生療法」や、見た目の改善を主目的とした「歯肉移植術(根面被覆術)」といった、より専門性の高い先進的な治療は、健康保険が適用されない自由診療となります。まずは保険診療で歯周病の進行を確実に止め、その上で、ご自身の希望や必要性に応じて自由診療を検討するというのが一般的な流れです。
Q. HRT(ホルモン補充療法)は歯周病に良い影響がありますか?
A. HRT(ホルモン補充療法)は、更年期障害の症状を緩和するために行われる治療法です。近年の研究では、HRTが歯周病の予防や進行抑制に良い影響を与える可能性があると報告されています。これは、歯周病の悪化に深く関わる女性ホルモン「エストロゲン」を補充することで、歯を支える歯槽骨の密度低下を抑制したり、歯ぐきのコラーゲンの減少を防いだりする効果が期待されるためです。実際に、HRTを受けている女性は、受けていない女性に比べて歯周病の進行が緩やかであるという報告もあります。ただし、HRTはあくまで全身的な更年期症状に対する治療であり、「歯周病を治すため」の治療ではありません。お口への良い影響は、副次的な効果と捉えるべきです。HRTを検討される際は、必ず婦人科の主治医と相談し、その上で歯科医師にも情報共有することが大切です。
輝くセカンドライフのために。今日から始めるお口のエイジングケア

女性ホルモンの変化に合わせた、口腔ケア製品の見直し
更年期を迎え、お口の中の環境が変化してきたと感じたら、毎日使う口腔ケア製品を見直すことも有効なエイジングケアの一つです。まず、歯ブラシは「やわらかめ」の毛先のものを選び、歯ぐきを傷つけないようにしましょう。歯ぐき下がりが気になる方は、強い力でのブラッシングは禁物です。歯磨き粉も、ご自身の悩みに合わせて選んでみてください。歯の根が露出してしみる場合は「知覚過敏用」、歯周病予防を強化したい場合は「抗炎症成分」や「殺菌成分」が配合されたもの、お口の乾燥が気になる場合は「低発泡性で保湿成分配合」のものなど、様々な種類があります。特に、露出した歯の根は虫歯になりやすいため、「高濃度フッ素配合の歯磨き粉は、根面う蝕の予防に役立つとされています。アルコールを含む洗口剤は、乾燥を助長することがあるため、ノンアルコールタイプを選ぶと良いでしょう。どの製品がご自身に合うか、歯科医師や歯科衛生士に相談するのもおすすめです。
カルシウムやビタミンD・Kなど、骨を支える食生活のすすめ
歯ぐき下がりの根本原因は、歯を支える歯槽骨が痩せてしまうことです。特に、女性ホルモン(エストロゲン)が減少する更年期は、全身の骨密度が低下しやすいため、骨の健康を支える食生活を意識することが、お口の健康を守ることにも直結します。基本となるのは、骨の主成分である「カルシウム」です。乳製品や小魚、大豆製品などを積極的に摂りましょう。そして、そのカルシウムの吸収を助けるのが「ビタミンD」です。鮭やサンマなどの魚類やきのこ類に多く含まれるほか、日光を浴びることでも体内で生成されます。さらに、骨へのカルシウムの取り込みを促す「ビタミンK」も重要です。納豆やほうれん草などに豊富に含まれています。これらの栄養素をバランス良く摂取し、丈夫な骨の土台を築くことは、歯周病による骨の破壊に抵抗し、歯ぐき下がりを防ぐための、体の中からできる大切なケアなのです。
ストレス管理と良質な睡眠が、お口の免疫力を支える
歯周病は、細菌による感染症です。その進行を食い止めるためには、体の「免疫力」を高く保つことが非常に重要になります。しかし、更年期はホルモンバランスの乱れから、自律神経が不安定になり、ストレスを感じやすくなったり、不眠に悩んだりする女性も少なくありません。慢性的なストレスや睡眠不足は、免疫機能を低下させ、歯周病菌に対する体の抵抗力を弱めてしまいます。また、ストレスは無意識の食いしばりや歯ぎしりを引き起こし、歯や歯ぐきに過剰な負担をかけて、歯周病を悪化させる一因にもなります。ウォーキングなどの軽い運動や、趣味に没頭する時間を作るなど、上手にストレスを管理し、リラックスできる時間を持つこと。そして、質の良い睡眠を十分にとることを心がけましょう。心と体の健康を保つことが、結果的にお口の免疫力を支え、歯周病に負けない強い歯ぐきを作ることにつながるのです。
まとめ:お口の変化は、体からのメッセージ。専門家とともに未来の健康を

更年期は、お口の健康を本気で考える機会です
更年期は、女性にとって心身ともに大きな変化が訪れる重要な節目です。女性ホルモンの減少は歯周病のリスクを高め、歯ぐき下がりを進行させる要因となるため、この時期はお口の健康を見直す絶好の機会といえます。体からの小さなサインを見逃さず、丁寧なセルフケアと定期的な歯科チェックを受けることが大切です。
歯ぐきの悩みは、一人で気軽にご相談ください
『歯ぐきが下がってきた気がする』『口が乾きやすい』『見た目が気になる』といった更年期世代の女性のお口の悩みは、デリケートで人に相談しにくいものです。私たちはその悩みに寄り添い、歯周病や歯ぐき下がりの状態を確認し、原因を突き止め、あなたに合った解決策を一緒に考えていきます。小さな不安も、将来への安心につなげていきましょう。
あなたのライフステージに寄り添う、専門的な診断とケアのご案内
まずは精密な検査で、現在の歯周病リスクや歯ぐき下がりの進行度を把握することから始めます。その結果に基づき、ホルモンバランスの変化も考慮した最適な治療計画や予防プランをご提案します。治療に加えて、日々のセルフケアの方法、食生活のアドバイス、必要に応じた婦人科との連携まで含めたサポートを行います。変化の時期だからこそ、専門家の力を活用することが、今後を健康で美しく過ごすための賢明な選択です。
汐留駅から徒歩5分の歯医者・歯科
患者様の声に耳を傾ける専門の歯科クリニック
監修:《 オリオン歯科 NBFコモディオ汐留クリニック 》
住所:東京都港区東新橋2丁目14−1 コモディオ汐留 1F
電話番号 ☎:03-3432-4618
*監修者
オリオン歯科 NBFコモディオ汐留クリニック東京
ドクター 櫻田 雅彦
*出身大学
神奈川歯科大学
*略歴
・1993年 神奈川歯科大学 歯学部卒
日本大学歯学部大学院博士課程修了 歯学博士
・1997年 オリオン歯科医院開院
・2004年 TFTビル オリオンデンタルオフィス開院
・2005年 オリオン歯科 イオン鎌ヶ谷クリニック開院
・2012年 オリオン歯科 飯田橋ファーストビルクリニック開院
・2012年 オリオン歯科 NBFコモディオ汐留クリニック開院
・2015年 オリオン歯科 アトラスブランズタワー三河島クリニック 開院
*略歴
・インディアナ大学 JIP-IU 客員教授
・コロンビア大学歯学部インプラント科 客員教授
・コロンビア大学附属病院インプラントセンター 顧問
・ICOI(国際口腔インプラント学会)認定医
・アジア太平洋地区副会長
・AIAI(国際口腔インプラント学会)指導医
・UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)インプラントアソシエーションジャパン 理事
・AO(アメリカインプラント学会)インターナショナルメンバー
・AAP(アメリカ歯周病学会)インターナショナルメンバー
・BIOMET 3i インプラントメンター(講師) エクセレントDr.賞受賞
・BioHorizons インプラントメンター(講師)
・日本歯科医師会
・日本口腔インプラント学会
・日本歯周病学会
・日本臨床歯周病学会 認定医
・ICD 国際歯科学士会日本部会 フェロー
・JAID(Japanese Academy for International Dentistry) 常任理事