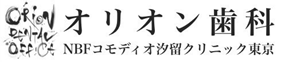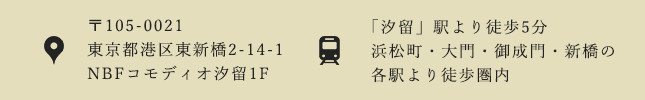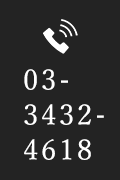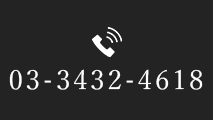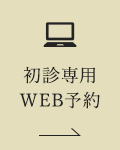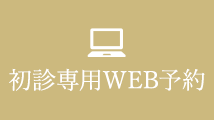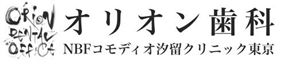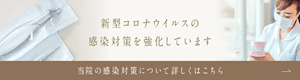「しっかり歯磨きしてるのに…」女性特有のお口の悩み、感じていませんか?

・昔より歯ぐきが腫れやすくなった気がする
毎日丁寧に歯を磨いているし、ケアの方法は変えていないはずなのに、なぜか以前より歯ぐきが腫れやすかったり、ブラッシングの際にじわりと出血したりする。そんなデリケートな変化を感じている女性は少なくありません。「私の磨き方が悪いのかしら」とご自身を責めてしまうこともあるかもしれません。しかし、そのお口の不調は、あなたの努力不足が原因ではない可能性があります。女性の体は非常に繊細で、ライフステージを通じて起こるホルモンバランスの変化が、実はお口の健康状態、特に歯ぐきのコンディションに深く関わっているのです。その関係性を知ることが、悩みを解消する第一歩となります。
・妊娠・出産を機にお口のトラブルが増えた
「子どもを一人産むと歯が一本なくなる」という古い言い伝えを耳にしたことはありますか?これは医学的な事実ではありませんが、多くの女性が妊娠・出産を機にお口のトラブルが急増するという実感を表した言葉と言えるでしょう。つわりで歯磨きが辛くなったり、食事の回数が増えたりといった生活習慣の変化に加え、この時期の体は女性ホルモンの分泌量が大幅に増加します。このホルモンの変化が、歯周病の原因菌の活動を活発にさせ、歯ぐきの炎症を非常に起こしやすくしてしまうのです。これまで何ともなかった方も、妊娠をきっかけに歯ぐきの腫れや出血を経験することが多く、これは「妊娠性歯肉炎」と呼ばれる特有の状態です。
・その不調、あなたのせいではないかもしれません
もしあなたが、丁寧なケアを続けているにも関わらず、歯ぐきの不調に悩まされているのだとしたら、それは決してあなたのせいではないかもしれません。女性の体は、思春期、月経、妊娠・出産、そして更年期といったライフステージごとに、女性ホルモンの分泌量が大きく変動します。そして、このホルモンの波が、お口の環境、特に歯周病への抵抗力に直接的な影響を及ぼすことが、数多くの研究で明らかになっています。つまり、女性のお口の健康を守るためには、日々の歯磨きという「外的要因」のコントロールに加えて、ホルモンバランスという「内的要因」の変化についても正しく理解し、それぞれの時期に合わせた適切なケアを行っていくことが非常に大切なのです。
まずは基本から。そもそも歯周病とはどんな病気?

・歯周病は「細菌」による感染症です
歯周病は、加齢によって誰にでも起こる自然現象ではなく、お口の中にいる特定の「細菌」によって引き起こされる感染症です。歯の表面に付着する、ネバネバとした白っぽい汚れ「歯垢(プラーク)」は、単なる食べかすではありません。これは細菌の塊であり、わずか1mgの歯垢の中には数億個以上もの細菌が生息しています。この歯垢の中に潜む歯周病菌が、歯ぐきに炎症を起こし、さらには歯を支える骨を溶かしていく、これが歯周病の正体です。原因が細菌である以上、お口の中の細菌の数をいかにコントロールするかが、予防と治療の最大の鍵となります。そして、後述しますが、女性ホルモンは、この歯周病菌の活動に影響を与えることが知られており、歯周病のリスクを高める一因となるのです。
・歯ぐきの炎症「歯肉炎」と、骨が溶ける「歯周炎」
「歯周病」という言葉は、実は病気の進行度によって大きく二つの段階に分けられます。初期段階は「歯肉炎(しにくえん)」と呼ばれ、炎症が歯ぐきに限定されている状態を指します。歯磨きの時の出血や、歯ぐきの赤み、腫れなどが主な症状です。この段階では、まだ歯を支える骨に影響は及んでいません。そのため、適切な歯磨きと歯科医院での専門的なクリーニングによって、健康な状態に回復することが可能です。しかし、歯肉炎を放置して炎症がさらに奥深くまで進行し、歯を支える骨(歯槽骨)が破壊され始めた状態を「歯周炎(ししゅうえん)」と呼びます。一度失われた骨を元に戻すのは非常に困難であり、ここまで進行すると、より専門的な治療が必要となります。
・痛みなく進行する「サイレント・ディジーズ(静かなる病気)」
歯周病が本当に怖いのは、初期から中期にかけて、虫歯のようなはっきりとした痛みがほとんどないまま進行することです。「サイレント・ディジーズ(静かなる病気)」という別名があるのは、このためです。歯磨きの時の少しの出血も「いつものこと」と見過ごしてしまいがちです。そして、歯が揺れる、歯ぐきから膿が出る、口臭が強くなるといった自覚症状が現れた時には、すでに歯周炎がかなり進行し、歯を支える骨が大きく失われているケースが少なくありません。特に女性ホルモンの影響で一時的に歯ぐきが腫れやすい時期などは、「体調のせいだろう」と思い込み、根本にある歯周病のサインを見逃してしまう危険性もあります。症状がないから大丈夫、ではなく、症状がないうちに専門家によるチェックを受けることが、お口の健康を守る上で極めて重要です。
女性ホルモンが歯周病菌に与える「3つの影響」

・特定の歯周病菌がホルモンを利用して増殖しやすくなる
歯周病の原因となる細菌は数多く存在しますが、その中には女性ホルモンを“大好物”とする特殊なタイプがいます。その代表格が「プレボテラ・インターメディア(P.i.菌)」と呼ばれる細菌です。この細菌は、自身の増殖のために特定の物質を必要としますが、エストロゲンやプロゲステロンといった女性ホルモンをその栄養源として利用できるのです。そのため、妊娠期や思春期など、体内の女性ホルモン濃度が高まる時期には、歯ぐきからにじみ出る液の中に含まれるホルモンの量も増えます。すると、それを待っていたかのようにP.i.菌が大幅に増殖し、歯ぐきに強い炎症を引き起こしやすくなります。つまり、同じ量の歯垢が付着していても、ホルモンバランスの変化によって歯周病のリスクが格段に高まってしまうのです。
・ホルモンの影響で歯ぐきの血管が拡張し、炎症が起きやすくなる
女性ホルモン、特にエストロゲン(卵胞ホルモン)は、歯ぐきにある毛細血管に直接作用することが知られています。ホルモンの影響を受けると、歯ぐきの血管は拡張し、血液が流れ込みやすい状態になります。これが、月経前や妊娠中に歯ぐきが赤く腫れぼったく見えたり、充血したりする原因です。さらに、血管の壁(血管内皮細胞)も影響を受け、透過性(物質の通り抜けやすさ)が高まります。これにより、プラークからのわずかな刺激に対しても、体は過敏に反応してしまいます。血管から炎症を引き起こす物質や白血球などが漏れ出しやすくなるため、少しのきっかけで出血や腫れといった炎症症状が強く現れるようになります。普段なら何ともない程度のプラーク量でも、女性ホルモンの作用によって歯周病が発症・悪化しやすいデリケートな状態になるのです。
・体の防御機能(免疫応答)の変化
私たちの体には、細菌などの外敵から身を守るための「免疫」という防御システムが備わっています。女性ホルモンは、この免疫システムの働きにも影響を及ぼし、お口の中の防御力を変化させます。例えば、妊娠期には、母体が胎児を異物として攻撃しないよう、免疫機能が全体的に抑制される傾向にあります。この免疫抑制は、お口の中においては、歯周病菌に対する抵抗力を弱めることにつながり、感染が広がりやすくなる一因となります。その一方で、女性ホルモンは炎症を引き起こす化学伝達物質(プロスタグランジンなど)の産生を促す作用も持っています。これにより、細菌に対して過剰な炎症反応が引き起こされ、かえって歯ぐきや歯を支える骨などの組織破壊を進行させてしまう側面もあります。このように、ホルモンは体の防御機能を複雑に変化させ、歯周病に対する抵抗力を不安定にさせるのです。
ライフステージ① 思春期・月経期に見られる歯ぐきの変化

・ホルモンバランスが乱れやすい10代の「思春期性歯肉炎」
思春期は、心と体が大人へと変化する多感な時期ですが、お口の中も例外ではありません。この時期、女性ホルモンの分泌が急激に活発になることで、「思春期性歯肉炎」と呼ばれる特有の歯ぐきの炎症が起こりやすくなります。これは、ホルモンの影響で歯ぐきがプラーク(歯垢)の刺激に対して非常に敏感になり、わずかな汚れでも過剰に反応して、赤く腫れたり、簡単に出血したりする状態です。部活動や勉強で生活が不規則になり、間食が増えたり、歯磨きがおろそかになったりすることも、この傾向に拍車をかけます。しかし、これは一時的な現象であることが多く、この時期に正しいブラッシング方法を身につけ、お口を清潔に保つことの重要性を理解することが、将来的な本格的な歯周病への移行を防ぐ上で極めて大切になります。
・月経前に歯ぐきがうずく、腫れるといった症状
毎月の月経前になると、歯ぐきがむずがゆくなったり、少し腫れぼったく感じたり、あるいは口内炎ができやすくなったりといった経験はありませんか。これもまた、女性ホルモンの周期的な変動が影響しています。排卵後から月経前にかけては、プロゲステロン(黄体ホルモン)の分泌量が増加します。このホルモンは、歯ぐきの血管を拡張させ、炎症を引き起こしやすくする作用があります。そのため、普段は何ともない方でも、この時期は特に歯ぐきがデリケートになりがちです。多くの場合、これらの症状は月経が始まると自然に和らいでいきますが、これはご自身の体が女性ホルモンの影響を受けているという分かりやすいサインです。もし症状が強かったり、毎月繰り返したりする場合は、根底に歯周病が隠れている可能性も考えられます。
・この時期に大切な、基本的なお口のケア習慣
思春期や月経期など、ホルモンバランスの影響で歯ぐきが敏感になっている時期こそ、丁寧なセルフケアが何よりも重要になります。ホルモンの影響そのものを止めることはできませんが、炎症の直接的な引き金となるプラークを徹底的に除去することで、症状をコントロールすることは十分に可能です。大切なのは、ゴシゴシと力任せに磨くのではなく、歯と歯ぐきの境目を意識して、一本一本優しく丁寧に磨くことです。また、歯ブラシだけでは届かない歯と歯の間のプラークは、フロスや歯間ブラシを使って毎日取り除く習慣をつけましょう。この時期に歯科医院でご自身に合った正しいケアの方法を学び、それを生涯にわたる習慣とすることができれば、今後迎える妊娠期や更年期といった、さらに大きなホルモンの波も、上手に乗り越えていくための大きな力となります。
ライフステージ② 妊娠期に特に注意すべき「妊娠性歯肉炎」とは

・つわりで歯磨きが困難に。高まる歯周病リスク
妊娠初期のつわりは、多くの妊婦さんにとって非常につらいものです。体調が優れないだけでなく、匂いに敏感になったり、吐き気をもよおしたりすることで、歯ブラシを口に入れることさえ困難になる場合があります。また、一度にたくさん食べられず食事の回数が増える「食べづわり」も、お口の中に食べかすが残る時間を長くし、プラークが形成されやすい環境を作ります。こうした清掃状態の悪化に加えて、妊娠期は女性ホルモンの分泌量が通常より大幅に増加する。このホルモンの大幅な増加が歯ぐきの炎症を大幅に起こしやすくするため、清掃不良とホルモンの影響という二重の要因で、歯周病のリスクが急速に高まってしまうのです。
・歯周病が早産・低体重児出産に及ぼす影響
お母さんのお口の健康は、お腹の赤ちゃんの健康にも深く関わっています。重度の歯周病にかかっているお母さんは、そうでないお母さんに比べて、早産や低体重児を出産するリスクが数倍高まるという研究報告があります。これは、歯周病によって歯ぐきで産生された炎症性物質(プロスタグランジンなど)が血流にのって全身を巡り、子宮の収縮を促してしまうことが原因の一つと考えられています。また、歯周病菌そのものが血中に入り込むことも、胎盤や赤ちゃんに影響を及ぼす可能性が指摘されています。女性ホルモンの変動で歯周病が悪化しやすい妊娠期に、お口のケアをしっかりと行うことは、ご自身の歯を守るだけでなく、これから生まれてくる大切な赤ちゃんの健やかな成長を守ることにも繋がる、非常に重要な意味を持っているのです。
・安定期が最適。妊娠中の歯科検診と治療の考え方
「妊娠中に歯の治療をしても大丈夫?」とご不安に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、妊娠中の歯科受診は、お母さんと赤ちゃんの両方にとって必要不可欠です。特に、つわりが落ち着き、体調も安定する妊娠中期(安定期:5〜7ヶ月頃)は、歯科治療を受けるのに最も適した時期とされています。この時期であれば、虫歯の治療や歯石の除去といった、ほとんどの一般的な歯科治療を安全に行うことが可能です。治療の際の麻酔や、痛み止めなどの飲み薬についても、妊娠の時期や状態に合わせて、安全に使用できるものを選択します。レントゲン撮影も、防護エプロンを着用すれば、お腹の赤ちゃんへの影響はまずありませんが、原則として緊急性のない場合は出産後に行います。まずは検診を受け、お口の状態を把握し、必要な治療は安定期に行う。これが妊娠中の歯科との上手な付き合い方です。
ライフステージ③ 更年期に訪れるお口の乾燥と骨への影響

・ホルモン減少による唾液の分泌低下(ドライマウス)
更年期を迎え、女性ホルモン(特にエストロゲン)の分泌が減少すると、体の様々な部分に変化が現れますが、お口の中も例外ではありません。女性ホルモンには、体の粘膜の潤いを保つ働きがあり、その減少は唾液の分泌量低下に直結します。唾液が減ってお口の中が乾いた状態を「ドライマウス(口腔乾燥症)」と呼びます。唾液は、単にお口を潤すだけでなく、食べかすを洗い流す「自浄作用」、お口の中の酸性を中和する「緩衝作用」、細菌の増殖を抑える「抗菌作用」など、お口の健康を守る重要な役割を担っています。唾液という天然の防御システムが弱まることで、虫歯菌や歯周病菌が繁殖しやすくなり、虫歯や歯周病のリスクが大幅に高まってしまうのです。
・骨粗しょう症と、歯を支える骨の密接な関係
閉経後の女性ホルモンの減少は、全身の骨密度を低下させ、骨がもろくなる「骨粗しょう症」の主な原因となります。そして、この影響は、歯を支えている顎の骨(歯槽骨)にも及びます。全身的に骨が弱くなっている状態では、歯槽骨の密度も低下し、歯周病による骨の破壊がより速く、より広範囲に進んでしまう危険性が高まります。また、一度失われた骨の再生能力も低下するため、歯周病の治りも悪くなる傾向があります。このように、更年期以降の歯周病管理は、お口の中だけの問題ではなく、全身の骨の健康とも密接に関わってきます。骨粗しょう症の診断を受けている方や、その治療を受けている方は、歯科受診の際に必ずその旨を歯科医師にお伝えください。
・ピリピリ痛む?「バーニングマウス症候群」の可能性
更年期の女性の中には、見た目には明らかな異常がないにもかかわらず、舌や唇、上顎などが「ヒリヒリ」「ピリピリ」と灼けるように痛む症状を訴える方がいます。これは「バーニングマウス症候群(口腔内灼熱症候群)」の可能性があり、女性ホルモンの減少による自律神経の乱れや、味覚・痛覚を伝える神経の変調が関与していると考えられています。これは歯周病とは直接関係のない病態ですが、お口の不快な症状という点では共通しており、生活の質(QOL)を大きく低下させる原因となります。もし、原因不明の舌の痛みなどでお悩みの場合も、まずは歯科医院にご相談ください。入れ歯の不適合やカンジダ症など、他の歯科的な原因がないかを確認し、必要に応じて専門の医療機関と連携して対応いたします。
ホルモンの影響は避けられない?いいえ、正しいケアでコントロールできます

・リスクの高まりは「細菌コントロール」で乗り越える
ライフステージに伴う女性ホルモンの変動は、女性の体にとって自然なことであり、避けることはできません。しかし、ホルモンの影響で歯周病のリスクが高まるからといって、歯ぐきのトラブルを諦める必要は全くありません。重要なのは、ホルモンはあくまで「リスクを高める要因」であり、歯周病の直接的な原因は「細菌(プラーク)」であるという事実です。つまり、ホルモンバランスが変化して歯ぐきが敏感になっている時期こそ、原因である細菌の数を徹底的に減らす「細菌コントロール」を行えば、炎症の発生を抑え込むことが可能なのです。アレルギー体質でも、原因物質に触れなければ症状が出ないのと同じです。ホルモンの影響を受け入れる一方で、ご自身の努力でコントロール可能な細菌の管理に集中すること。それが、ホルモンの波を賢く乗りこなし、お口の健康を守るための最も効果的な戦略です。
・すべての基本となるプラークコントロールの重要性
細菌コントロールの根幹をなすのが、ご自身で毎日行う「プラークコントロール」、すなわち歯磨きです。プラーク(歯垢)は、歯周病菌のすみかそのものです。このプラークをいかに効率よく、かつ確実に取り除くかが、すべての基本となります。特に女性ホルモンの影響で歯ぐきがデリケートになっている時期は、これまで以上に質の高いセルフケアが求められます。「磨いている」と「磨けている」は全くの別物です。歯と歯ぐきの境目にある「歯周ポケット」を狙って優しくブラッシングすること、そして歯ブラシだけでは絶対に届かない歯と歯の間の汚れを、デンタルフロスや歯間ブラシを使って毎日必ず除去すること。この二つを徹底するだけで、お口の中の細菌の数は大幅に減り、歯周病のリスクを大幅に低減させることができます。
・歯科医院での専門的なクリーニングが強力な味方に
毎日の丁寧なセルフケアは非常に重要ですが、残念ながらそれだけでは100%のプラークコントロールは困難です。ご自身ではどうしても磨きにくい場所があったり、気づかないうちにプラークが硬化して「歯石」になってしまったりするからです。歯石は歯ブラシでは除去できない、まさに細菌の砦です。そこで強力な味方となるのが、歯科医院での専門的なクリーニング(PMTC)です。専門家が特殊な器具を用いて、セルフケアでは取り切れないプラークや歯石を徹底的に除去し、お口の環境をリセットします。特に、女性ホルモンの影響を受けやすい時期には、このプロによる定期的な介入が、歯周病の発症・悪化を防ぐための安全策となります。歯科医院を「治療に行く場所」から、「健康を維持するために通う場所」と捉え、ぜひ積極的にご活用ください。
ライフステージ別・今日からできるセルフケアとプロフェッショナルケア

・思春期・月経期:正しいブラッシングの習得と習慣化
ホルモンの影響で歯ぐきが敏感になるこの時期は、自己流の力任せのブラッシングは逆効果です。出血を恐れて歯磨きが不十分になると、プラークが蓄積し、さらに炎症が悪化するという悪循環に陥ります。この時期に最も大切なのは、歯科医院で専門家によるブラッシング指導を受け、「正しい歯磨き」を身につけて習慣化することです。歯と歯ぐきの境目を優しく、しかし確実に清掃する技術と、デンタルフロスなどを用いて歯と歯の間の汚れを取り除くことの重要性を学びましょう。この時期に確立された良い習慣は、一生涯の財産となります。女性ホルモンの波に負けないお口の土台作りのためにも、まずは一度、専門的なチェックと指導を受けることをお勧めします。
・妊娠期:体調に合わせた無理のないケアと、フッ素の活用
妊娠期は、心身ともに大きな変化があり、お口のケアが思うようにいかないことも多いでしょう。特に、つわりで歯磨きが辛い時期は、無理をする必要はありません。体調の良い時間帯を選んだり、ヘッドの小さな歯ブラシを使ったり、一度にすべてを磨こうとせず何度かに分けたりと、工夫してみましょう。また、歯磨きが不十分になりがちな時期だからこそ、「フッ素」の活用が効果的です。フッ素には歯質を強化し虫歯を予防する効果に加え、プラーク中の細菌の活動を抑制する働きもあります。フッ素配合の歯磨剤や洗口液を上手に取り入れましょう。そして何より、体調が安定したら必ず歯科検診を受けてください。プロの手で一度お口の中をリセットすることが、女性ホルモンの影響で高まる歯周病リスクから、お母さんとお腹の赤ちゃんを守ることに繋がります。
・更年期以降:保湿ケアと、骨の健康も意識した生活習慣
女性ホルモンが減少し、唾液が出にくくなる更年期以降は、歯周病だけでなく虫歯のリスクも高まります。セルフケアでは、丁寧なブラッシングに加え、「保湿」を意識することが重要です。こまめな水分補給を心がけるほか、保湿成分の入った洗口液やジェルなどを活用するのも良いでしょう。また、全身の骨密度が低下するこの時期は、歯を支える骨ももろくなりがちです。カルシウムやビタミンD、ビタミンKなどを意識したバランスの良い食事や、適度な運動を心がけるなど、骨の健康を維持する生活習慣が、巡り巡って歯周病の進行を食い止めることにも繋がります。定期的な歯科検診では、お口のクリーニングと共に、唾液量のチェックや粘膜のケアなど、この時期特有のお悩みに合わせたアドバイスも行います。
「女性の歯周病」に関する、よくある質問(FAQ)

・Q. ピル(経口避妊薬)の服用は影響しますか?
A. かつての高用量ピルは、妊娠時と同様に体内の女性ホルモン濃度を大きく上昇させたため、歯ぐきの炎症を助長する副作用が報告されていました。しかし、現在、主に使用されている低用量ピルは、ホルモンの含有量が大幅に少ないため、お口への影響はかなり小さいと考えられています。ほとんどの場合、適切なプラークコントロールができていれば、ピルの服用によって歯周病のリスクが大幅に高まることはありません。ただし、もともと歯肉炎がある方や、歯周病にかかりやすい体質の方では、わずかなホルモンの変化が症状を悪化させる可能性もゼロではありません。ピルを服用している、あるいはこれから服用を始める予定がある場合は、必ず歯科医師および歯科衛生士にお伝えください。より注意深く、お口の状態を管理していくことが大切です。
・Q. 閉経後のホルモン補充療法(HRT)は歯周病に良いですか?
A. 閉経後の女性ホルモンの減少を補うホルモン補充療法(HRT)は、更年期症状の緩和や骨粗しょう症の予防などを目的に行われます。このHRTが、歯周病に対しても良い影響を与える可能性が多くの研究で示唆されています。エストロゲンは、歯を支える骨(歯槽骨)の密度を維持する働きがあるため、HRTによって骨粗しょう症が予防されることは、歯槽骨の破壊を防ぐことにも繋がります。また、HRTが歯ぐきの炎症を抑制し、歯周ポケットの深化を防いだという報告もあります。ただし、HRTは全身状態を考慮して婦人科医の判断で行われる医療です。歯周病治療のためだけにHRTを行うことはありませんが、HRTを受けている方は、その旨を必ず歯科医師に伝え、連携して健康管理を行っていくことが望ましいです。
・Q. 歯周病は遺伝しますか?母から娘への影響は?
A. 歯周病そのものが病気として遺伝するわけではありませんが、「歯周病へのかかりやすさ」という体質(骨格や歯並び、免疫反応の強さなど)が遺伝する可能性はあります。また、親子関係、特に母から娘への影響を考える上では、遺伝的要因に加えて「環境要因」も非常に重要です。同じ家庭で育つことで、食生活や歯磨きの習慣、歯科医院への関心度などが似てくる傾向があります。さらに、歯周病は感染症であるため、唾液を介して原因菌がお母さんからお子さんへ伝播することも起こり得ます。お母様が歯周病で苦労された場合、それは「自分も必ずなる」という運命ではなく、「自分はリスクが高いかもしれない」という注意信号と捉え、より一層、日々のケアと専門家による定期検診を大切にするきっかけとしてください。
・Q. 妊娠前に、どんな歯科治療を済ませておくべきですか?
A. 妊娠を計画されている方には、ぜひ「プレマタニティ歯科検診」をお勧めします。妊娠中は女性ホルモンの影響で歯周病が悪化しやすく、また、つわりなどで治療が困難になる時期もあるため、妊娠前にできるだけお口を健康な状態にしておくことが理想です。具体的には、①虫歯の治療、②歯周病の治療(歯石除去など)、③親知らずの抜歯(炎症を起こすリスクがある場合)の3つが挙げられます。特に、痛みなどの自覚症状がなくても、隠れた歯周病や小さな虫歯が存在するケースは少なくありません。妊娠前にこれらをすべて治療し、正しいセルフケアの方法を身につけておくことで、妊娠期間中のお口のトラブルを最小限に抑え、安心してマタニティライフを送ることができます。これは、未来の赤ちゃんへの大切な準備とも言えるでしょう。
まとめ:体との対話を大切に。しなやかに乗り切るためのかかりつけ歯科医

・女性の体とお口は、一生を通じて変化し続けます
この記事を通じて、女性ホルモンの波が、いかに女性のお口の健康、特に歯周病のリスクに深く関わっているかをお分かりいただけたかと思います。思春期、性成熟期、妊娠・出産期、そして更年期と、女性の体は一生を通じてダイナミックに変化し続けます。そして、お口の中は、その繊細な体の変化を映し出す鏡のような存在です。これまでと同じケアをしているのに、なぜか不調を感じる。その背景には、こうしたホルモンバランスの変化が隠れていることが少なくありません。大切なのは、ご自身の体の変化に耳を傾け、お口の健康管理もまた、ライフステージに合わせてしなやかに変化させていく必要がある、という視点を持つことです。
・ライフステージの変化を、お口の健康を見直す機会に
ホルモンの影響を受けやすい時期は、歯周病のリスクが高まるピンチの時期と捉えがちですが、見方を変えれば、それはご自身のお口の健康と向き合う絶好の「チャンス」でもあります。例えば、妊娠を考え始めた時。それは、生まれてくる赤ちゃんのためにも、お口の中を総点検し、万全の状態を整える良い機会です。更年期を迎え、体の変化を感じ始めた時。それは、これからの人生をより健康に過ごすために、骨の健康まで含めたトータルな視点でお口のケアを見直す良い機会となります。人生の節目節目を、歯科医院に足を運ぶきっかけとすることで、プロアクティブ(主体的)に健康を管理し、歯周病の進行を食い止めることが可能になるのです。
・不安な時はいつでも相談できる「かかりつけ歯科医」というパートナー
女性のライフステージに伴うお口の悩みは、非常にデリケートで、一人で抱え込みがちです。そんな時、あなたの心強い味方となるのが、地域に根ざした「かかりつけ歯科医」の存在です。かかりつけ歯科医は、単に痛みやトラブルがあった時に治療をするだけの場所ではありません。あなたのライフステージの変化を共有し、長期的な視点でお口の健康を見守り、ささいな不安や疑問にも親身に耳を傾ける、人生のパートナーです。ホルモンの影響を受けやすい時期のケア方法から、将来のリスク管理まで、専門的な知識と経験であなたをサポートします。どうぞ一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。それが、健やかで美しい笑顔を生涯にわたって守るための、最も確かな一歩です。
汐留駅から徒歩5分の歯医者・歯科
患者様の声に耳を傾ける専門の歯科クリニック
監修:《 オリオン歯科 NBFコモディオ汐留クリニック 》
住所:東京都港区東新橋2丁目14−1 コモディオ汐留 1F
電話番号 ☎:03-3432-4618
*監修者
オリオン歯科 NBFコモディオ汐留クリニック東京
ドクター 櫻田 雅彦
*出身大学
神奈川歯科大学
*略歴
・1993年 神奈川歯科大学 歯学部卒
日本大学歯学部大学院博士課程修了 歯学博士
・1997年 オリオン歯科医院開院
・2004年 TFTビル オリオンデンタルオフィス開院
・2005年 オリオン歯科 イオン鎌ヶ谷クリニック開院
・2012年 オリオン歯科 飯田橋ファーストビルクリニック開院
・2012年 オリオン歯科 NBFコモディオ汐留クリニック開院
・2015年 オリオン歯科 アトラスブランズタワー三河島クリニック 開院
*略歴
・インディアナ大学 JIP-IU 客員教授
・コロンビア大学歯学部インプラント科 客員教授
・コロンビア大学附属病院インプラントセンター 顧問
・ICOI(国際口腔インプラント学会)認定医
・アジア太平洋地区副会長
・AIAI(国際口腔インプラント学会)指導医
・UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)インプラントアソシエーションジャパン 理事
・AO(アメリカインプラント学会)インターナショナルメンバー
・AAP(アメリカ歯周病学会)インターナショナルメンバー
・BIOMET 3i インプラントメンター(講師) エクセレントDr.賞受賞
・BioHorizons インプラントメンター(講師)
・日本歯科医師会
・日本口腔インプラント学会
・日本歯周病学会
・日本臨床歯周病学会 認定医
・ICD 国際歯科学士会日本部会 フェロー
・JAID(Japanese Academy for International Dentistry) 常任理事