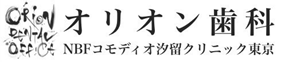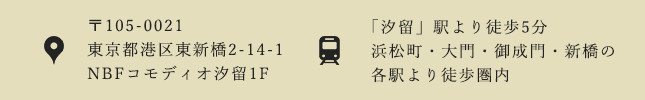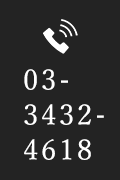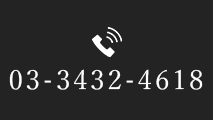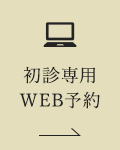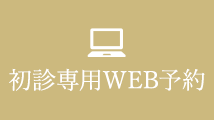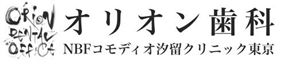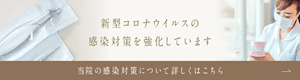1.「噛むとズキッ!」その痛み、本当に虫歯のせいだと信じていますか?

食事のたびに、特定の歯で噛むと「ズキッ」と鋭い痛みが走る。硬いものを避けるようになり、食事を心から楽しめない…。そんな経験はありませんか?歯に痛みを感じた時、私たちの頭に真っ先に浮かぶのは、おそらく「虫歯」という言葉でしょう。そして、「歯医者に行かなければ」と思いつつも、治療の怖さや忙しさを理由に、つい先延ばしにしてしまう。しかし、もしその痛みが、レントゲンにも映らない、全く別の原因から来ていたとしたら…?実は、「噛むと痛い」という症状を訴えて来院される患者様の中には、虫歯が見当たらないケースが少なくないのです。そして、多くの方がその「原因不明の痛み」に長期間悩み、不安な日々を過ごされています。この記事では、そんな“虫歯じゃないのに噛むと痛い”という、厄介な症状の裏に隠された、見逃されがちな「もうひとつの原因」について、専門家の視点から深く、そして分かりやすく解き明かしていきます。
2.なぜ痛む?「噛む」という行為で歯に何が起きているのか

「噛むと痛い」―このシンプルな症状の裏側では、一体何が起きているのでしょうか。私たちは毎日、ほとんど無意識に「噛む」という行為を繰り返していますが、その一瞬一瞬に、お口の中では驚くほど精巧なメカニズムが働いています。そして、そのメカニズムのどこかに異常が生じた時、体は「痛み」というシグナルを発して、私たちに危険を知らせます。「噛むと痛いのに虫歯じゃない」という不可解な現象を理解するためには、まず、この「噛む」という行為の舞台裏で活躍する、重要な登場人物の存在を知る必要があります。それは、単に歯や骨だけでなく、それらをつなぎ、守るための、驚くべき機能を持った組織です。ここでは、痛みの謎を解く鍵となる、お口の中のミクロの世界へとご案内します。この基本的な仕組みを知ることが、あなたの痛みの原因を理解するための、最初の、そして最も重要なステップとなるでしょう。
歯と骨のクッション役「歯根膜」の存在
私たちの歯は、顎の骨にセメントで固められたように、直接植わっているわけではありません。実は、歯の根っこ(歯根)と、それを支える顎の骨(歯槽骨)との間には、「歯根膜(しこんまく)」と呼ばれる、非常に薄い(約0.2mm)けれども強靭な繊維組織が介在しています。この歯根膜は、歯と骨をハンモックのようにつなぎとめる、無数のコラーゲン線維の束でできています。そして、この組織こそが、「噛む」という行為において、極めて重要な役割を果たしているのです。歯根膜の最大の役割は、噛んだ時に歯にかかる強大な力を吸収し、分散させる「クッション」としての機能です。もしこのクッションがなければ、硬いものを噛んだ時の衝撃が骨に直接伝わり、歯や骨はすぐにダメージを受けてしまうでしょう。さらに、歯根膜の中には、血管や神経が豊富に分布しています。この神経は、非常に敏感なセンサーであり、食べ物の硬さや食感を瞬時に脳に伝える役割を担っています。「お米の中に紛れた小石」に気づけるのも、この歯根膜の鋭敏な感覚のおかげです。そして、このセンサーは、歯にかかる力が異常であったり、歯の周りに何らかのトラブルが起きたりした際に、「痛み」という警告を発する、重要な警報装置でもあるのです。
正常な“噛む力”と、異常な“噛む力”
私たちは、食事の際に、自分の体重とほぼ同じくらいの力で噛んでいると言われています。奥歯では、瞬間的に60kg以上の力がかかることもあります。歯根膜は、この正常な「噛む力(咬合力)」をうまく受け流し、骨に伝えるように設計されています。食事の時に歯と歯が接触している時間は、1日トータルでも20分に満たないとされています。つまり、歯根膜は、強い力がかかっても、その間に十分な休息時間があるため、ダメージから回復することができるのです。しかし、このバランスが崩れ、「異常な力」が、あるいは「異常な時間」、歯にかかり続けると、事態は一変します。例えば、無意識の「歯ぎしり」や「食いしばり」です。これらは、食事の時の何倍もの力(時には100kg以上)が、長時間にわたって歯にかかり続ける異常な状態です。また、高さの合わない詰め物や被せ物があると、特定の歯だけに噛む力が集中してしまいます。このような「異常な力」に晒され続けると、歯根膜のクッション機能は限界を超え、組織はダメージを受け、炎症を起こしてしまいます。まるで、長時間正座をした後の足がジンジンと痛むように、歯根膜は常に圧迫され、血行が悪くなり、悲鳴を上げ始めるのです。
歯根膜が発する「痛み」という警告信号
「噛むと痛い」という症状の多くは、この「歯根膜」が炎症を起こしていること(歯根膜炎)が直接的な原因です。虫歯が進行して歯の神経(歯髄)にまで達した場合の痛みは、何もしなくてもズキズキと痛む「自発痛」が特徴です。これに対し、歯根膜の痛みは、普段は何ともないのに、噛むという圧力がかかった時にだけ、「ズキッ」「ジン」といった痛みを感じるのが特徴です。なぜなら、噛むことで炎症を起こしている歯根膜が圧迫され、その中にある痛みを感じる神経(痛覚受容器)が刺激されるからです。この痛みは、歯根膜からの「これ以上、この歯に力をかけないで!」「この歯の周りで何か異常が起きています!」という、体からの明確な警告信号です。この警告の背景には、歯周病の進行、過剰な噛み合わせの力、あるいは歯そのものにひびが入っているなど、様々な原因が隠されています。つまり、「噛むと痛いのに虫歯じゃない」という症状は、歯の神経ではなく、その土台である「歯根膜」が発しているSOSサインである可能性が高いのです。このサインを見逃さず、その根本原因を突き止めることこそが、問題解決への唯一の道となります。
3.虫歯じゃないのに痛い。考えられる5つの原因

「噛むと痛い」という症状で歯科医院を訪れたけれど、「レントゲンを撮っても虫歯は見当たりませんね」と言われてしまった。そんな経験はありませんか?患者様にとっては、痛みという紛れもない事実があるのに、その原因が分からないというのは、非常にもどかしく、不安なものです。しかし、前の項目でお話ししたように、痛みの震源地が歯の神経(歯髄)ではなく、その周りのクッション役である「歯根膜」にあると考えれば、この不可解な現象の謎が解けてきます。歯根膜に炎症を引き起こし、「噛む」という圧力によって痛みを発生させる原因は、虫歯以外にも数多く存在するのです。それらは、目に見えないほど小さな歯のひびであったり、日々の無意識の癖であったり、あるいは、お口全体のバランスの崩れであったりと、多岐にわたります。ここでは、私たち歯科医師が「虫歯じゃないのに噛むと痛い」という訴えをお聞きした際に、鑑別診断のリストに挙げる代表的な5つの原因について、一つひとつ詳しく解説していきます。あなたのその痛みが、この中のどれかに当てはまるかもしれません。
原因①:知覚過敏(象牙質知覚過敏症)
「冷たいものがしみる」という症状で知られる知覚過敏ですが、実は「噛んだ時の痛み」の原因となることもあります。私たちの歯は、一番外側を硬い「エナメル質」が覆っていますが、その内側には「象牙質」という柔らかい組織があります。この象牙質には、歯の神経(歯髄)につながる無数の小さな管(象牙細管)が通っています。何らかの原因でエナメル質が削れたり、歯周病で歯ぐきが下がって歯の根が露出したりすると、この象牙質が剥き出しになります。その状態で、噛むという圧力がかかると、象牙細管の中にある液体が動き、神経を刺激して「キーン」とした鋭い痛みを感じることがあるのです。これは、冷たい水や歯ブラシの刺激だけでなく、噛むという物理的な圧力によっても引き起こされる現象です。特に、歯ぎしりや食いしばりによって歯の表面がすり減ってしまっている方や、歯周病が進行している方では、噛んだ時の知覚過敏症状が現れやすくなります。虫歯の痛みと似ていますが、比較的瞬間的で、鋭い痛みが特徴です。
原因②:歯周病の進行
歯周病は、歯ぐきの出血や腫れを引き起こすだけでなく、進行すると「噛んだ時の痛み」の直接的な原因となります。歯周病は、歯を支える顎の骨(歯槽骨)を溶かしてしまう病気です。病気が進行すると、歯を支える骨が少なくなり、歯がグラグラと動揺し始めます。この状態で食べ物を噛むと、不安定な歯が沈み込むように動き、歯根膜に異常な力がかかって、鈍い痛みを感じるようになります。まるで、ぐらついた杭を無理やり地面に押し込むようなものです。さらに、歯周病が重症化し、歯と歯ぐきの間の溝(歯周ポケット)が深くなると、その中で細菌が繁殖し、膿が溜まることがあります(歯周膿瘍)。こうなると、歯ぐきがパンパンに腫れ、噛むどころか、少し触れただけでも激しい痛みを感じるようになります。初期の歯周病では痛みはほとんどありませんが、「噛むと歯が浮いたような感じがする」「鈍い痛みが続く」といった症状が出てきた場合、それは歯周病がかなり進行し、歯の土台そのものが揺らぎ始めている危険なサインかもしれません。
原因③:歯ぎしり・食いしばり(TCH)による過剰な負担
自覚している、していないに関わらず、現代人の多くが抱えている問題が、「歯ぎしり」や「食いしばり」です。特に、日中に無意識のうちに上下の歯を接触させ続ける癖は「TCH(Tooth Contacting Habit:歯列接触癖)」と呼ばれ、近年、様々な歯のトラブルの原因として注目されています。私たちの歯は、食事や会話の時以外、リラックスしている状態では上下の歯の間にわずかな隙間(安静空隙)があり、接触していません。しかし、ストレスや集中などによって、このTCHが習慣化すると、歯とそれを支える歯根膜には、持続的に、そして過剰な力がかかり続けることになります。これは、歯にとって一種の「オーバーワーク」状態です。この過剰な負担によって、歯根膜は慢性的な炎症を起こし、血行不良に陥ります。その結果、普段は何ともないのに、食事で噛むという「追い打ち」の力が加わった瞬間に、ズキッとした痛みとして症状が現れるのです。朝起きた時に顎がだるかったり、原因不明の頭痛や肩こりに悩んでいたりする方は、夜間の歯ぎしりや日中の食いしばりが、あなたの歯を痛めつけている最大の犯人である可能性を疑う必要があります。
原因④:不適合な詰め物・被せ物による噛み合わせの異常
お口の中全体の噛み合わせは、ミクロン単位の非常に繊細なバランスの上に成り立っています。しかし、過去に行った治療で入れた詰め物や被せ物の高さが、ほんの少しでも周囲の歯より高かったり、形が合っていなかったりすると、そのバランスは簡単に崩れてしまいます。これを「早期接触」や「咬合性外傷(こうごうせいがいしょう)」と呼びます。たった一本の歯だけが、他の歯よりも先に、そして強く当たってしまう状態です。この状態では、噛むたびに、その歯にだけ集中的に過大な力がかかり、歯根膜に大きなダメージを与えます。まるで、一点だけに体重が集中するハイヒールで、長時間踏みつけられているようなものです。最初は違和感程度だったものが、時間の経過とともに歯根膜の炎症を引き起こし、「噛むと痛い」という明確な症状として現れてきます。治療したばかりの時は問題なくても、長年の使用で周りの歯がすり減ったり、わずかに移動したりすることで、相対的に詰め物が高くなってくることもあります。原因不明の痛みを訴える歯に、過去に治療した銀歯などが入っている場合、この噛み合わせの不調和が原因であるケースは非常に多いのです。
原因⑤:歯の破折(ひび・亀裂)
そして、虫歯以外で「噛むと痛い」という症状を引き起こす、最も診断が難しく、そして見逃されやすい原因が、歯そのものに入った「ひび(クラック)」や「亀裂」です。歯は人体で最も硬い組織ですが、決して割れないわけではありません。特に、神経を取る治療(根管治療)をした歯は、血液の供給がなくなるため、枯れ木の枝のように脆くなり、破折のリスクが高まります。また、健康な歯であっても、歯ぎしりなどの過剰な力や、硬いものを噛んだ時の衝撃、あるいは加齢によって、目には見えないほどの微細なひび(マイクロクラック)が入ることがあります。このひびが入った状態で噛むと、歯がたわんで、ひびがわずかに開きます。その刺激が内部の神経に伝わったり、ひびの隙間から細菌が侵入して歯根膜に炎症を起こしたりすることで、噛んだ時にだけ鋭い痛みを感じるのです。この痛みは、噛むのをやめるとすぐに消えることが多く、また、噛む角度によって痛んだり痛まなかったりするため、「気のせいかな?」と放置されがちです。しかし、この小さなひびこそが、後に深刻な問題を引き起こす、非常に危険なサインなのです。
4.最大の容疑者?目に見えない“歯のひび”「歯根破折」の恐怖

「噛むと痛いのに、虫歯じゃない」―この不可解な症状を解明する上で、私たち歯科医師が常に最大の容疑者の一つとして念頭に置くものがあります。それは、レントゲンにも映りにくく、肉眼ではほとんど見つけることができない、歯に入った微細な「ひび割れ」、すなわち**「歯の破折(はせつ)」**です。食器に小さなひびが入っていると、普段は問題なくても、力を加えた瞬間にピシッと割れてしまうことがありますよね。歯にも、全く同じことが起こるのです。特に、歯の根の部分(歯根)にまで達するひび割れは「歯根破折(しこんはせつ)」と呼ばれ、診断が非常に困難であると同時に、歯の寿命を左右する、極めて深刻なトラブルです。患者様ご自身は、もちろんその存在に気づいていません。「原因不明の痛み」に長年悩み、いくつもの歯科医院を渡り歩いた結果、ようやくこの「歯のひび」が原因だと判明するケースも少なくないのです。ここでは、なぜこの目に見えない小さなひびが、これほどまでに厄介で、そして恐ろしいのか。その正体と、放置した場合に待ち受ける未来について、詳しく掘り下げていきます。
・なぜ歯にひびが入るのか?加齢、過去の治療、そして過剰な力
ダイヤモンドに次ぐ硬さを誇るエナメル質を持つ歯が、なぜ割れてしまうのでしょうか。その原因は一つではなく、複数の要因が複雑に絡み合って発生します。
①過去の治療、特に神経を取った歯:
歯にひびが入る最大のリスク因子は、過去の「根管治療(神経を取る治療)」です。歯の神経(歯髄)は、歯に栄養や水分を供給する役割も担っています。神経を取った歯は、この供給が絶たれるため、時間が経つにつれて、まるで枯れ木の枝のように、もろく、弾力性を失っていきます。そこに、金属の土台(メタルコア)などが挿入されていると、噛む力がくさびのように働き、歯を内側から引き裂くような力がかかりやすくなります。これが、歯根破折の最も典型的なパターンです。
②過剰な力(歯ぎしり・食いしばり):
たとえ神経が残っている健康な歯であっても、歯ぎしりや食いしばりによって、日常的に体重以上の過大な力がかかり続ければ、金属疲労のように、歯の内部に微細なダメージが蓄積していきます。この繰り返し応力が、やがて目に見えないひび(マイクロクラック)を生じさせるのです。
③その他(外傷・加齢など):
転倒などで歯を強くぶつけた経験や、硬いものを不用意に噛んでしまった時の衝撃も、ひびの原因となります。また、加齢とともに歯そのものがもろくなってくることも、リスクを高める一因と考えられています。これらの要因が複合的に作用し、ある日突然、歯の耐久力の限界を超えた時に、破折は起こるのです。
レントゲンでも見つけにくい「マイクロクラック」
歯のひびが厄介である最大の理由は、その発見が極めて困難であることに尽きます。虫歯であれば、レントゲン写真に黒い影として映ることが多いですが、髪の毛よりも細いような歯のひびは、初期の段階ではレントゲンに全く映りません。ひびが大きく広がり、骨にまで影響が及んで初めて、レントゲン上で異常として認識できることもありますが、その時点ではすでに手遅れに近い状態であることも少なくありません。また、ひびは歯の内部で発生するため、歯科医師がミラーで口の中を覗き込んでも、直接見ることはほとんど不可能です。痛みがあるのに、レントゲンは正常、見た目も問題ない―。これが、「原因不明」とされる所以です。患者様は、「噛む角度によって痛んだり、痛まなかったりする」「特定の硬さのものを噛んだ時だけ、ピリッと痛む」といった、曖昧で再現性の低い症状を訴えることが多く、診断はさらに困難を極めます。この「見つけにくさ」が、問題を長期間放置させてしまう最大の原因となり、水面下で静かに、しかし着実に、歯の崩壊を進めていくのです。
歯根破折が引き起こす、根の先の膿と抜歯のリスク
目に見えないほどの小さなひびでも、それを放置すると、やがて深刻な事態を引き起こします。歯に入ったひび割れは、お口の中の細菌にとって、格好の侵入経路となります。ひびの隙間から細菌が歯の内部、そして歯根の先にまで侵入すると、そこで感染を起こし、歯根の先端部分の骨を溶かして、膿の袋(根尖病巣:こんせんびょうそう)です。接着剤で修復を試みる治療法もありますが、成功率は決して高くありません。多くの場合、周囲の骨へのさらなる感染拡大を防ぐために、最終的に「抜歯」という、最も避けたい結論に至らざるを得ないのです。「噛むと痛い」という小さなサインを見過ごし続けた結果、残せたはずの大切な歯を失ってしまう。これこそが、歯根破折という「静かなる時限爆弾」の、本当の恐怖なのです。
5.あなたの「噛むクセ」は大丈夫?無意識の悪習慣セルフチェック

「噛むと痛い」という症状の背景には、歯ぎしりや食いしばりといった「過剰な力」が関わっていることが多い、とお話ししてきました。しかし、そうお伝えすると、多くの方が「でも、私は歯ぎしりなんてしていません」とおっしゃいます。それもそのはず。夜間の歯ぎしりや、日中の食いしばりは、そのほとんどが「無意識」のうちに行われているため、自覚症状がないのが当たり前なのです。自分では気づいていない、その静かなる悪習慣が、あなたの歯に毎日、毎晩、じわじわとダメージを与え続け、痛みの原因となっているのかもしれません。では、どうすればその無意識のサインに気づくことができるのでしょうか。実はお口の中や、あなたの体には、その「噛むクセ」の痕跡が、様々な形で現れています。まるで、事件現場に残された犯人の指紋のように、それらは雄弁に、あなたの癖の存在を物語っているのです。ここでは、ご自身でできる簡単なセルフチェックリストをご用意しました。鏡を見ながら、あるいはご自身の体の感覚に耳を澄ませながら、当てはまる項目がないか、ぜひ確認してみてください。このチェックが、あなたの痛みの謎を解く、意外な手がかりになるかもしれません。
日中、気づくと上下の歯が接触している(TCH:歯列接触癖)
今、この記事を読んでいるこの瞬間、あなたの上下の歯はどうなっていますか?軽く触れ合っていますか?それとも、少し隙間が空いていますか?実は、人間の口は、リラックスしている状態では、唇は閉じていても、上下の歯の間には1〜3mm程度の隙間が空いているのが正常です。これを「安静空隙(あんせいくうげき)」と呼びます。食事や会話の時以外、歯が接触している必要は全くありません。しかし、パソコン作業に集中している時、スマートフォンを眺めている時、あるいは家事をしている時など、ふと気づくと、上下の歯が「カチッ」と軽く接触していたり、「グッ」と噛みしめていたりすることはありませんか。これが、近年問題視されているTCH(Tooth Contacting Habit:歯列接触癖)です。たとえ軽い力であっても、歯が持続的に接触し続けると、歯や歯根膜、そして顎の筋肉は、常に緊張状態に置かれ、休まる暇がありません。1日にトータルで何時間もこの状態が続けば、歯根膜は疲弊し、炎症を起こして、噛んだ時の痛みを引き起こす大きな原因となります。まずは、日中の生活の中で、ご自身の上下の歯がどうなっているかを、意識的にチェックする習慣をつけてみてください。ポストイットなどに「歯を離す」と書いて、よく目につく場所に貼っておくのも効果的です。
朝起きた時、顎がだるい、または疲れている感じがする
夜間の歯ぎしりや食いしばり(ブラキシズム)は、本人が眠っている間に行われるため、自覚するのが最も難しい癖の一つです。しかし、その痕跡は、朝、目覚めた時のあなたの体に現れます。もし、朝起きた時に、①顎の関節(耳の前あたり)や、頬の筋肉がだるい、重い、あるいは痛いと感じる、②口が開きにくい、③原因不明の頭痛(特にこめかみあたり)や、首・肩のこりが慢性的にある、といった症状があれば、それは夜間に無意識のうちに、相当な力で歯ぎしりや食いしばりをしている可能性が非常に高いサインです。睡眠中の歯ぎしりでは、食事の時の何倍もの力、時には100kgを超えるような異常な力が、長時間にわたって歯と顎にかかります。これは、まるで一晩中、筋力トレーニングをしているようなものです。朝、顎の筋肉が疲労しているのは当然の結果と言えるでしょう。この破壊的な力は、歯をすり減らし、歯にひびを入れ、詰め物や被せ物を壊し、そして歯根膜に深刻なダメージを与えます。「噛むと痛い」という症状は、この夜間の過酷な労働によって悲鳴を上げている歯からの、当然の訴えなのかもしれません。ご家族に、寝ている間の歯ぎしりの音を指摘されたことがある方は、間違いなく要注意です。
歯の先端がすり減って、平らになってきた
あなたの「噛むクセ」は、歯の形そのものにも、動かぬ証拠を刻みつけます。鏡でご自身の歯、特に前歯や犬歯の先端をじっくりと見てみてください。若い方の健康な歯は、先端にある程度の丸みや凹凸があります。しかし、長年にわたって歯ぎしりや食いしばりを続けていると、上下の歯がヤスリのようにこすれ合い、歯の最も硬いエナメル質が徐々にすり減っていきます。その結果、歯の先端が、まるで削られたように平らになってきます。これを「咬耗(こうもう)」と呼びます。さらにすり減りが進行すると、エナメル質の内側にある黄色い象牙質が露出し、歯の先端が黄色っぽく見えたり、凹んでいるように見えたりすることもあります。奥歯でも同様に、本来あるはずの複雑な溝や山が摩耗し、全体的に平坦な形になってきます。この咬耗は、あなたの歯に、長期間にわたって異常な力がかかり続けてきたことを示す、最も分かりやすい物証です。歯がこれだけすり減っているのですから、その下にある歯根膜がダメージを受けていないはずがありません。「噛むと痛い」という症状と、この歯のすり減りは、同じ原因から生じている、表裏一体のサインである可能性が極めて高いのです。
頬の内側や舌に、歯の痕がついている
もう一つ、簡単にご自身でチェックできるサインがあります。それは、頬の内側の粘膜や、舌の側面です。鏡で「イーッ」と口を横に広げた時に、頬の内側、ちょうど上下の歯が噛み合うあたりの高さに、白い横一線のスジがついていませんか?これは「圧痕(あっこん)」あるいは「咬合線(こうごうせん)」と呼ばれるもので、日中や夜間に、無意識に歯を食いしめることで、頬の粘膜が歯列に強く押し付けられてできる歯の痕です。同様に、舌の縁(側面)を見てみてください。そこに、歯の形に沿った、ギザギザ、あるいは波状の痕がついていませんか?これも、舌が歯列に強く押し付けられている証拠です。これらのサインがあるということは、あなたが思っている以上に、あなたの口の周りの筋肉が常に緊張し、歯を強く噛みしめる癖があることを示唆しています。頬や舌にこれだけはっきりと痕がつくほどの力が、四六時中、あなたの歯にかかっていると想像してみてください。歯根膜が悲鳴を上げるのも、無理はないと思いませんか。この頬や舌の圧痕は、あなたの無意識の癖を可視化してくれる、非常に重要な手がかりなのです。
6.歯科医院ではどう見つける?原因不明の痛みを突き止める精密検査

「噛むと痛いのに、虫歯は見当たらない」―この厄介で、そして不安な状況を解決するためには、痛みの真の原因を正確に突き止める「診断」のプロセスが何よりも重要になります。それは、まるで優秀な探偵が、難事件の真相を解明していく作業によく似ています。患者様の訴えという「証言」に耳を傾け、お口の中に残された様々な「物証」を丁寧に拾い集め、そして、最新の科学捜査機器を駆使して、目には見えない決定的な「証拠」を掴み出す。私たち歯科医師は、日々の診療で、まさにこのようなアプローチで、原因不明の痛みの謎に挑んでいます。何となくの勘や経験だけに頼るのではなく、科学的根拠に基づいた体系的な検査を行うことで、隠された真実を一つひとつ明らかにしていきます。ここでは、あなたが歯科医院を訪れた際に、私たちがどのような“捜査”を行い、痛みの原因を特定していくのか、その具体的な精密検査の内容について、詳しくご紹介します。このプロセスを知ることで、あなたは「原因不明」という暗闇の中から、確かな光が見えてくるのを感じられるはずです。
視診・触診:詰め物の段差や、歯の揺れを確認
すべての診断は、最も基本的でありながら、最も重要な「視診」と「触診」から始まります。これは、探偵がまず事件現場をくまなく観察するのと同じです。私たちは、ミラーやライトを使い、痛みを訴えている歯とその周りの状態を、注意深く観察します。
・視診: 歯の色に変色はないか、歯ぐきに腫れや赤み、膿の出口(サイナストラクト)はないか、詰め物や被せ物の縁に隙間や段差はないか、そして、歯の表面に目に見えるひび(クラックライン)が入っていないか、といったことを詳細にチェックします。染色液を使って、微細なひびを染め出して確認することもあります。
・触診: 次に、ピンセットのような器具を使って、歯を様々な方向から優しく揺さぶってみます。これにより、歯がどの程度動揺しているのか、そのグラつき具合を確認します。歯周病が進行していたり、歯根が割れていたりすると、特定の方向に異常な揺れが見られることがあります。また、指で歯ぐきを押してみて、痛みや膿が出るかどうかも確認します。
咬合検査:噛み合わせのバランスと、強く当たっている場所を特定
「噛むと痛い」という症状の原因を探る上で、絶対に欠かせないのが「咬合(こうごう)検査」、つまり、噛み合わせのバランスを調べる検査です。特定の歯だけに過剰な力がかかっていないか、いわば「犯人探し」を行います。そのために、私たちは「咬合紙」という、色のついた薄いセロハンのような紙を使います。この紙を歯の間に挟んで、カチカチと噛んでもらったり、ギリギリと歯ぎしりをしてもらったりします。すると、上下の歯が強く接触している部分にだけ、色が濃く付着します。
この色の付き具合を見ることで、①どの歯が、他の歯よりも先に、そして強く当たっているのか(早期接触)、②歯ぎしりをした時に、どの歯に有害な横方向の力がかかっているのか、といった、噛み合わせの力のかかり具合を、一目瞭然で可視化することができるのです。もし、痛みを訴えている歯にだけ、クッキリと濃い色の印が付いたならば、その歯にかかる「過剰な力」が痛みの原因である可能性が非常に高いと推測できます。
歯科用CT検査:レントゲンでは見えない歯のひびや、骨の状態を3次元で解析
視診や触診、咬合検査でも原因が特定できない、より複雑なケース。特に、目に見えない歯のひび(マイクロクラック)や、歯根の破折が強く疑われる場合に、絶大な威力を発揮するのが「歯科用CT」です。これは、いわば科学捜査におけるDNA鑑定のような、決定的な証拠を掴むための切り札です。
CT画像を解析することで、①レントゲンでは捉えきれない、歯の内部や歯根表面の微細なひび割れ、②歯根の周りの骨が、どの部分で、どの程度溶けているのか(骨吸収の状態)、③歯根の先にできた膿の袋(根尖病巣)の正確な大きさや広がり、といった情報を、立体的に、そして極めて詳細に把握することができます。
マイクロスコープ(歯科用顕微鏡):肉眼の数十倍の視野で、微細な亀裂を発見
歯科用CTが歯の内部や骨の状態を“透視”する検査だとすれば、「マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)」は、歯の表面を極限まで拡大して“直視”する検査です。マイクロスコープは、治療部位を肉眼の最大20倍以上にまで拡大し、さらに強力な光で明るく照らし出すことができるため、これまで「見えないから分からない」とされてきた世界を、鮮明に映し出してくれます。
特に、歯の表面に入ったマイクロクラックの診断において、その威力は絶大です。肉眼では決して見ることのできない、髪の毛ほどの細さのひび割れ(クラックライン)も、マイクロスコープの拡大視野下では、明確な一本の線として確認することができます。そのひびが、歯の表面のエナメル質だけに留まっているのか、それとも内部の象牙質にまで達しているのか、あるいは詰め物の下にまで続いているのか。その深さや範囲を直接観察することで、痛みの原因を確定診断し、ひびの深刻度に応じた最適な治療法を、より正確に判断することができるのです。
7.原因別・痛みの対処法と治療の選択肢

原因不明という暗闇の中を手探りで進むような不安な日々は、精密な検査と診断によって、ついに終わりを告げます。あなたの痛みの「真犯人」が特定された今、次なるステップは、その原因に対して、いかに的確で効果的なアプローチを行うか、という「治療」のフェーズです。虫歯ではない痛みの原因が多岐にわたるように、その治療法も一つではありません。歯周病が原因なのか、過剰な力が原因なのか、あるいは歯のひびが原因なのか。その根本原因に応じて、治療の選択肢は大きく異なってきます。それは、病名に応じて処方する薬が変わるのと全く同じです。ここでは、これまでお話ししてきた代表的な原因別に、どのような治療法が存在するのか、その具体的な選択肢について解説していきます。あなたの痛みの原因に合わせた「処方箋」を知ることで、治療への理解が深まり、これから始まる回復への道のりを、より前向きな気持ちで歩んでいけるはずです。
歯周病が原因の場合:歯周基本治療で炎症をコントロール
検査の結果、痛みの原因が「歯周病の進行」によるものだと判明した場合、治療の主眼は、歯ぐきや歯を支える組織の「炎症をコントロールする」ことに置かれます。歯周病は細菌による感染症ですので、その原因であるプラーク(歯垢)と、その温床となる歯石を徹底的に除去する「歯周基本治療」が治療の中心となります。
①ブラッシング指導(TBI): まず、最も重要なのが、あなた自身による日々のセルフケアの改善です。染め出し液などを使って、どこに磨き残しがあるのかを可視化し、あなたのお口の状態に合った、効果的な歯ブラシの当て方や、デンタルフロス・歯間ブラシの使い方を、歯科衛生士が丁寧に指導します。
②スケーリング&ルートプレーニング: ご自身の歯磨きでは取り除くことのできない、硬くこびりついた歯石や、歯周ポケットの奥深くに潜むプラークを、専用の器具を使って徹底的に除去します。これにより、炎症の原因となる細菌の数を劇的に減らし、歯ぐきが引き締まって健康な状態に戻るのを促します。
歯ぎしり・食いしばりが原因の場合:マウスピース(ナイトガード)による力の分散
診断の結果、あなたの歯にかかる「過剰な力」、すなわち歯ぎしりや食いしばり(ブラキシズム)、TCH(歯列接触癖)が痛みの主犯だと特定された場合、治療の目的は、その破壊的な力から歯を守り、歯根膜や顎の筋肉への負担を軽減することになります。
①マウスピース(ナイトガード)療法:
最も一般的で効果的な治療法が、夜間睡眠中に装着する、オーダーメイドの「マウスピース(ナイトガード)」です。あなたの歯型に合わせて作製した、弾力のある樹脂製のマウスピースを装着することで、上下の歯が直接強く接触するのを防ぎます。これにより、歯ぎしりの力をマウスピース全体で受け止め、特定の歯にかかる力を分散させることができます。また、歯のすり減りを防止する効果もあります。保険適用で作製が可能です。
②咬合調整:
噛み合わせの検査で、特定の歯だけが強く当たっている「早期接触」が見つかった場合は、その部分をほんのわずか(数ミクロン単位)だけ慎重に削って、全体の噛み合わせのバランスを整える「咬合調整」を行うこともあります。
③TCHの是正指導:
日中の食いしばり(TCH)が原因の場合は、「歯を離す」ことを意識づける行動療法が中心となります。リラックスしている時は上下の歯に隙間があるのが正常であることをお伝えし、生活の中で意識していただくよう指導します。
歯のひびが原因の場合:破折の深さに応じた治療(接着、被せ物、抜歯)
精密検査の結果、痛みの原因が「歯のひび(クラック)」や「歯根破折」であると確定診断された場合、その治療法は、ひびがどこまで深く、そしてどの方向に広がっているかによって、大きく変わってきます。これは、治療の選択肢が、歯の予後(将来性)に直結する、非常にシビアな判断が求められる状況です。
①ひびが浅い場合(エナメル質・象牙質まで):
ひびが、歯の神経に達していない、比較的浅いレベルに留まっている場合は、歯を保存できる可能性が高いです。ひびの部分を削り取り、歯科用の接着剤を含んだプラスチック(コンポジットレジン)で修復したり、歯がそれ以上割れるのを防ぐために、歯全体を覆う「被せ物(クラウン)」を作製したりします。
②ひびが神経に達している場合:
ひびが歯の神経にまで達してしまっている場合は、まず神経を取る治療(根管治療)が必要になります。その後、歯の補強を行い、被せ物で保護します。ただし、ひびから細菌が感染しているため、治療の成功率は100%ではありません。
③ひびが歯根にまで達している場合(歯根破折):
残念ながら、ひびが歯の根っこまで、特に垂直方向に割れてしまっている「歯根垂直破折」の場合、現代の歯科医療をもってしても、その歯を長期的に保存することは極めて困難です。ひびの隙間から細菌が侵入し、周囲の骨を溶かし続けてしまうため、多くの場合、周囲の組織へのさらなる被害を防ぐために「抜歯」という選択をせざるを得ません。
8.「そのうち治るだろう」という放置が招く、最悪のシナリオ

「噛むと痛い」という症状は、厄介なことに、常に一定の強さで続くとは限りません。痛い日もあれば、全く気にならない日もある。噛む角度によっては痛くない。そんな風に、痛みが波のように寄せては返すため、「しばらく様子を見ていれば、そのうち治るだろう」「疲れているだけかもしれない」と、つい問題を先延ばしにしてしまいがちです。そのお気持ちは、非常によく分かります。しかし、どうか知ってください。お口の中で起きている問題、特に「噛むと痛い」という症状の根本原因は、自然に治癒することは決してありません。あなたが「様子を見ている」間にも、水面下では病状が静かに、しかし着実に進行し、より深刻で、より取り返しのつかない事態へと向かっているのです。それは、小さな火種を放置した結果、気づいた時には家全体が燃え盛る大火事になっていた、という悲劇にも似ています。ここでは、その「放置」という選択が、最終的にどのような“最悪のシナリオ”を招く可能性があるのか、目を背けたくなるような現実を、あえて具体的にお話しします。この未来予想図を知ることが、あなたを後悔から守るための、最後のブレーキとなることを願っています。
歯のひびが広がり、突然歯が割れてしまう
痛みの原因が、目に見えないほどの微細な「ひび(マイクロクラック)」だった場合、放置は最も危険な選択です。最初は髪の毛ほどの細さだったひびも、あなたが食事をするたびに、あるいは夜中に歯ぎしりをするたびに、何千回、何万回と繰り返される「噛む力」によって、くさびを打ち込まれるように、少しずつ、しかし確実に、その亀裂を深めていきます。そして、ある日突然、その時は訪れます。いつも通りに食事をしていただけなのに。「ガリッ」という、今まで聞いたことのない嫌な音とともに、歯が大きく欠けてしまう。あるいは、真っ二つに割れてしまう。それは、もはや「ひび」ではなく、完全な「破断」です。こうなってしまうと、治療の選択肢は著しく限られてしまいます。小さなひびの段階であれば、接着剤で修復したり、被せ物で保護したりすることで、歯を救えたかもしれません。しかし、大きく割れてしまった歯は、もはや元の形に戻すことはできず、多くの場合、抜歯以外の選択肢がなくなってしまいます。「あの時、噛むと少し痛いと感じた時に、すぐに行っていれば…」―その瞬間に訪れる後悔は、計り知れないほど大きなものになるでしょう。放置という時間は、静かなる時限爆弾のタイマーを進めているのと同じことなのです。
根の先の感染が拡大し、周りの骨を溶かしてしまう
歯のひびや、深い歯周ポケットを放置することは、お口の中に、細菌が体内に侵入するための「開けっ放しのドア」を作っているようなものです。ひびの隙間や、歯周ポケットの奥深くから侵入した細菌は、歯の根の先端部分に到達し、そこで巣を作って繁殖を始めます。すると、私たちの体は、その細菌と戦うために免疫細胞を送り込み、激しい防衛反応、すなわち「炎症」を起こします。この戦いの結果、歯根の周りにある、歯を支えるための大切な顎の骨(歯槽骨)が、少しずつ溶かされて吸収されていってしまうのです。そして、戦いの残骸である「膿」が溜まり、膿の袋(根尖病巣や歯周膿瘍)を形成します。最初は、噛んだ時に少し違和感がある程度だったものが、やがて歯ぐきが大きく腫れあがり、顔の形が変わるほどになることもあります。さらに感染が拡大すれば、隣の健康な歯の骨まで溶かしたり、副鼻腔にまで炎症が及んだり(歯性上顎洞炎)、あるいは、細菌が血流に乗って全身に回り、重篤な全身疾患を引き起こしたりするリスクさえあります。たった一本の歯の問題が、お口全体、そしてあなたの全身の健康をも脅かす、大きな脅威へと発展していく。これが、感染を放置することの、本当の恐ろしさなのです。
最終的に、残せたはずの歯を「抜歯」せざるを得なくなる
これまでお話ししてきたシナリオの、最終的な結末。それは、多くの場合、「抜歯」という、最も避けたい結果です。歯が大きく割れてしまった場合。歯を支える骨が、歯周病や根の先の感染によって、ほとんど溶けてなくなってしまった場合。あるいは、歯根にまで達したひび割れによって、保存が不可能だと判断された場合。これらの状況では、もはやその歯を残しておくこと自体が、周囲の組織にとって有害となり、さらなる問題を引き起こすリスクとなります。そのため、私たちは、非常に辛い決断ではありますが、その歯を抜くことをご提案せざるを得なくなります。大切なのは、これらの歯の多くは、「もっと早い段階で適切な対処をしていれば、救えた可能性があった」ということです。「噛むと痛い」という、歯が発していた最初のSOSサインに気づき、すぐに行動を起こしていれば。小さなひびのうちに、保護する治療を受けていれば。歯周病の初期段階で、徹底的なクリーニングを行っていれば。その「もしも」の選択肢は、放置という時間とともに、一つ、また一つと失われていきます。そして、最後に残された道が「抜歯」なのです。天然の歯は、一度失ってしまえば、二度と元には戻りません。その喪失感と後悔は、計り知れないものがあります。どうか、その未来を、あなたの選択で回避してください。
9.まとめ:原因が分からない痛みこそ、専門家の診断が不可欠

「噛むと痛いのに、虫歯じゃない」―この記事を通して、そのミステリアスな症状の裏に隠された、様々な“容疑者”たちの顔ぶれが見えてきたのではないでしょうか。それは、歯のクッション役である「歯根膜」の悲鳴であり、目に見えない「歯のひび」からの警告であり、あるいは、あなた自身も気づいていない「無意識の癖」が残した痕跡かもしれません。そして、最も重要なことは、これらの原因のどれもが、放置すればより深刻な事態を招き、自然に治ることは決してない、という厳然たる事実です。
今、あなたの手の中には、ご自身の痛みの原因を推測するための、いくつかのヒントがあるかもしれません。しかし、それはあくまで可能性の一つに過ぎません。本当の真実を突き止め、そして、それに終止符を打つためには、最終的に、ある一つの行動が不可欠となります。それは、専門家である私たち歯科医師に、その謎を解き明かすための「調査」を依頼することです。最後に、なぜ原因不明の痛みこそ、専門家の診断が必要なのか。その理由を改めてお伝えし、あなたの不安な日々に、確かな光を灯したいと思います。
あなたの痛みは、あなただけのせいではない
「噛むと痛い」という症状が続くと、「自分の歯の管理が悪かったからだ」と、ご自身を責めてしまう方がいらっしゃるかもしれません。しかし、どうかそう思い詰めないでください。この記事で見てきたように、痛みの原因は、非常に多岐にわたります。過去の治療で入れた詰め物の、ほんの数ミクロンの高さのズレ。加齢とともに、どうしても避けられない歯の質の変化。あるいは、現代社会のストレスが生み出す、無意識の歯ぎしりや食いしばり。これらは、あなた一人の努力だけでは、どうにもコントロールできない要因が複雑に絡み合って生じていることがほとんどです。
あなたの痛みは、決してあなただけのせいではないのです。大切なのは、自分を責めることではなく、「なぜ、自分の歯に、今、このようなことが起きているのか」という、その根本原因を客観的に知ることです。そして、その原因を正確に突き止められるのは、専門的な知識と、精密な検査機器を駆使できる、私たち歯科医師だけなのです。あなたは、一人で悩む必要はありません。その重荷を、どうぞ私たちに預けてください。
正しい診断が、正しい治療への唯一の道
もし、あなたが風邪をひいて高熱が出た時、自己判断で「胃腸薬」を飲む、ということはしませんよね。まず医師の診察を受け、「あなたの熱の原因は、ウイルス性の風邪ですよ」という正しい「診断」が下されて初めて、「解熱剤」という正しい「治療薬」が処方されます。歯科治療も、これと全く同じです。正しい診断なくして、正しい治療はあり得ません。
「噛むと痛い」という一つの症状に対して、原因が歯周病なのか、噛み合わせなのか、それとも歯のひびなのかによって、治療法は180度異なります。もし、歯のひびが原因であるのに、歯周病の治療ばかりを続けていても、痛みは決してなくなりません。むしろ、時間を無駄にし、その間にひびはさらに広がってしまうでしょう。私たち歯科医師の最も重要な仕事は、この「診断」を正確に行うことです。様々な可能性を一つひとつ検証し、あらゆる検査結果を統合して、たった一つの真実にたどり着く。そのプロセスを経て初めて、私たちは、あなたの痛みを取り除くための、最も効果的で、最も的確な治療法をご提案することができるのです。原因不明の痛みという迷宮から抜け出すための、唯一の地図。それが、「正しい診断」なのです。
不安な日々を終わらせ、食事を楽しむ喜びを取り戻しましょう
「この歯で噛んだら、また痛むんじゃないか…」そんな不安を抱えながらの食事は、本当に辛いものです。本来、人生における大きな喜びであるはずの「食べること」が、苦痛や不安の時間に変わってしまう。それは、あなたの生活の質(QO-L)を、著しく低下させてしまいます。もう、そんな日々を続けるのは、終わりにしませんか。あなたのその痛みには、必ず原因があります。そして、原因が分かれば、必ず解決への道筋が見えてきます。
今、あなたに必要なのは、ほんの少しの勇気です。歯科医院の扉を叩き、「噛むと痛いんです。でも、原因が分からなくて…」と、私たちに打ち明けてみてください。そこから、すべてが始まります。原因が分かり、適切な治療を受け、痛みのない快適な毎日を取り戻した時、あなたは、これまで我慢してきた、好きだった硬いおせんべいを、何の気兼ねもなく食べられるようになっているかもしれません。友人との食事会を、心の底から楽しめるようになっているかもしれません。その「当たり前の幸せ」を取り戻すための第一歩を、どうか、今日、踏み出してください。私たちは、あなたのその勇気を、全力でサポートすることをお約束します。
10.「噛むと痛い」に関するよくある質問Q&A

ここまでお読みいただき、本当にありがとうございます。「噛むと痛いのに虫歯じゃない」という、もどかしい症状の裏に隠された様々な原因と、その解決への道筋について、ご理解が深まったことと思います。しかし、実際に歯科医院へ行こうと決心した時、あなたの心には、さらに具体的で、個人的な疑問が湧き上がってくるかもしれません。「なぜ日によって痛みが違うの?」「治療すれば完全に元通りになる?」―そうした疑問は、治療への期待と不安が入り混じる中で、当然生まれてくるものです。
そこでこの最後の章では、私たちが日々の診療で「噛むと痛い」というお悩みを抱える患者様から、特によくお受けする質問を3つ選び、専門家の立場から、誠実にお答えしていきたいと思います。あなたの心に残る最後の霧を晴らし、晴れやかな気持ちで第一歩を踏み出すためのお手伝いができれば幸いです。
Q. 痛い時と痛くない時があります。なぜですか?
A. 痛みの原因や、その日の体調、噛み方など、複数の要因が関係しているためです。
これは、多くの患者様が不思議に思われる点で、「気のせいなのだろうか?」と悩む原因にもなりますよね。痛みに波があるのには、いくつかの理由が考えられます。
①痛みの原因による特性:
特に「歯のひび(クラック)」が原因の場合、この傾向は顕著です。ひびは非常に微細なため、噛む時の力の“角度”や“方向”によって、ひびが開いて神経を刺激することもあれば、全く刺激しないこともあります。特定の硬さのものや、特定の動きをした時にだけ、「ピリッ」と痛むのはこのためです。また、「歯ぎしり・食いしばり」が原因の場合も、ストレスの度合いなどによって、夜間の食いしばりの強さが日によって変わるため、翌朝の顎のだるさや歯の痛みに波が出ることがあります。
②体調や免疫力の変化:
私たちの体は、疲労が溜まっていたり、寝不足だったり、風邪をひいていたりすると、免疫力が低下し、炎症反応が強く出やすくなります。普段は何とか抑えられていた歯ぐきや歯根膜の炎症が、体調が悪い時にだけ、痛みとして顔を出すのです。「疲れると、決まってこの歯がうずく」というのは、まさにこの状態です。
③無意識の噛み方の変化:
痛みを感じると、私たちは無意識のうちに、その歯をかばって反対側で噛むようになります。そうすると、痛かった歯は一時的に休まるため、症状が和らぎます。そして、痛みがなくなったからと、またその歯で噛み始めると、再び痛みがぶり返す…というサイクルを繰り返している場合もあります。
このように、痛みに波があるからといって、決して「治った」わけではありません。むしろ、それは根本的な原因が解決されていない証拠なのです。
Q. 治療すれば、痛みは完全になくなりますか?
A. 痛みの原因と、治療への反応によります。多くの場合、症状は大幅に改善しますが、100%の保証は難しい場合もあります。
これは、非常に正直にお答えしなければならない、大切な質問です。私たちの治療の最大の目標は、もちろん「痛みをなくし、快適に噛める状態を取り戻す」ことです。そして、多くの場合、正しい診断と適切な治療によって、痛みは劇的に改善、あるいは完全に消失します。
歯周病が原因であれば、徹底的なクリーニングで炎症が治まれば痛みはなくなります。噛み合わせの不調和が原因であれば、調整することで、その日から痛みが嘘のようになくなることもあります。
しかし、残念ながら、100%痛みがなくなるとは断言できないケースも存在します。それは、主に「歯のひび」が原因の場合です。ひびが歯の神経に近い深い部分まで達していると、修復治療を行っても、強い力がかかった時に、わずかな違和感や軽い痛みが残ってしまう可能性は否定できません。また、「歯ぎしり・食いしばり」は、ストレスなどにも起因する生理現象であり、マウスピースで歯を守ることはできても、歯ぎしりそのものを完全に止めることは困難です。そのため、極度に強い食いしばりがあった日には、多少の違和感が出ることがあるかもしれません。
私たちは、治療前に、あなたの痛みの原因から予測される治療後の見通し(予後)について、正直にご説明します。そして、痛みを完全に取り除くことを目指し、最善を尽くすことをお約束します。
Q. 歯ぎしりの自覚がないのですが、それでも原因になりますか?
A. はい、大いに関係します。歯ぎしり・食いしばりの9割以上は、無自覚・無意識に行われています。
「私は歯ぎしりなんてしていません」―カウンセリングで、本当に多くの方がそうおっしゃいます。音の出る「グラインディング(歯をギリギリこすり合わせる)」タイプの歯ぎしりは、ご家族に指摘されて気づくこともありますが、音の出ない「クレンチング(歯をグーッと強く噛みしめる)」タイプの食いしばりは、本人も、そして周りの人も、気づくことがほぼ不可能です。
研究データによれば、何らかの形の歯ぎしり・食いしばり(ブラキシズム)は、成人のほぼ100%に見られるという報告さえあります。つまり、「自分はしていない」と思っている人でも、睡眠中や日中の集中している時に、無意識のうちに歯を接触させたり、噛みしめたりしているのです。
大項目5のセルフチェックリストで、「朝、顎がだるい」「歯がすり減っている」「頬や舌に歯の痕がある」といったサインが一つでも当てはまれば、たとえ自覚がなくても、あなたの歯には過剰な力がかかっている可能性が極めて高いと言えます。むしろ、「自覚がない」ことの方が、より問題が根深い場合もあります。なぜなら、無意識下での力は、自分でコントロールすることができず、際限なく歯にダメージを与え続けるからです。「噛むと痛い」という症状は、そんなあなたの無意識の癖を、体が教えてくれている、貴重なサインなのかもしれません。自覚の有無にかかわらず、一度、専門家による客観的なチェックを受けてみることを、強くお勧めします。
参考文献
1)Manfredini D, Winocur E, Guarda-Nardini L, Paesani D, Lobbezoo F. Epidemiology of bruxism in adults: a systematic review of the literature. J Orofac Pain. 2013;27(2):99-110.
2)Zieliński G, Weber J, Wieczorek A, et al. Global Prevalence of Sleep Bruxism and Awake Bruxism in Pediatric and Adult Populations: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Med. 2024;13(3):723.
出典コメント(脚注用の注記例)
本稿では “成人のほぼ 100 % にブラキシズムが見られるとの報告もある” という臨床的な比喩表現を用いていますが、現行の系統的レビューでは 睡眠ブラキシズム 8 – 13 %、覚醒時ブラキシズム 20 – 30 % 前後 が妥当な疫学値とされています(参考文献 1, 2)。数値の詳細については各論文をご参照ください。
汐留駅から徒歩5分の歯医者・歯科
患者様の声に耳を傾ける専門の歯科クリニック
監修:《 オリオン歯科 NBFコモディオ汐留クリニック 》
住所:東京都港区東新橋2丁目14−1 コモディオ汐留 1F
電話番号 ☎:03-3432-4618
*監修者
オリオン歯科 NBFコモディオ汐留クリニック東京
ドクター 櫻田 雅彦
*出身大学
神奈川歯科大学
*略歴
・1993年 神奈川歯科大学 歯学部卒
日本大学歯学部大学院博士課程修了 歯学博士
・1997年 オリオン歯科医院開院
・2004年 TFTビル オリオンデンタルオフィス開院
・2005年 オリオン歯科 イオン鎌ヶ谷クリニック開院
・2012年 オリオン歯科 飯田橋ファーストビルクリニック開院
・2012年 オリオン歯科 NBFコモディオ汐留クリニック開院
・2015年 オリオン歯科 アトラスブランズタワー三河島クリニック 開院
*略歴
・インディアナ大学 JIP-IU 客員教授
・コロンビア大学歯学部インプラント科 客員教授
・コロンビア大学附属病院インプラントセンター 顧問
・ICOI(国際口腔インプラント学会)認定医
・アジア太平洋地区副会長
・AIAI(国際口腔インプラント学会)指導医
・UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)インプラントアソシエーションジャパン 理事
・AO(アメリカインプラント学会)インターナショナルメンバー
・AAP(アメリカ歯周病学会)インターナショナルメンバー
・BIOMET 3i インプラントメンター(講師) エクセレントDr.賞受賞
・BioHorizons インプラントメンター(講師)
・日本歯科医師会
・日本口腔インプラント学会
・日本歯周病学会
・日本臨床歯周病学会 認定医
・ICD 国際歯科学士会日本部会 フェロー
・JAID(Japanese Academy for International Dentistry) 常任理事