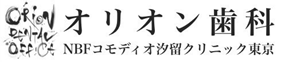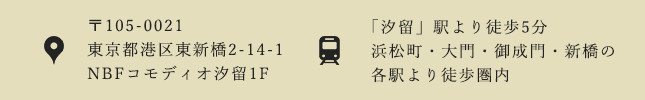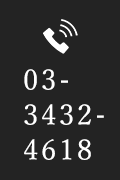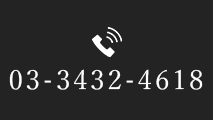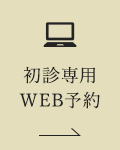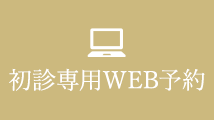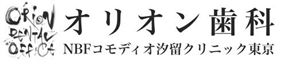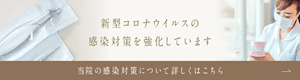生理前や更年期に「歯ぐきが腫れる」——女性特有の悩み

女性ホルモンの変動が歯ぐきに影響する理由
女性の体は、一生のうちで何度もホルモンバランスが変化します。特に生理前や更年期には、エストロゲンやプロゲステロンといった女性ホルモンの分泌量が大きく揺らぎます。これらのホルモンは血管の透過性や炎症反応に関与しており、バランスが崩れると歯ぐきの血流が増し、腫れやすく・出血しやすくなるのです。
また、ホルモン変動によって免疫力が一時的に低下し、口腔内の細菌に対する防御力が弱まることもあります。これにより、軽度の歯垢や歯石でも歯周病の炎症が悪化しやすい状態になります。とくに「ホルモン性歯肉炎」と呼ばれる症状は、女性の生理周期や更年期の時期に見られる典型的な変化です。体の仕組みが関係しているため、「自分のケア不足」と責める必要はありません。大切なのは、体調変化と口腔内の関係を正しく理解し、早めに歯科でチェックを受けることです。
「いつもと違う」口の中の変化に気づいたら
生理前や更年期になると、「歯ぐきがムズムズする」「歯ブラシのときに血が出る」「口臭が強くなった気がする」といった変化を感じる方が増えます。これらは、女性ホルモンの変化によって歯周組織が敏感になっているサインです。特に、腫れや赤みが出ている場合は、歯ぐきの内部で炎症が進行している可能性があります。
この段階で自己判断に頼り、「しばらくすれば落ち着く」と放置するのは避けましょう。炎症が慢性化すると、歯を支える骨(歯槽骨)にまで影響が及び、歯周病のリスクが高まります。女性ホルモンの変化による腫れは一時的なものでも、その間に歯周病菌が増えることで症状が悪化するケースがあるため、注意が必要です。「なんとなく違和感がある」と感じた時点で、専門医に相談することで早期発見・早期治療につながります。
腫れや出血を放置してはいけないサインとは
歯ぐきの腫れや出血は、体の防御反応の一つです。しかし、これを繰り返すうちに慢性的な炎症が進行し、歯周病や歯槽骨の吸収といった不可逆的な変化へつながることがあります。特に、女性ホルモンの影響を受けやすい時期は、歯周組織がデリケートになっており、通常より炎症が拡大しやすい傾向があります。
「ブラッシングのたびに血が出る」「口の中がねばつく」「歯が浮いたように感じる」といった症状が見られる場合は、歯ぐきの内部で炎症が深部化しているサインです。これらを見過ごすと、治療が必要な歯周病へと発展する恐れがあります。歯ぐきの腫れは一見小さな変化に見えても、体全体のホルモンバランスや免疫力と密接に関わる重要なサインです。放置せず、早めに歯科医院で状態を確認し、正しいケアを受けることが、長く健康な歯を保つ第一歩になります。
女性ホルモンと歯ぐきの密接な関係

エストロゲン・プロゲステロンが歯周組織に与える影響
女性ホルモンであるエストロゲンとプロゲステロンは、歯ぐき(歯肉)や歯を支える骨などの「歯周組織」にも大きく関わっています。エストロゲンは歯肉の血管やコラーゲンの代謝を整える働きがあり、減少すると歯ぐきの弾力や修復力が低下しやすくなるといわれています。一方、プロゲステロンは血管を拡張させ、炎症反応を強める性質があります。そのため、このホルモンが増加する時期には歯ぐきの腫れや出血が起こりやすくなるのです。
また、女性ホルモンの変動は口腔内細菌のバランスにも影響を及ぼします。特に歯周病菌の一部はホルモンを栄養源として利用するため、ホルモン値が高まる時期には菌の活動性が上がり、歯周病リスクが一時的に上昇することがあります。これは、日頃の歯磨き習慣が十分でも腫れやすくなる理由の一つです。女性特有の体の変化を理解し、その時期に応じたケアを行うことが大切です。
思春期・妊娠・更年期——年代別で異なる口腔内変化
女性のライフステージにおいて、ホルモンの変化はそれぞれ異なる形で歯ぐきに影響します。思春期ではホルモン分泌の急上昇により、一時的に歯ぐきが赤く腫れたり、歯磨き時に出血しやすくなることがあります。妊娠中はプロゲステロンが大幅に増えることで免疫反応が変化し、「妊娠性歯肉炎」と呼ばれる歯ぐきの腫れや出血が起こりやすくなります。
更年期に入ると、エストロゲンの減少が進み、歯ぐきの血流や骨代謝が低下します。結果として、歯槽骨の吸収(骨の減り)や歯ぐきの退縮が進みやすくなり、歯が長く見えるようになることもあります。さらに口腔乾燥(ドライマウス)も加わり、細菌が繁殖しやすい環境が生まれます。こうした変化は自然な生理現象であり、早めに気づいて適切な対策を取ることで、健康な口腔環境を維持することが可能です。
女性に多い「ホルモン性歯肉炎」とは
「ホルモン性歯肉炎」は、女性ホルモンの変動が関与して起こる歯ぐきの炎症です。歯垢(プラーク)が原因である点は通常の歯肉炎と同じですが、ホルモンの作用によって炎症反応が過敏に出やすくなるのが特徴です。特に生理前、妊娠中、更年期など、ホルモンバランスが大きく変化する時期に発症・悪化しやすい傾向があります。
症状としては、歯ぐきの赤みや腫れ、ブラッシング時の出血、口臭などが挙げられます。多くの場合、歯垢の除去と正しいブラッシング指導で改善が見込めますが、ホルモンの影響が続く限り再発を繰り返すこともあるため、定期的な歯科でのクリーニングが重要です。ホルモン性歯肉炎は、身体の自然な変化に伴って起こるもの。無理に抑え込むのではなく、体調のサイクルに合わせた予防ケアでコントロールすることが健康維持の鍵になります。
歯ぐきの腫れを引き起こす主な原因を正しく理解する

歯周病菌とホルモンの相互作用
女性ホルモンと歯周病菌は、実は密接に関係しています。特に生理前や妊娠中、更年期など、ホルモンバランスが変化する時期には、エストロゲンやプロゲステロンの分泌量が増減します。これらのホルモンは、歯ぐきの血管を拡張させたり、炎症反応を強めたりするため、通常よりも歯周病菌に対する抵抗力が弱まるのです。
また、ある種の歯周病菌は女性ホルモンを栄養源として利用し、繁殖を活発化させることが知られています。その結果、同じ量の歯垢(プラーク)でも、ホルモン変動の時期には歯ぐきの腫れや出血が強く出やすくなる傾向があります。こうした変化は一時的なものですが、炎症を繰り返すうちに慢性化することもあるため、歯科医院での早期チェックとケアが大切です。
ストレス・睡眠不足・免疫低下の関係
女性ホルモンの変動に加えて、ストレスや睡眠不足も歯ぐきの腫れを悪化させる要因になります。ストレスが続くと、コルチゾールというホルモンが分泌され、免疫力が低下します。その結果、歯周病菌への抵抗力が下がり、炎症を抑える力も弱まるのです。
さらに、睡眠不足は自律神経のバランスを乱し、ホルモン分泌にも影響を与えます。生理周期や更年期のホルモン変動と重なると、体全体の免疫調整がうまくいかず、歯ぐきが腫れやすい・治りにくい状態に陥ることがあります。ストレスや疲労を軽減し、質の良い睡眠をとることも、歯ぐきの健康を保つうえで重要なセルフケアの一つです。
市販薬やピルによるホルモン変化の影響
避妊用ピル(経口避妊薬)や一部の市販薬も、歯ぐきの腫れに関係する場合があります。ピルにはエストロゲンやプロゲステロンが含まれており、体内のホルモンバランスに影響を与えます。特に服用開始から数か月は、ホルモン変化に体が慣れるまで、歯ぐきの腫れ・出血・違和感といった症状が一時的に現れることがあります。
また、抗うつ薬や降圧薬などの一部の薬には、唾液分泌を減らす副作用があります。唾液が減ると口腔内の自浄作用が弱まり、歯垢がたまりやすくなり、結果的に歯ぐきが腫れやすくなることもあります。薬の影響による腫れは一概に異常ではありませんが、症状が続く場合は自己判断せず、歯科医師や主治医に相談することが大切です。適切なケアと情報共有により、安全に治療を進めることができます。
女性ホルモンの変化による歯ぐきのトラブルは治せる?

炎症の程度に応じた歯周病治療の流れ
女性ホルモンの変化が関係する歯ぐきの腫れや出血は、歯周病の初期症状であることが多く、早期の治療で改善が期待できます。治療はまず、歯垢や歯石を除去する「スケーリング」から始まります。歯周ポケットが深い場合には、より深部の汚れを除去する「ルートプレーニング」や「歯周外科治療」が検討されます。
炎症が強い場合や腫れが繰り返す場合は、歯周病菌を抑制するための薬剤投与や、咬み合わせの調整が行われることもあります。女性ホルモンの変動により一時的に炎症が悪化することもありますが、原因となる細菌をしっかり除去すれば症状の安定が可能です。また、治療後の定期的なメンテナンスと生活習慣の見直しが、再発防止の大きな鍵となります。
ホルモンバランスの整え方と生活習慣の見直し
歯ぐきの腫れを繰り返す背景には、女性ホルモンの乱れが関係している場合があります。特に、ストレス・睡眠不足・不規則な食生活はホルモン分泌のバランスを崩し、免疫力の低下を招きやすくなります。ホルモンバランスを整えるには、十分な休息とバランスの取れた食事が基本です。鉄分・ビタミンC・カルシウムなど、歯周組織の健康を支える栄養素を意識的に摂ると良いでしょう。
また、喫煙は血流を悪化させ、歯ぐきの治癒力を低下させるため、歯周病治療中の禁煙は重要です。ホルモンの影響そのものを完全に防ぐことはできませんが、生活習慣を整えることで体の抵抗力を高め、歯ぐきの炎症を抑えやすくすることが可能です。体の内側から整える意識が、口腔環境の改善にもつながります。
定期的なメンテナンスで再発を防ぐ方法
女性ホルモンの変化による歯ぐきのトラブルは、一度改善しても再発することがあります。そのため、治療後は定期的なメンテナンスが欠かせません。歯科医院でのメンテナンスでは、日常のブラッシングでは落としきれない歯石やバイオフィルムを除去し、炎症の再発を予防します。
また、ホルモンバランスの変化が大きい時期(生理前・妊娠期・更年期など)は、普段より丁寧なケアが必要です。症状が出やすいタイミングを理解しておくと、早めの受診と適切なケアで重症化を防ぐことができます。定期的なチェックにより、口腔内の小さな異変を早期に発見できるため、「治療」ではなく「予防」にシフトした健康管理が可能になります。
歯科医院での検査とカウンセリングでできること

専門医による歯周組織検査とリスク評価
歯ぐきの腫れや出血が続く場合、歯科医院ではまず歯周組織の検査を行い、歯周病の有無や進行度を確認します。検査では、歯と歯ぐきの間にある「歯周ポケット」の深さを専用の器具で測定し、炎症の程度や出血の有無を調べます。必要に応じてレントゲン撮影や口腔内写真を用い、歯槽骨の吸収状態を把握します。
また、女性ホルモンの変化による歯ぐきの炎症は、単なる口腔衛生の問題ではなく、体内ホルモンや免疫バランスとの関係性を考慮する必要があります。歯科医院ではこれらの点も踏まえ、「今の歯周環境がホルモン変動によってどのような影響を受けているのか」を総合的に評価します。こうした検査結果をもとに、患者様一人ひとりに合ったケアや治療の方向性が立てられます。
生活習慣や服薬状況をふまえた治療提案
歯ぐきの腫れには、ホルモンの変化だけでなく、ストレス・食生活・喫煙・薬の服用など、日常生活に関連する要因も深く関係しています。そのため歯科医院では、問診時に生活習慣や服薬状況を丁寧にヒアリングし、体全体の状態をふまえた上で治療計画を立てます。
例えば、避妊用ピルや更年期治療のホルモン補充療法を受けている場合は、ホルモン変動が歯ぐきの腫れにどのように影響しているかを考慮します。さらに、栄養バランスの改善指導や正しいブラッシング方法の提案、メンタル面のストレス軽減も含め、長期的に歯周病をコントロールするための包括的なアプローチが行われます。
このように、歯科治療は「口の中だけを見る」のではなく、生活背景を理解したうえで最適な治療を行うことが重要です。
女性の体調変化に寄り添う歯科医師のサポート体制
女性はライフステージごとにホルモンバランスが大きく変化します。思春期・妊娠・出産・更年期といったそれぞれの時期に、歯ぐきの腫れや炎症が起こりやすいタイミングがあります。歯科医院では、こうした女性特有の体調の変化を理解した上で、無理のない治療スケジュールやケアプランを提案します。
例えば、妊娠中は胎児への影響を考慮して処置内容を慎重に判断し、更年期には口腔乾燥への対策を組み合わせるなど、体調やライフスタイルに寄り添ったサポートが行われます。また、生理周期や更年期症状に伴う体調の波に応じて、診療時期の調整やセルフケア方法の見直しも行われます。
女性が安心して通える歯科医院とは、単に治療技術に優れているだけでなく、患者の体の変化と心の不安に寄り添う姿勢を持つ医院です。そのようなサポート体制が、長期的な口腔健康の維持につながります。
自宅でできる「ホルモン期別ケア」

生理前・排卵期の歯ぐきケアポイント
生理前や排卵期は、女性ホルモンの影響で歯ぐきの血流が増加し、腫れやすく・出血しやすい状態になります。これは、エストロゲンとプロゲステロンという2つのホルモンが増減することで、歯ぐきの毛細血管が拡張し、炎症反応が起こりやすくなるためです。この時期は、普段よりもやさしく丁寧なケアを意識しましょう。
まず、歯ブラシは柔らかめを選び、歯と歯ぐきの境目を軽い力で磨くことが大切です。強い力でこすると炎症を悪化させることがあります。また、デンタルフロスや歯間ブラシを併用して、プラーク(歯垢)を残さないことが最も効果的な予防策です。さらに、ビタミンCやタンパク質を意識して摂取し、歯ぐきの修復をサポートしましょう。
更年期・閉経後の口腔乾燥への対処法
更年期以降はエストロゲンの分泌量が減少し、唾液の分泌が低下しやすくなります。これにより、口腔乾燥(ドライマウス)や口臭、歯ぐきの炎症が起こりやすくなります。唾液は口内の自浄作用を担っており、その減少は歯周病やむし歯のリスクを高めます。
対策としては、こまめな水分補給を心がけるほか、キシリトール入りのガムやタブレットで唾液分泌を促すことが有効です。室内が乾燥しているときは加湿器を使い、舌や頬のストレッチで口周りの筋肉を動かすことも効果的です。また、カフェインやアルコールは口の乾きを助長するため、摂取を控えるのが望ましいでしょう。必要に応じて歯科医院で保湿ジェルやマウススプレーを相談することもおすすめです。
毎日のセルフケアで炎症を予防するコツ
歯ぐきの腫れを防ぐには、日々のセルフケアが最も重要です。歯周病菌は毎日のプラーク(歯垢)の中で繁殖するため、24時間以内に除去することが炎症予防の基本です。朝と夜の2回だけでなく、食後の軽いブラッシングも効果的です。
歯ブラシだけでは届かない部分には、デンタルフロスや歯間ブラシを取り入れましょう。また、抗菌作用のある洗口液を使うと、細菌の繁殖を抑えるサポートになります。加えて、栄養バランスの取れた食事や十分な睡眠も、ホルモンバランスと免疫機能を整えるうえで欠かせません。正しい生活リズムと適切な口腔ケアの継続が、女性特有の歯ぐきトラブルの予防につながります。
よくある質問Q&A:女性ホルモンと歯ぐきの腫れ

「生理前だけ腫れるのは病気?」という疑問
生理前にだけ歯ぐきが腫れる、出血しやすいといった症状は、多くの女性が経験するものです。これは、女性ホルモン(特にエストロゲンとプロゲステロン)の増減によって歯ぐきの毛細血管が拡張し、炎症が起こりやすくなるためです。生理周期に伴う一時的な反応であれば、病気とは限りません。
しかし、炎症が毎月強く出る場合や、腫れが長引く場合は注意が必要です。ホルモンの影響に加え、歯周病菌やプラーク(歯垢)の蓄積が関与していることが多いため、症状を放置すると慢性的な歯周病へ進行するおそれがあります。症状が生理周期と関係していると感じたら、歯科でのクリーニングや歯周検査を受け、早期に原因を確認しておくことが大切です。
「更年期の歯ぐきの出血は治る?」
更年期はエストロゲンの分泌が大きく減少し、歯ぐきのコラーゲンや血流が低下することで、出血しやすく・治りにくい状態になる傾向があります。ただし、適切なケアと治療によって改善が可能です。
歯科では、プラークや歯石を除去する基本的な歯周治療に加え、口腔乾燥(ドライマウス)や免疫低下への対策も行います。自宅では、柔らかい歯ブラシでの丁寧なブラッシングと、保湿ジェル・洗口液の使用が有効です。また、鉄分・ビタミンC・タンパク質など、歯ぐきの再生を助ける栄養素を意識して摂取しましょう。
ホルモンバランスの変化自体を止めることはできませんが、生活習慣の見直しと定期的な歯科メンテナンスで、出血や炎症の軽減が期待できます。
「婦人科と歯科、どちらに相談すべき?」
女性ホルモンの変化によって歯ぐきが腫れる場合、原因が「全身」と「口腔」の両方にまたがることがあります。そのため、どちらか一方ではなく、症状の出方によって相談先を使い分けるのが理想的です。
歯ぐきの腫れ・出血・口臭など口腔内の症状が中心であれば、まずは歯科を受診して歯周病やプラークの有無を確認します。一方で、周期的な腫れや更年期に伴う乾燥、体調の変化が強い場合は、婦人科でのホルモン検査や治療を並行して受けるとよいでしょう。
最近では、歯科と婦人科が連携して口腔と全身の健康をサポートする取り組みも進んでいます。どちらか迷う場合は、歯科でまず口腔内の検査を受け、必要に応じて医科との連携を提案してもらうのが安心です。
歯科医院を選ぶときのチェックポイント

女性のライフステージに理解のある歯科を選ぶ
女性の体は、思春期・妊娠期・更年期といったライフステージごとにホルモンバランスが変化します。これに伴い、歯ぐきの腫れや出血、口腔乾燥といった症状が起こりやすくなるため、女性ホルモンの影響を理解している歯科医院を選ぶことが重要です。
女性患者の歯科治療には、単なる歯の診療だけでなく、体調・服薬・生理周期・妊娠中の安全性など、きめ細やかな配慮が求められます。女性歯科医師やスタッフが在籍している医院では、こうした悩みを話しやすい環境が整っていることが多く、「相談しやすさ」や「理解の深さ」が治療継続の安心感につながります。さらに、ホルモン変動による歯ぐきのトラブルに対して、歯周病治療と生活指導を組み合わせた包括的なケアを行っているかも確認しておくとよいでしょう。
定期検診とカウンセリングの充実度
歯ぐきの腫れや出血は、定期的なチェックによって早期発見・早期治療が可能です。そのため、定期検診とカウンセリング体制が整っている歯科医院かどうかは、選ぶ際の大きなポイントです。
カウンセリングでは、現在の歯ぐきの状態だけでなく、生活習慣・ストレス・睡眠・食事内容・ホルモンの変化など、背景にある要因まで丁寧にヒアリングしてくれる医院が望ましいでしょう。特に女性の場合は、症状の強さや発症時期が生理周期や更年期と関連しているケースも多いため、患者一人ひとりのリズムに寄り添った診療方針を立ててくれる医院が安心です。
また、検診のたびに歯周ポケットの測定や口腔写真の記録を行い、経過を可視化して説明してくれる歯科医院は、患者が自身の口腔状態を理解しやすく、セルフケアのモチベーション維持にもつながります。
通いやすさ・相談しやすさも継続の鍵
どれほど高い専門性を持つ歯科医院でも、通いづらければ治療やメンテナンスの継続は難しくなります。アクセスの良さ、診療時間の柔軟さ、予約の取りやすさなどは、長期的な口腔ケアを続けるうえで欠かせない要素です。
また、女性特有の悩みを気兼ねなく相談できる雰囲気があるかも重要です。スタッフの対応が穏やかで、質問に丁寧に答えてくれる医院では、不安を抱えずに受診しやすくなります。さらに、妊娠中や更年期など体調の変化がある時期には、治療内容や来院スケジュールを柔軟に調整してくれる医院が安心です。
治療技術や設備だけでなく、「通いやすさ」と「相談のしやすさ」を重視することで、長く信頼して任せられる“かかりつけ歯科医院”を見つけることができます。
放置しないで!歯ぐきの腫れがもたらすリスク

慢性歯周病への進行と歯の喪失リスク
歯ぐきの腫れは、一時的な炎症と思われがちですが、放置すると慢性歯周病へ進行する危険信号です。歯ぐきの腫れは、歯と歯ぐきの間にプラーク(歯垢)がたまり、細菌が炎症を起こしているサインです。この状態をそのままにすると、炎症が歯の支えである歯槽骨にまで及び、歯がぐらつく・噛むと痛い・最終的に抜け落ちるといった深刻な結果を招くことがあります。
さらに、女性ホルモンの変動がある時期は、歯ぐきの血流や免疫反応が変わり、炎症が進行しやすい状態になります。とくに更年期や妊娠中は、歯周病の悪化リスクが高まるため、歯ぐきの腫れを軽視せず早期に歯科受診することが大切です。
全身疾患(糖尿病・動脈硬化)との関係
歯ぐきの腫れを引き起こす歯周病は、口腔内だけの問題ではなく、全身疾患との関連が多く報告されています。特に糖尿病とは双方向の関係があり、歯周病が悪化すると血糖コントロールが難しくなり、逆に糖尿病があると歯周病も進行しやすくなります。
また、歯周病菌が血管内に侵入すると、動脈硬化や心疾患、脳梗塞などのリスクを高めることが知られています。炎症によって産生されるサイトカイン(炎症性物質)が全身に影響を及ぼし、免疫バランスを乱すことも一因です。
特に女性の場合、更年期や閉経後にホルモンの保護作用が減少し、血管疾患のリスクが上がる傾向があります。歯ぐきの健康を守ることは、全身の健康管理にも直結する重要なケアといえます。
見た目・口臭・食事への影響
歯ぐきの腫れは、見た目や日常生活にも影響を及ぼします。まず、赤く腫れた歯ぐきや歯間の膨らみは、口元の印象を大きく変えてしまいます。また、歯周病菌が産生する揮発性硫黄化合物が原因で、強い口臭が発生することもあります。
さらに、歯ぐきが腫れていると食事のたびに痛みや出血を感じ、硬いものを避けがちになります。その結果、噛む力が低下し、栄養バランスの乱れや消化不良を引き起こすこともあります。
女性ホルモンの変動によって腫れが出やすい時期には、見た目・機能・健康のすべてに影響を与えるリスクが高まるため、違和感を感じた段階での早期治療が推奨されます。
まとめ:体と心の変化を前向きに受け止めるために

女性ホルモンと上手に付き合う口腔ケア習慣
女性ホルモンの変化は避けられない自然な体のサイクルですが、その影響を理解し、上手に付き合うことで歯ぐきの腫れや出血といったトラブルを防ぐことができます。特にエストロゲンやプロゲステロンが増減する生理前・妊娠期・更年期は、歯周病菌に対する防御力が低下しやすく、炎症が起こりやすい時期です。
日々のケアでは、歯ブラシに加えてフロスや歯間ブラシを使った細部の清掃を意識し、口腔内の菌の増殖を抑えることが重要です。また、ホルモンバランスを整えるためには、バランスの取れた食事・十分な睡眠・ストレス管理も欠かせません。定期的な歯科検診とプロフェッショナルケアを組み合わせることで、女性特有の体の変化にも負けない口腔環境を維持できます。
歯ぐきの腫れをきっかけに「自分をいたわる時間」を持つ
歯ぐきの腫れや出血は、体が発している小さなサインでもあります。「疲れがたまっている」「ホルモンバランスが乱れている」など、心身の変化に気づくきっかけとして受け止めることも大切です。
歯科医院での治療やメンテナンスは、口腔の健康を守るだけでなく、自分の体と向き合う機会にもなります。日々忙しい女性こそ、定期的な通院を「自分をケアする時間」として前向きに取り入れてみましょう。
また、口腔の不調は見た目や食事、会話など日常の質にも影響します。歯ぐきの違和感を放置せず早めに行動することが、健康と美しさの両立につながります。
まずは信頼できる歯科医院で相談してみよう
女性ホルモンの影響による歯ぐきの腫れや出血は、我慢や自然治癒を待つよりも、専門家による早期診断と適切なケアが安心です。歯科では、歯周病の進行度を調べる検査やクリーニング、生活習慣のアドバイスなどを通して、症状の根本原因にアプローチします。
さらに、女性特有の体調変化を理解し、ライフステージに合わせた治療や予防を行ってくれる歯科医院を選ぶことで、より快適なケアが受けられます。歯ぐきの腫れは「歳のせい」「仕方ない」と片付けず、体の変化に寄り添うパートナーとしての歯科医師に相談することが、健康な笑顔を守る第一歩です。
汐留駅から徒歩5分の歯医者・歯科
患者様の声に耳を傾ける専門の歯科クリニック
監修:《 オリオン歯科 NBFコモディオ汐留クリニック 》
住所:東京都港区東新橋2丁目14−1 コモディオ汐留 1F
電話番号 ☎:03-3432-4618
*監修者
オリオン歯科 NBFコモディオ汐留クリニック東京
ドクター 櫻田 雅彦
*出身大学
神奈川歯科大学
*略歴
・1993年 神奈川歯科大学 歯学部卒
日本大学歯学部大学院博士課程修了 歯学博士
・1997年 オリオン歯科医院開院
・2004年 TFTビル オリオンデンタルオフィス開院
・2005年 オリオン歯科 イオン鎌ヶ谷クリニック開院
・2012年 オリオン歯科 飯田橋ファーストビルクリニック開院
・2012年 オリオン歯科 NBFコモディオ汐留クリニック開院
・2015年 オリオン歯科 アトラスブランズタワー三河島クリニック 開院
*略歴
・インディアナ大学 JIP-IU 客員教授
・コロンビア大学歯学部インプラント科 客員教授
・コロンビア大学附属病院インプラントセンター 顧問
・ICOI(国際口腔インプラント学会)認定医
・アジア太平洋地区副会長
・AIAI(国際口腔インプラント学会)指導医
・UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)インプラントアソシエーションジャパン 理事
・AO(アメリカインプラント学会)インターナショナルメンバー
・AAP(アメリカ歯周病学会)インターナショナルメンバー
・BIOMET 3i インプラントメンター(講師) エクセレントDr.賞受賞
・BioHorizons インプラントメンター(講師)
・日本歯科医師会
・日本口腔インプラント学会
・日本歯周病学会
・日本臨床歯周病学会 認定医
・ICD 国際歯科学士会日本部会 フェロー
・JAID(Japanese Academy for International Dentistry) 常任理事