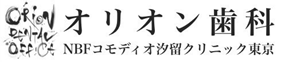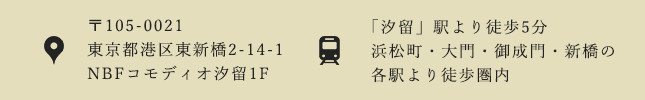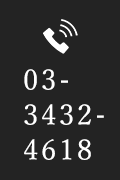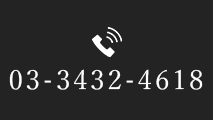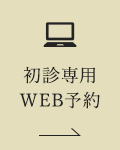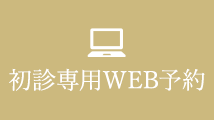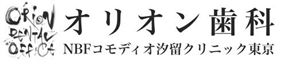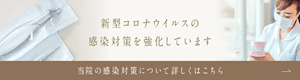「年齢のせい?」と悩む前に知っておきたいこと

・女性ホルモンと口腔内の変化:更年期の影響とは
40代以降の女性にとって、ホルモンバランスの変化は体のさまざまな部分に影響を及ぼします。なかでもエストロゲンの分泌量が減る更年期以降は、唾液の分泌低下によって口の中が乾燥しやすくなり、菌の繁殖環境が整ってしまいます。
唾液は単なる潤滑液ではなく、口腔内のpHを保ち、細菌を洗い流す働きがあるため、減少すれば口臭が強くなる要因にもつながります。また、歯ぐきの血流も低下しやすくなり、歯周病のリスクも高まります。ホルモン変化にともなう口腔環境の悪化を放置すれば、口臭が慢性化することもあるため、年齢に応じたケアが必要です。
・40代以降に増える“自覚しにくい”口臭の特徴
実は、強い口臭ほど自覚しにくいという特徴があります。特に40代以降は嗅覚の感度が少しずつ落ちてくるため、自分では気づかないうちに周囲に不快感を与えてしまっているケースもあります。
しかも、年齢により口腔内の変化が緩やかに進行するため、「昔より少し匂うかも?」というレベルでは判断が難しいことも。加齢により代謝が低下すると、舌苔(ぜったい)や歯周病菌も増加しやすくなり、それらが複雑に関係して「気づかれにくく、しかし確実に強くなる口臭」が発生するのです。日常的に意識する機会が少ない分、気づいたときには慢性化している可能性もあります。
・周囲の反応で気づくケースも…早めの対策が鍵
「最近、家族や同僚の距離感が気になる」「なんとなく避けられている気がする」と感じたことはありませんか? それがもし無意識の口臭によるものだとしたら、非常に残念なすれ違いです。
周囲の人はデリケートな話題を指摘しにくいため、言われなくても気にしておくことが大切です。また、「年齢のせいだから仕方ない」と受け流すのではなく、医療機関で原因を探ることが大きな一歩となります。
歯科では、口臭の原因となる歯周病、唾液の状態、舌苔などを多角的に評価し、改善策を提案できます。実際に診断を受けることで、原因を可視化し、正しい対処ができる安心感も得られます。
加齢とともに変化する唾液の分泌とその影響

・唾液量の低下で起こる「ドライマウス」
年齢を重ねるとともに、唾液腺の機能が低下し、口の中が乾きやすくなる「ドライマウス(口腔乾燥症)」を訴える女性が増えてきます。特に40代以降の女性では、更年期を迎えるタイミングでホルモンバランスが乱れやすくなり、唾液の分泌が急激に減少することも。
唾液には、食べ物を飲み込みやすくしたり、虫歯菌・歯周病菌を洗い流したり、pHバランスを中和して口内の環境を整えるといった重要な役割があります。これらの作用が低下すると、細菌の増殖が進み、口臭の原因となる揮発性硫黄化合物(VSC)の発生が促進されてしまいます。つまり、唾液の減少は、見逃してはならない口臭リスクの一つです。
・自浄作用の低下が菌の繁殖につながる
唾液の最大の機能の一つが「自浄作用」です。これは、口内に残った食べかすや細菌を自然に洗い流す力であり、この働きが正常に保たれていれば、多少の磨き残しがあっても大きな問題にはなりにくいものです。
しかし、加齢によって唾液量が減少するとこの自浄能力も低下し、食べかすが歯の隙間や舌の表面に残りやすくなり、細菌の温床となります。特に、歯周ポケットの中や舌苔の奥深くでは、酸素の少ない環境が整い、嫌気性菌(口臭の原因菌)が活発に活動します。これにより、ドライマウスと口臭は密接に関係し、進行性の問題として慢性化する恐れもあります。
・唾液検査でわかるお口の健康状態
「自分の唾液が十分に出ているか」「細菌のバランスは正常か」など、見た目や感覚では判断が難しい部分も、唾液検査を行うことで客観的に評価できます。
最近では、歯科医院で数分でできる簡易な唾液検査も普及しており、口腔内のpH値、緩衝能(酸を中和する力)、白血球の数値、細菌の活動性などを数値化できます。これにより、今の自分の状態に適したケアの方向性が明確になります。
唾液検査は、加齢にともなう口腔内のトラブルを早期に発見し、口臭リスクを事前にコントロールする上でも非常に有効な手段です。定期的な検査を通じて、年齢に応じたメンテナンスを取り入れていくことが、健康的な口元と快適な対人関係の維持につながります。
歯周病が潜んでいる可能性も

・口臭の主因「メチルメルカプタン」とは?
加齢とともに強くなる口臭の背景には、歯周病が密接に関与していることがあります。その代表的な原因物質が「メチルメルカプタン」という揮発性硫黄化合物です。これは、歯周ポケットの中で繁殖した嫌気性菌が、タンパク質を分解する過程で発生するガスで、卵が腐ったような独特の悪臭を放ちます。
歯周病が進行している口腔内では、このガスが慢性的に産生され、本人は気づきにくいまま口臭が悪化しているケースも少なくありません。また、このガスには粘膜を刺激する作用もあるため、炎症の悪化を招く悪循環にもなり得ます。歯磨きやマウスウォッシュで一時的にニオイを抑えても、根本的な原因である歯周病菌が存在する限り、口臭は再発し続けてしまうのです。
・自覚症状がない初期の歯周病に注意
歯周病は「沈黙の病気」とも呼ばれ、初期段階ではほとんど自覚症状がないことが大きな特徴です。40代以降の女性の場合、加齢に伴ってホルモンバランスが変化し、唾液の分泌が減少することや、免疫力の低下により歯周組織が炎症を起こしやすくなる傾向があります。
しかし、歯ぐきの腫れや出血といった症状は感じにくく、気づかないうちに進行してしまうのが実情です。「最近、口臭が気になる…」という違和感は、実は初期の歯周病が放つサインである可能性もあるのです。定期的な歯科健診を受けていないと、このような初期のサインを見逃してしまい、気づいたときには歯周組織の破壊が進行していることも少なくありません。
・歯科検診で発見できる“沈黙の疾患”
歯周病の早期発見・早期治療には、歯科での定期検診が最も有効です。歯科医師や歯科衛生士が、歯周ポケットの深さや歯ぐきの状態、出血の有無などを丁寧にチェックし、歯周病の兆候を見逃しません。また、必要に応じてレントゲン撮影により、歯を支える骨の状態も確認できます。
歯周病は進行すればするほど治療が難しくなり、歯を失うリスクも高まりますが、早期であればプラークコントロールやスケーリングといった基本的な処置だけで改善が期待できます。特に口臭が気になる方にとっては、目に見えない「臭いの根本原因」を知る上でも、歯科検診は重要な手段となります。40代以降の女性は、「年齢のせいだから仕方ない」と諦めず、歯科医に相談することが健康的な口元への第一歩です。
舌の汚れ=舌苔が原因になることも

・舌の上に蓄積する細菌のかたまり
口臭の原因として意外と見落とされがちなのが、舌の表面にたまる白っぽい汚れ「舌苔(ぜったい)」です。舌苔は、食べかすや口腔内の細菌、剥がれた粘膜のカスなどが舌の凹凸に付着してできるもので、特に舌の奥にたまりやすい性質があります。
実はこの舌苔が発するガスが、強い悪臭を生む「揮発性硫黄化合物(VSC)」の大きな発生源であることが、数々の研究で明らかになっています。年齢を重ねると、唾液の分泌が減少して自浄作用が低下し、舌の汚れも蓄積しやすくなるため、40代以降の女性にとっては要注意のポイントです。見た目にわかりづらい場所である分、気づかないうちにニオイのもとになっていることが少なくありません。
・舌ブラシでの正しい清掃方法
舌苔を効率的に除去するには、専用の「舌ブラシ」を使ったケアが推奨されます。通常の歯ブラシでは毛先が舌の繊細な粘膜を傷つけてしまう恐れがあるため、柔らかく平たい形状の舌専用ブラシを使用するのが理想的です。
清掃は朝起きた直後、まだ唾液が少なく、舌苔が乾燥しているタイミングが最も効果的とされています。ポイントは、「奥から手前に優しく撫でるように動かす」こと。ゴシゴシ強くこすってしまうと舌粘膜を傷め、かえって炎症やさらなる細菌の温床になるリスクもあります。また、1日に何度も磨くのは避け、基本は1日1回を目安に行うのが安全です。鏡で自分の舌をチェックする習慣を持つことも、口臭予防の第一歩です。
・舌苔と全身の体調の関係にも注目
実は、舌苔の状態は全身の健康状態とも深く関係しています。例えば、胃腸の不調や風邪、免疫力の低下があるとき、舌苔が厚くなったり、色が黄ばんだりすることがあります。
中医学では古くから舌の色や舌苔のつき方を健康のバロメーターと捉える考え方があり、西洋医学でも舌の状態は口腔内のみならず、体調管理の一環として注目されています。加齢とともに、体調の変化が舌苔として現れやすくなる傾向もあり、「最近口臭が気になる」と感じたときは、体調の見直しとともに舌のチェックも欠かせません。日々のセルフチェックだけでは不安な方は、歯科医院でのプロフェッショナルな清掃とアドバイスを受けることで、安心して対策を進められます。
ホルモンバランスの乱れが口臭に与える影響

・エストロゲンの減少と口腔内乾燥の関係
40代以降の女性が「口臭が強くなった」と感じる背景には、女性ホルモンの一種であるエストロゲンの減少が関係していることがあります。エストロゲンには、口腔内の粘膜を潤し、唾液の分泌を促進する働きがあります。
しかし、更年期を迎える時期になると、このホルモンの分泌量が大きく低下し、それに伴って唾液の量も減少しがちです。唾液は、口内を清潔に保ち、細菌の繁殖を抑える自浄作用を担っており、その働きが弱まると、口腔内は乾燥し、菌が増殖しやすい環境になります。結果として、歯周病や舌苔などの口臭の原因が増えやすくなり、自分でも不快に感じるニオイが慢性化してしまうのです。唾液の減少は、体調やストレスとも連動しており、加齢とともに口腔内の変化は無視できない問題となって現れます。
・口腔粘膜の変化と炎症リスク
ホルモンバランスの乱れは、唾液の分泌低下にとどまらず、口腔粘膜そのものの質にも影響を与えます。特にエストロゲンの低下により、口腔内の粘膜が薄くなり、乾燥しやすくなることで、わずかな刺激でも炎症が起きやすくなるのです。
粘膜のバリア機能が低下すると、細菌の侵入を防ぎにくくなり、歯ぐきや舌、頬の内側などに小さな炎症が繰り返し起こることもあります。炎症が起これば、そこに集まる白血球が細菌と戦う過程で悪臭物質が生成され、それが口臭として現れます。さらに、粘膜の不調により、味覚異常や口内炎を併発することもあり、食欲や生活の質にまで影響を及ぼすことがあります。これは、単なる口臭の問題にとどまらず、全身の健康や精神的なストレスにもつながりやすいため、放置せず歯科での評価と対応が重要です。
・ストレス・睡眠・生活習慣の見直しも大切
ホルモンバランスの乱れは、単に加齢だけでなく、ストレスや睡眠不足、食生活の乱れといった生活習慣とも密接に関わっています。たとえば、慢性的なストレスは交感神経を優位にし、唾液腺の働きを抑制するため、口の中が乾きやすくなり、細菌が繁殖しやすい状態に陥ります。
また、夜更かしや不規則な食事も、ホルモン分泌を乱す原因となります。加えて、偏った食生活では必要な栄養素が不足し、粘膜の修復力や免疫機能が低下することもあります。このような生活リズムの乱れが重なると、結果的に口臭の悪化や歯周病の進行を招きかねません。40代以降の女性にとって、口臭の予防・改善は、生活習慣の見直しから始まると言っても過言ではありません。歯科での治療と合わせて、身体と心の健康を整える意識が大切です。
加齢による口腔内の“ニオイの巣”とは

・歯と歯の隙間・補綴物の隙間に潜む汚れ
年齢を重ねると、歯ぐきが少しずつ下がり、歯と歯の間に“すき間”ができやすくなります。こうした隙間には、食べかすや歯垢(プラーク)が溜まりやすくなり、十分に除去されないまま時間が経つと、細菌が繁殖し、揮発性硫黄化合物などのニオイ成分を放つようになります。
さらに、詰め物や被せ物(補綴物)が古くなっている場合、そこにわずかな段差や隙間が生じることがあります。このミクロの空間に細菌が入り込み、通常の歯磨きでは取り除けない「ニオイの巣」となるのです。とくに40代以降は、長年使用してきた補綴物の劣化が起こり始めるタイミングでもあり、見た目では問題なさそうに見えても、内部で細菌が繁殖しているケースが珍しくありません。こうした汚れは口臭の根本原因となるため、定期的に歯科でチェックし、必要であれば補綴物の再製作などの対応を行うことが重要です。
・古くなった被せ物や入れ歯も要チェック
長年使い続けた被せ物や入れ歯は、経年劣化によって適合が悪くなったり、素材の劣化により表面に微細な傷やくぼみができることがあります。これらの凹凸部分に細菌や食物残渣が溜まり、そこから悪臭が発生することがあります。
とくに入れ歯の場合、毎日使用していても、専用のブラシや洗浄剤で適切に清掃していなければ、バイオフィルムと呼ばれる細菌の膜が形成されてしまいます。このバイオフィルムは口臭の強烈な発生源となり、しかも通常の水洗いでは落ちにくいため、注意が必要です。また、部分入れ歯の金属バネがかかっている歯は、構造的に清掃が難しく、虫歯や歯周病のリスクも高まります。被せ物や入れ歯の状態を長年見直していない方は、一度歯科で検査を受けることが、口臭改善への第一歩となります。
・定期的なメンテナンスの必要性
口腔内の“ニオイの巣”を早期に発見し、改善するためには、定期的な歯科メンテナンスが欠かせません。自分では取り切れない汚れや、補綴物の微細なトラブルを専門的にチェックすることで、ニオイの原因を根本から排除できます。
とくに、40代以降は歯ぐきの状態が変化しやすく、今まで問題なかった部位に急にトラブルが発生することもあります。また、噛み合わせの変化によって補綴物に無理な力が加わると、それが微細な破損や隙間につながることもあるため、定期的な確認は必要不可欠です。歯科医院でのプロフェッショナルケアでは、歯石除去・着色除去・バイオフィルムの除去などを行い、見た目だけでなく“ニオイの改善”にも直結する清潔な口腔環境を保つことができます。自宅ケアと歯科メンテナンスの両輪で、年齢とともに起こる変化に対応していくことが、口臭を予防し、清潔で快適な毎日を送るための秘訣です。
マスク時代だからこそ気づく自分の口臭

・マスク越しに感じるニオイの正体とは
マスクの着用が日常となった今、「自分の口臭」に初めて気づいたという方が増えています。マスクをすると、呼気がダイレクトに鼻に戻ってくるため、これまで感じなかった自分の口腔内のニオイを強く自覚する機会が増えました。
特に40代以降の女性では、ホルモンバランスの変化や唾液の減少、歯周病リスクの上昇といった複合的要因により、知らぬ間に口臭が強くなっているケースが少なくありません。マスク内でこもった空気に違和感を覚えるようになったら、それは体からの「注意サイン」かもしれません。多くの人は「食べ物のせい」「朝だから」と簡単に考えがちですが、実際には歯周病・舌苔・唾液の減少・補綴物のトラブルなど、複数の要因が重なっている場合が多く、軽視してはいけません。
・呼気に含まれるガスの成分を知る
口臭の主な原因物質は「揮発性硫黄化合物(VSC)」と呼ばれるガスで、代表的なものに「硫化水素」「メチルメルカプタン」「ジメチルサルファイド」があります。これらは主に歯周病菌や舌苔の細菌活動によって発生し、卵が腐ったようなニオイや生ゴミのような不快臭を放ちます。
特にメチルメルカプタンは歯周病に特有のガスで、進行すればするほど濃度が高まる傾向があります。40代以降では唾液の分泌が減少し、これらのガスが口腔内に停滞しやすくなるため、ニオイをより強く感じることがあるのです。また、胃や消化器の不調、糖尿病などの内科的疾患が関係する場合もありますが、多くのケースでは「口の中の原因」が中心です。ガスの発生源を正しく理解し、それに応じたアプローチを行うことが根本的な改善につながります。
・恥ずかしさで受診をためらわないで
口臭はデリケートな悩みであるため、周囲には相談しにくく、歯科受診をためらう方も少なくありません。しかし、自己判断で対処しようとすると、本来の原因を見逃してしまい、かえって症状が悪化することもあります。
「恥ずかしいから」「たいしたことないから」と我慢するのではなく、医療機関で正確な検査と診断を受けることが、最短かつ確実な解決への道です。特に歯科では、口臭の原因を「見える化」する測定器や唾液検査、歯周病の検査など、総合的に状態を把握する体制が整っています。症状の背景にある問題を一つひとつクリアにしていくことで、不安や自己否定感からも解放され、より前向きな気持ちでケアに取り組むことができます。今や口臭ケアは“エチケット”から“健康管理”の一環へと変わりつつあります。マスク時代に気づけたことを、これからの自分の健康維持に活かしていきましょう。
歯科医院でできる口臭の専門的な検査と対策

・口臭測定器や唾液検査による「見える化」
「自分の口臭がどの程度なのか」「他人に不快感を与えていないか」…こうした不安を抱える女性にとって、数値として“見える化”できるのは非常に大きな安心材料となります。歯科医院では、ガス成分を測定する専用機器(口臭測定器)を用いて、呼気中に含まれる揮発性硫黄化合物(VSC)の濃度を正確に測定することが可能です。
VSCは主に歯周病菌の活動によって生まれるため、数値が高い場合は歯周病の存在が疑われます。また、唾液の質や量を確認できる「唾液検査」も有用です。唾液は口腔内の自浄作用や殺菌作用を担っているため、唾液が少なかったり、粘性が高かったりすると、口臭が発生しやすくなります。これらの検査を通じて、自分の口臭のタイプや原因を客観的に把握することができ、必要な治療や生活改善の方向性を明確にできます。
・歯周治療・クリーニングで原因にアプローチ
口臭の主な原因が歯周病にある場合、対症療法では根本的な解決にはつながりません。まずは、原因菌が潜む歯周ポケットの深部を徹底的に清掃し、炎症を抑える治療が不可欠です。
歯科医院では、専用の器具を使ったスケーリング(歯石除去)やルートプレーニング(歯根面の滑沢化)などの処置が行われ、歯周病の進行を抑えることができます。加えて、定期的なプロフェッショナルクリーニング(PMTC)により、日常のブラッシングでは取り切れないバイオフィルムや着色汚れを除去することで、菌の温床を取り除くことが可能です。
特に40代以降の女性では、ホルモンバランスの変化により歯ぐきの炎症が起きやすくなっており、口臭予防の観点からも継続的なメンテナンスが重要となります。「臭いを消す」ではなく「臭いを作らせない口腔内環境をつくる」ことが、歯科でのアプローチの本質です。
・必要に応じた舌苔除去や生活指導も
意外と見落とされがちなのが、舌の表面に付着した「舌苔(ぜったい)」の存在です。舌苔は細菌・食べかす・古い粘膜などが蓄積したもので、歯ブラシでは届かないため専用の舌ブラシを使ってやさしく取り除くことが勧められます。
ただし、誤った方法で舌を強くこすりすぎると、粘膜を傷つけたり炎症を引き起こしたりするため、歯科で正しい舌ケアの指導を受けることが望ましいでしょう。また、生活習慣も口臭に大きく影響します。水分不足・偏った食事・口呼吸・過度なストレス・睡眠不足などは、いずれも唾液の減少や口腔内の乾燥を招き、菌の繁殖を助長します。
歯科医院では、これらの生活背景をヒアリングしたうえで、一人ひとりに合ったアドバイスやセルフケア指導を行います。医療と生活の両面からサポートできるのが、専門的な歯科口臭治療の大きな強みです。
自宅でできるセルフケアと意識の変え方

・ブラッシング・舌ケア・フロスの活用法
口臭対策の第一歩は、毎日のセルフケアにあります。ただ歯を磨くだけでは不十分で、正しい方法と道具選びが重要です。歯ブラシは毛先が開いていないものを使用し、歯ぐきとの境目や奥歯まで丁寧に磨くことが基本です。
歯ブラシだけでは届かない歯と歯の間の汚れには、デンタルフロスや歯間ブラシの併用が有効で、これらを使わないとプラーク除去率は6割以下にとどまるというデータもあります。また、舌の表面に付着する舌苔(ぜったい)も臭いの原因になるため、専用の舌ブラシでやさしく清掃する習慣をつけましょう。
歯みがき粉は研磨剤や発泡剤が少ないタイプが口臭対策には適しています。抗菌成分を含むマウスウォッシュの使用も補助的に効果を発揮しますが、あくまで日々のブラッシング・フロッシングが主軸となるべきです。
・就寝前と起床後のケアが特に重要
1日の中でも、就寝前と起床後のケアは特に重要です。夜寝ている間は唾液の分泌量が大幅に減少し、口腔内の自浄作用が低下するため、細菌が繁殖しやすい状態になります。寝る前には念入りなブラッシングと、歯間部・舌のケアを徹底することで、細菌の増殖を抑え、翌朝の口臭の強さを軽減できます。
起床直後は、口腔内が最も不衛生な状態とされており、まずはうがいやブラッシングで口の中の細菌をリセットすることが大切です。朝食前に一度歯磨きを行うことで、食事とともに細菌を体内に取り込むリスクを減らせます。さらに、朝起きたらまずコップ一杯の水を飲むことで、口の中と体全体の潤いが回復し、唾液の分泌も促進されます。このように「いつケアするか」にも注目することで、セルフケアの質は大きく変わってきます。
・市販のケア用品の“選び方”にも注意
ドラッグストアやインターネットには、数多くの口臭対策グッズが並んでいますが、すべてが効果的とは限りません。たとえば強い香料で一時的に口臭を“ごまかす”タイプの商品は、根本的な改善にはなりません。逆に刺激が強すぎる洗口液は、口腔粘膜や舌を傷めてしまうこともあります。
選ぶべきは、低刺激でありながら抗菌作用があるもの、また口腔内のpHバランスを整えるよう設計された製品です。歯科医院で販売されている歯みがき粉やマウスウォッシュは、成分の信頼性や臨床効果の実証という点で安心材料になります。
また、オーラルケア用品の使い方にも工夫が必要です。フロスは糸の通し方や力の加減を誤ると歯ぐきを傷つける原因になり、舌ブラシも過度な使用は逆効果となります。歯科衛生士に相談することで、自分の口の状態に合った製品と正しい使い方を身につけることができ、セルフケアの質が格段に上がります。
口臭は「体からのサイン」だから放置しないで

・ただのニオイでは済まされない口臭の裏側
「最近、口臭が気になる…」「マスクの中で自分の息が気になるようになった…」――40代以降の女性がこのような違和感を覚える背景には、単なるエチケットの問題では片付けられない体の変化が隠れています。加齢に伴ってホルモンバランスが崩れたり、唾液の分泌が減少したりすることが、口臭の増加につながるのは事実です。
しかし、実はこの口臭が、歯周病や舌苔、ドライマウスなどの口腔トラブルだけでなく、糖尿病や消化器疾患といった全身の病気のサインである可能性もあるのです。特に“血液のようなにおい”や“アンモニア臭”、“腐った卵のような臭い”などは、歯科や内科での精密な診断を要することもあります。つまり口臭は、体の中からの「助けて」の声。見て見ぬふりをすることは、病気の早期発見のチャンスを逃すことにもなりかねません。
・歯科受診で健康と自信を取り戻す
加齢による変化を前向きに受け止めながら、自分自身の健康と丁寧に向き合う姿勢が、これからの時代にますます重要になります。中でも口臭というテーマは、他人に相談しづらいデリケートな問題である一方で、放置すると心理的にも大きなストレス要因になってしまうケースが少なくありません。
実際に、口臭を気にして人と話すのが億劫になったり、外食や会話の場面を避けるようになったりする人もいます。こうした状況は、日常生活の質(QOL)を大きく下げてしまう要因になります。
しかし、歯科医院では口臭の原因を“可視化”し、的確に対処する術がそろっています。舌苔・歯周病・ドライマウス・補綴物の不適合などを総合的にチェックし、一人ひとりの状態に合ったケアを提案してくれるのが歯科医療の強みです。受診によって原因が特定され、治療が進むことで、単なる臭いの改善にとどまらず、気持ちや表情にも明るさが戻るという副次的効果が期待できます。
・“加齢のせい”にせず、前向きなケアの一歩を
「年齢のせいだから仕方ない」と諦める前に、ぜひ知っていただきたいのは、加齢による変化に正しく対処すれば、口臭は改善できるという事実です。加齢そのものが病気ではないように、加齢による唾液量の低下やホルモンの変動に伴う口腔環境の変化も、“予防”と“適切なケア”によって十分コントロール可能です。
40代以降は、これまで以上に「自分の体と対話する」時期。些細な変化に気づき、行動を起こすことが、今後の人生の健康を大きく左右します。歯科医院での定期的な口腔チェックは、未来の自分を守るための「健康投資」といえるでしょう。
何よりも、自分の口臭に不安を感じたときに受診することは、自身への思いやりでもあります。「仕方ない」ではなく、「できることから始める」。その選択こそが、これからの健やかな毎日への第一歩です。
汐留駅から徒歩5分の歯医者・歯科
患者様の声に耳を傾ける専門の歯科クリニック
監修:《 オリオン歯科 NBFコモディオ汐留クリニック 》
住所:東京都港区東新橋2丁目14−1 コモディオ汐留 1F
電話番号 ☎:03-3432-4618
*監修者
オリオン歯科 NBFコモディオ汐留クリニック東京
ドクター 櫻田 雅彦
*出身大学
神奈川歯科大学
*略歴
・1993年 神奈川歯科大学 歯学部卒
日本大学歯学部大学院博士課程修了 歯学博士
・1997年 オリオン歯科医院開院
・2004年 TFTビル オリオンデンタルオフィス開院
・2005年 オリオン歯科 イオン鎌ヶ谷クリニック開院
・2012年 オリオン歯科 飯田橋ファーストビルクリニック開院
・2012年 オリオン歯科 NBFコモディオ汐留クリニック開院
・2015年 オリオン歯科 アトラスブランズタワー三河島クリニック 開院
*略歴
・インディアナ大学 JIP-IU 客員教授
・コロンビア大学歯学部インプラント科 客員教授
・コロンビア大学附属病院インプラントセンター 顧問
・ICOI(国際口腔インプラント学会)認定医
・アジア太平洋地区副会長
・AIAI(国際口腔インプラント学会)指導医
・UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)インプラントアソシエーションジャパン 理事
・AO(アメリカインプラント学会)インターナショナルメンバー
・AAP(アメリカ歯周病学会)インターナショナルメンバー
・BIOMET 3i インプラントメンター(講師) エクセレントDr.賞受賞
・BioHorizons インプラントメンター(講師)
・日本歯科医師会
・日本口腔インプラント学会
・日本歯周病学会
・日本臨床歯周病学会 認定医
・ICD 国際歯科学士会日本部会 フェロー
・JAID(Japanese Academy for International Dentistry) 常任理事