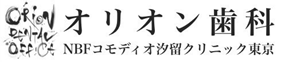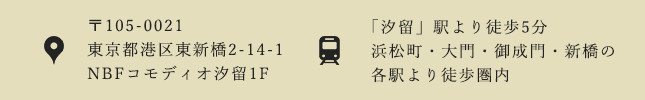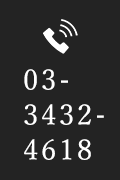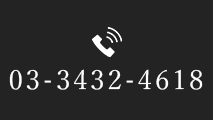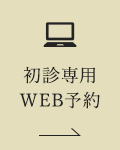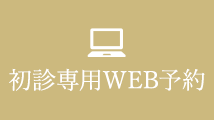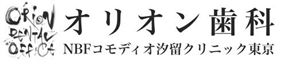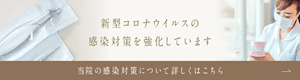その不安の正体は?「見えない部分が怖い」と感じる理由

「歯根端切-除術(しこんたんせつじょじゅつ)」という治療法を提案され、このページに辿り着かれたことと思います。おそらく、担当の先生からは「根管治療では治しきれないので、外科的なアプローチで歯を残しましょう」といった説明があったのではないでしょうか。
ご自身の歯を残せる最後のチャンスかもしれない、と期待する一方で、心の奥底から拭えない、もやもやとした不安があるはずです。その不安の正体こそ、この記事のタイトルにもある「見えない部分が怖い」という感覚ではないでしょうか。この感覚は、決してあなただけが感じている特別なものではありません。
・これまでの治療で「治りきらなかった」という経験
何度も通院し、時間をかけて根管治療を頑張ってきたにもかかわらず、痛みが再発したり、歯茎の腫れが引かなかったりした経験は、歯科治療に対する不信感を生むのに十分です。目に見えない歯の根の中だからこそ、「本当に今度こそ大丈夫なのだろうか」「また同じことの繰り返しになるのでは…」と感じるのは、ごく自然なことです。
・歯茎を切り、骨を削るという「未知の恐怖」
歯茎を切開し、その下にある顎の骨を少し削って、病巣を取り除く。言葉で聞くだけでも、強い抵抗感や恐怖を覚える方がほとんどです。「どれくらい痛いのだろう」「顔は腫れるのだろうか」といった具体的な心配はもちろん、「自分の体の中で、見えないことが行われる」という事実そのものが、大きなストレスとなります。
・「最後の砦」と言われることへのプレッシャー
この手術がうまくいかなければ、次は「抜歯」という選択肢が現実味を帯びてきます。「この歯を残せるかどうかは、この手術にかかっている」という状況は、患者様にとって大きなプレッシャーです。このプレッシャーが、「もし手術で原因を取り残してしまったら…」という最悪のケースを想像させ、不安を増幅させてしまうのです。
この記事では、そんなあなたの不安に真正面から向き合います。なぜ「取り残し」が起こりうるのか、そして、そのリスクを限りなくゼロに近づけるためには何が必要なのか。専門的な知識を分かりやすく解説していきますので、どうかご安心してお読みください。
なぜ?歯根端切除術で「病巣の取り残し」が起こりうるのか

歯根端切除術という選択肢に至ったということは、あなたはおそらく、時間をかけて根管治療を頑張ってこられたはずです。それにもかかわらず、なぜ症状が改善しなかったのか。そして、なぜ外科手術をもってしても「取り残し」というリスクが存在するのか。その根本的な理由を知ることは、あなたの不安を解消し、次の治療へ進むための大切な一歩となります。ここでは、その「なぜ?」に専門的な見地からお答えします。
・根の形は超複雑。レントゲンに映らない「側枝・根管の網目構造」
私たちが普段、歯のイラストなどで目にする歯の根は、とてもシンプルに描かれています。しかし、実際の歯の根の中は、まるで大樹の根や、川の支流のように、想像を絶するほど複雑な構造をしています。太い幹となる「主根管(しゅこんかん)」から、無数の細い枝葉のように分岐する「側枝(そくし)」や、根の先端で網目のように広がる「根尖分岐(こんせんぶんき)」が存在するのです。これらは、細菌にとって絶好の隠れ家となります。通常の根管治療で用いる器具は、主に太い主根管を清掃するためのもので、この迷路のように入り組んだ側枝の奥深くまで物理的に到達し、汚染を完全に取り除くことは極めて困難です。そのため、どんなに丁寧に治療を行っても、この複雑な網目構造の中に細菌が潜んでしまい、再発の原因となるケースは決して少なくありません。歯根端切除術で「取り残し」が起こりうる一因も、この解剖学的な複雑さにあるのです。
・従来の2次元レントゲン診断の限界と見落としのリスク
これまで歯科治療で撮影されてきたレントゲンは、骨や歯の内部を透過させてフィルムに焼き付けた「影絵」のようなものです。これは2次元(平面)の情報であり、診断において非常に重要ですが、万能ではありません。最大の弱点は、立体的な構造を平面に押しつぶしているため、「奥行き」の情報が完全に失われてしまうことです。例えば、歯の根のすぐ裏側に病巣があったとしても、レントゲン上では歯と重なってしまい、その正確な位置や大きさ、広がりを把握することができません。また、頬側の骨は薄いため病巣が確認できても、舌側の厚い骨に隠れた病巣は見落としてしまう可能性もあります。このように、2次元のレントゲン写真だけを頼りに手術を行うことは、いわば不完全な地図で目的地を目指すようなもの。これが「見えているはず」の病巣を見誤ったり、「見えない」病巣を見落としたりする原因となり、結果として病巣の取り残しというリスクに繋がってしまうのです。
・嚢胞(のうほう)の完全除去が難しい理由と再発のメカニズム
歯の根の先にできる病巣は「歯根嚢胞(しこんのうほう)」と呼ばれる、膿や滲出液が溜まった袋状の組織であることが多くあります。これは単なる膿の塊ではなく、風船やシャボン玉のように、非常に薄くデリケートな「嚢胞壁(のうほうへき)」という膜に覆われています。この嚢胞を完全に取り除くことが、再発を防ぐ上で極めて重要です。しかし、嚢胞は周囲の骨と癒着していることも多く、手術中にこの薄い膜が破れてしまうと、内容物とともに嚢胞壁の細胞が周囲に散らばってしまいます。たとえごくわずかでも、この嚢胞壁の細胞が骨の中に残ってしまうと、それが「種」となり、時間をかけて再び増殖し、嚢胞が再発してしまうのです。嚢胞を破らずに、一つの塊として綺麗に摘出するためには、病巣の正確な輪郭を術前に把握し、極めて繊細な外科手技で丁寧に剥がしていく必要があります。この繊細な作業の難しさこそが、嚢胞の完全除去を困難にし、再発の一因となっているのです。
「取り残し」を防ぐ第一歩。見えない部分を可視化する「歯科用CT」

歯根端切除術における「取り残し」のリスクは、歯の根の複雑な構造や、病巣の見えにくさにあるとご説明しました。では、どうすればこの「見えない」という根本的な問題を解決できるのでしょうか。その答えが、現代の精密歯科治療に不可欠な診断機器「歯科用CT」の活用です。従来の2次元レントゲンが「影絵」だとすれば、歯科用CTは対象をあらゆる角度から観察できる「立体模型」です。この圧倒的な情報量の差が、手術の精度と安全性を劇的に向上させるのです。
・なぜ外科処置の前にCT撮影が不可欠なのか
歯根端切除術は、歯茎を切開し、顎の骨を一部削って行う外科処置です。一度手術を始めたら、後戻りはできません。だからこそ、手術を始める前の「設計図」の精度が、治療の成否を大きく左右します。もし、不完全な地図(2次元レントゲン)を頼りに手術を進めれば、予期せぬ出血や神経の損傷、そして何より病巣の取り残しといったリスクが高まります。歯科用CTは、手術前に口腔内を3次元で正確に再現することで、こうしたリスクを限りなくゼロに近づけるために不可欠な存在です。どこを、どのくらい、どのように切削すれば、最も安全かつ確実に病巣を取り除けるのか。その最適なアプローチをシミュレーションできることこそ、CT撮影が精密な外科処置の前に必須とされる最大の理由です。これは、単に「あった方が良い」というレベルのものではなく、治療の質そのものを決定づける重要なプロセスなのです。
・歯や病巣を3次元で捉えることで得られる情報(位置・大きさ・神経との距離)
歯科用CTがもたらす3次元情報は、2次元レントゲンとは比較にならないほど膨大で、かつ精緻です。まず、これまで把握が難しかった病巣の「正確な位置と大きさ」を、ミリ単位で立体的に把握できます。病巣が頬側にあるのか、舌側にあるのか、どの根の先端に広がっているのかが一目瞭然となります。さらに、歯の根の形態も手に取るようにわかります。湾曲の度合いや、通常のレントゲンでは見えない根の断面形、そして再発の原因となりやすい「側枝」や「破折線」の有無まで確認できる場合があります。そして、安全性において最も重要なのが、下顎の骨の中を走る太い神経(下歯槽神経)や、上顎の鼻の脇にある空洞(上顎洞)といった、絶対に傷つけてはならない重要組織との「位置関係・距離」を正確に計測できることです。これらの情報を術前に完全に把握することで、安全な範囲で、かつ必要十分な量の骨だけを削り、病巣を確実に取り除くという、極めて精密な治療計画を立案することが可能になるのです。
・CTによる精密診断が手術の安全性と成功率をどう高めるか
CTによる精密診断は、手術の「安全性」と「成功率」の両方を飛躍的に高めます。安全性については、前述の通り、神経や血管などの重要組織を損傷するリスクを事前に回避できることが最大のメリットです。これにより、術後の麻痺などの偶発症の発生を最小限に抑えることができます。そして成功率、つまり「病巣の取り残しを防ぐ」という点においては、その貢献度は計り知れません。CTによって病巣の輪郭が明確になることで、術者は迷いなく、自信を持って病巣の除去に集中できます。どこまで削れば病巣が完全になくなるのかが事前にわかっているため、健康な骨を不必要に削りすぎることもありません。これは、歯を支える骨を最大限温存することにも繋がり、結果として歯の長期的な安定に寄与します。CTという「正確な目」を持つことで、闇雲な手術ではなく、科学的根拠に基づいた計画的で確実な手術が実現する。これこそが、CT診断が成功率を高める本質的な理由です。
ミリ単位の精度を追求。「マイクロスコープ」が叶える精密手術

歯科用CTによって、病巣の位置や大きさ、形といった「設計図」を完璧に手に入れたとしても、それを寸分の狂いもなく実行する「技術」がなければ意味がありません。歯根端切除術は、直径わずか数ミリの歯の根の先端を扱う、極めて繊細な外科処置です。このミリ単位以下の世界で確実な結果を出すために、現代の精密治療において絶対的な役割を果たすのが「マイクロスコープ(歯科用実体顕微鏡)」です。これは単なる虫眼鏡ではなく、術者の視野を劇的に変え、治療の次元そのものを引き上げるための医療機器です。
・なぜ肉眼での手術には限界があるのか
人間の肉眼の分解能(2つの点を識別できる能力)には限界があります。どんなに視力の良い術者であっても、0.2mm程度のものを見分けるのがやっとだと言われています。しかし、歯根端切除術で扱う根管の内部や、病巣と正常な組織との境界は、それよりもはるかに微細な世界です。暗くて狭いお口の中で、出血も伴う視野の中、肉眼だけを頼りに手術を行うことは、いわば指先の感覚だけを頼りに、見えない場所で精密な作業を行うようなものです。これでは、感染源となっている汚染物質を完全に取り除いたり、嚢胞の壁を綺麗に剥がしたりすることは極めて困難です。「おそらく取れたであろう」という経験と勘に頼らざるを得ない部分が多くなり、それが「取り残し」という不確実性を生む最大の原因となります。治療の成功を「おそらく」という曖昧なものから「確実」なものへと変えるためには、肉眼の限界をテクノロジーで超える必要があるのです。
・最大20倍以上の拡大視野がもたらすもの(病巣の確実な除去)
マイクロスコープは、術野を最大で20倍以上にまで拡大することができます。これは、これまで肉眼では決して見ることのできなかった世界を、術者の目の前に映し出すことを意味します。例えば、根管治療がうまくいかなかった原因である、見落とされていた「側枝(根の分岐)」や「イスムス(根管同士を繋ぐ溝)」、あるいは歯に生じた微細な「マイクロクラック(ひび割れ)」までもが、拡大視野下ではっきりと識別可能になります。これにより、病巣の根源となっている感染源を特定し、それをピンポイントで、かつ確実に取り除くことができます。嚢胞を摘出する際にも、その薄い膜と周囲の骨との境界が明確に見えるため、膜を破ることなく、一つの塊として丁寧に剥がし取ることが可能です。マイクロスコープの使用は、単に「よく見える」というレベルの話ではありません。治療の概念そのものを変え、これまで不可能だったレベルの精度を実現し、「取り残し」のリスクを限りなくゼロに近づけるための、最も強力な武器となるのです。
・明るい視野の確保と、健康な組織を傷つけない低侵襲治療への貢献
マイクロスコープのもう一つの大きな利点は、強力な光源によって術野を非常に明るく照らし出せることです。お口の奥深く、光が届きにくい場所であっても、まるで真昼の光の下で作業するかのようなクリアな視野を確保できます。これにより、術者は組織の色や性状の違いを正確に見分けることができ、より安全で確実な処置が可能になります。そして、この「拡大」と「照明」という二つの恩恵がもたらす最大のメリットが、「低侵襲(ていしんしゅう)治療」の実現です。低侵襲治療とは、健康な組織へのダメージを最小限に抑える治療のことです。マイクロスコープによって悪い部分だけがピンポイントで視認できるため、病巣を取り除くために健康な骨や歯質を不必要に削りすぎるということがありません。切開や骨の切削範囲を最小限にできるため、術後の痛みや腫れを軽減し、患者様の身体的負担を和らげ、より早い治癒を促すことにも繋がるのです。
再発の芽を摘む”壁”。病巣除去後の「MTAセメントによる逆根管充填」

歯科用CTで正確な診断を行い、マイクロスコープを用いて病巣を完璧に取り除いたとしても、歯根端切除術にはもう一つ、治療の成否を決定づける極めて重要な工程が残されています。それが、病巣と共に切断した歯の根の先端を、特殊な材料で封鎖する「逆根管充填(ぎゃくこんかんじゅうてん)」です。この最後の「蓋」が不完全であれば、どれだけ完璧に病巣を除去しても、根管内から再び細菌が漏れ出し、再発してしまいます。この再発の芽を完全に摘み、治療を完結させるための”最後の砦”となるのが、「MTAセメント」という画期的な材料です。
・根の切断面を「封鎖」することの重要性
歯根端切除術では、感染の温床となっている歯の根の先端部分を、外科的に切断します。すると、そこには根管治療で詰めた薬の断面や、感染物質が潜んでいたかもしれない根管の内部が露出することになります。この切断面を、いわば「開けっ放し」の状態にしておくと、どうなるでしょうか。たとえ周囲の骨が綺麗になったとしても、この断面から細菌が漏れ出し、再び周囲の組織を汚染し始めてしまいます。これでは、苦労して病巣を取り除いた意味がありません。この細菌の漏洩(リーケージ)を防ぐために、切断した根の先端に緊密な「蓋」をして、根管の内部と外部を完全に遮断する必要があります。この封鎖の精度こそが、歯根端切-除術後の長期的な安定を左右する、まさに生命線と言えるのです。この工程が不完全だと、数年後に再び歯茎が腫れたり、痛みが出たりといった再発のリスクが格段に高まります。
・MTAセメントとは?従来の材料との決定的な違い
これまで逆根管充填には、様々な材料が使用されてきましたが、それぞれに一長一短がありました。例えば、封鎖性は良いものの体に優しくなかったり、逆に生体親和性は高いものの、封鎖性が不十分で唾液や血液などの水分に弱かったりといった課題があったのです。こうした従来材料の欠点を克服するために開発されたのが「MTA(Mineral Trioxide Aggregate)セメント」です。MTAセメントの最大の特徴は、その卓越した「封鎖性」と「生体親和性」を両立させている点にあります。この材料は水分がある環境で硬化するという特殊な性質を持つため、手術中の血液や組織液の存在下でも、根の切断面と化学的に結合し、隙間なく緊密に封鎖することができます。これは、常に湿潤環境にある口腔内の外科処置において、極めて大きなアドバンテテージとなります。従来材料では成し得なかったレベルの封鎖性を実現できること、これがMTAセメントが画期的と言われる所以です。
・高い封鎖性と生体親和性が、なぜ再感染防止に繋がるのか
MTAセメントによる強固な封鎖は、細菌の漏れ出す「出口」を完全にシャットアウトし、再感染のリスクを根本から断ち切ります。しかし、MTAセメントの優れた点はそれだけではありません。もう一つの重要な特性である「高い生体親和性」が、治癒を積極的に後押ししてくれるのです。生体親和性が高いとは、つまり「体に優しい」ということで、アレルギー反応や炎症反応を起こしにくい性質を指します。それどころか、MTAセメントは周囲の骨の再生を促す「骨誘導能」や、歯の硬組織(セメント質)の形成を促す性質も持っていることが分かっています。つまり、MTAセメントで根の先端を封鎖すると、単に蓋をするだけでなく、そのセメントに接する形で新しい骨や歯の組織が再生され、より強固で一体化した封鎖構造が出来上がるのです。この「封鎖」と「再生促進」という二重の働きによって、感染の再発を長期的に防ぎ、手術した歯の予後を格段に安定させることができるのです。
取り残しを防ぐための治療の全貌

これまで、歯根端切除術における「取り残し」のリスクと、それを防ぐためのCT、マイクロスコープ、MTAセメントといった先進技術についてご説明してきました。しかし、最も重要なのは、これらの機器や材料をただ導入するだけでなく、一連の治療プロセスの中でいかに有機的に連携させ、一貫した哲学のもとで実践するかです。ここでは、当院が「取り残しを限りなくゼロに近づける」という目標を達成するために、どのようなこだわりのステップで治療を進めているのか、その全貌をご紹介します。
・Step1:精密な診査・診断(CT撮影と治療計画のご説明)
すべての治療は、正確な現状把握から始まります。当院では、歯根端切除術を検討するすべての患者様に対し、原則として歯科用CTの撮影を実施します。これは、あなたの歯を救うための「航海図」を作成する、最も重要なステップです。撮影したCT画像をもとに、なぜ通常の根管治療では治癒に至らなかったのか、その原因を徹底的に分析します。病巣の正確な位置・大きさ・広がりはもちろん、見落とされがちな根の分岐(側枝)や破折線の有無、そして神経や血管との三次元的な位置関係までを詳細に把握します。そして、ただ私たちが分析するだけでなく、そのCT画像やシミュレーション画面をモニターに映し出し、あなたご自身にもご覧いただきながら、現在の状況と治療計画について、専門用語を避けて分かりやすくご説明します。「何のために、どこを、どのように治療するのか」をあなた自身が深く理解し、納得していただくことです。
・Step2:万全な環境下での外科処置(マイクロスコープ・MTAセメント使用)
十分な診査・診断とカウンセリングを経て、治療にご同意いただけましたら、いよいよ外科処置へと進みます。当院の手術は、全症例でマイクロスコープを使用することが標準です。術者は最大20倍以上に拡大されたクリアな視野のもと、CTで計画した通りに、寸分の狂いもなく処置を進めていきます。病巣と正常組織の境界を明確に識別し、感染源となっている組織を徹底的に、かつ健康な組織へのダメージは最小限に抑えながら除去します。この精密な作業は、肉眼では決して到達できないレベルのものです。そして、病巣を完全に取り除き、根の先端を切断した後は、最後の仕上げとしてMTAセメントによる逆根管充填を行います。湿潤環境下でも高い封鎖性を発揮するMTAセメントで根の切断面を緊密に封鎖し、細菌の再侵入経路を完全に遮断します。
・Step3:術後のフォローアップと治癒の確認
手術が終われば、すべて完了というわけではありません。むしろ、そこからが本当の意味での治癒の始まりです。当院では、手術後の経過を責任をもって見守る、長期的なフォローアップ体制を重視しています。術後の痛みや腫れを最小限に抑えるための投薬や注意事項のご説明はもちろん、定期的にご来院いただき、傷口の状態や治癒の経過を丁寧に確認します。そして、術後一定期間が経過したタイミングで、再度レントゲンやCTを撮影し、病巣があった部分の骨がきちんと再生してきているかを客観的に評価します。CT画像上で、黒い影として映っていた病巣が、白く硬い骨に置き換わっていく様子をあなたご自身の目で確認していただくことで、治療の成功を実感し、大きな安心感を得ていただけるはずです。手術という「点」で終わるのではなく、完全な治癒という「線」で捉え、最後まで責任をもって寄り添うことがカギとなります。
手術後の歯は、どうなる?歯の寿命と骨の再生に関する真実

「手術は成功しても、その歯は結局長持ちしないのではないか」「根が短くなると、すぐにグラグラしてしまうのでは…」歯根端切除術という大きな決断を前に、手術後の歯の未来について心配になるのは当然のことです。外科的な処置を受けた歯が、その後どのような経過をたどり、健康な歯と同じように機能し続けることができるのか。ここでは、手術後の歯の寿命や、骨が再生するメカニズムといった、あなたが本当に知りたい「真実」について、専門的な視点から詳しく解説します。
・歯根が短くなることによる強度への影響は?
歯根端切除術では、感染源となっている根の先端を数ミリ切断するため、確かに歯の根(歯根)は少し短くなります。この事実から、「歯が弱くなる」「噛む力に耐えられなくなる」といった不安を感じる方は少なくありません。しかし、結論から言えば、適切に行われた手術であれば、この数ミリの切除が歯の寿命に致命的な影響を与えることはほとんどありません。歯を支えているのは歯根全体であり、その先端を少し切除したとしても、歯を支える骨(歯槽骨)が十分に残っていれば、機能的な強度は維持されます。歯学的には、歯を支えるために最低限必要な歯根の長さ(歯根長)と、それを支える骨の量(歯槽骨レベル)のバランスが重要とされています。術前のCT検査でこのバランスを精密に評価し、手術後も十分な支持組織が残ると判断された場合にのみ、この治療法は適応されます。むしろ、感染源をそのまま放置し、周囲の骨がさらに溶かされてしまうことの方が、歯の寿命を縮めるはるかに大きなリスクとなるのです。
・骨が再生するメカニズムと、レントゲンでの治癒の確認
歯根端切除術の最も素晴らしい点の一つは、失われた骨が「再生」する可能性があることです。病巣(歯根嚢胞など)によって吸収され、空洞になっていた顎の骨は、その原因である細菌感染が完全に取り除かれると、自己修復能力を発揮し始めます。手術でクリーンになったスペースに、まず血液が満たされて血餅(けっぺい:血の塊)となり、これが足場となって新しい骨を作る細胞(骨芽細胞)が集まってきます。そして、数ヶ月から1年以上の時間をかけて、徐々に新しい骨が作られ、元の硬い骨組織に置き換わっていくのです。この治癒のプロセスは、術後に定期的に撮影するレントゲンやCTで客観的に確認することができます。初めは黒い影のように見えた病巣の跡が、徐々に白く、周りの骨と同じ密度になっていく様子を見たとき、多くの患者様が治療の成功を実感し、心からの安堵の表情を浮かべられます。この「骨の再生」こそが、歯根端切-除術が単なる延命処置ではなく、根本的な治癒を目指す治療法であることの何よりの証拠です。
・歯を長持ちさせるために最も重要な「術後のメンテナンス」
歯根端切除術によって救われた歯を、その後何十年と長持ちさせるために、最も重要になるのは何でしょうか。それは、日々のセルフケアと歯科医院での定期的なプロフェッショナルメンテナンスです。手術によって歯の根の先の問題は解決しましたが、歯周病や新たなむし歯といった別のリスクがなくなるわけではありません。特に、外科処置を行った歯の周辺は、丁寧なケアが不可欠です。手術が無事に成功したからといって、そこで終わりにしてしまうのではなく、むしろ「新たなスタート」と捉えることが大切です。毎日の正しいブラッシングでプラークコントロールを徹底し、定期的に歯科衛生士による専門的なクリーニング(PMTC)を受けることで、お口全体の健康を維持する。この地道な努力こそが、手術で残した大切な歯を守り、その寿命を最大限に延ばすための、最も確実で効果的な方法なのです。私たちは、手術後のメンテナンスの重要性についても丁寧に指導し、あなたの歯の未来を長期的にサポートしていきます。
それでも迷う方へ。「抜歯してインプラント」との冷静な比較

歯根端切除術を提案された時、多くの患者様の頭をよぎるのが、「いっそのこと、この歯を抜いてインプラントにした方が良いのではないか?」という選択肢です。確かに、インプラント治療は失った歯を補うための優れた治療法の一つであり、近年では非常に身近な存在になりました。しかし、安易に抜歯を選択する前に、ご自身の天然の歯を残すことの価値をもう一度冷静に考えてみる必要があります。ここでは、感情論ではなく、歯科医学的な観点から「歯根端切除術で歯を残すこと」と「抜歯してインプラントにすること」を比較し、あなたが後悔のない選択をするためのお手伝いをします。
・自分の歯を残す最大のメリット「歯根膜」の存在
天然の歯とインプラントの決定的な違い、それは「歯根膜(しこんまく)」という、わずか0.2mmほどの薄い膜の有無にあります。歯根膜は、歯の根と顎の骨との間に存在するクッションのような組織で、実は驚くほど多くの重要な役割を担っています。まず、噛んだ時の力を絶妙に分散・吸収し、硬すぎるものを噛んだ時には「痛い!」という信号を脳に送って、歯や顎がダメージを受けるのを防いでくれます。この繊細なセンサー機能のおかげで、私たちは豆腐の柔らかさからお煎餅の硬さまで、食感を楽しみながら食事をすることができるのです。さらに、歯根膜は細菌に対する防御壁としても機能し、歯周病菌が骨に直接侵入するのを防いでいます。インプラントにはこの歯根膜が存在しません。そのため、噛み合わせの力がダイレクトに骨にかかり、過度な力が加わると骨を失いやすい傾向があります。また、細菌への抵抗力も天然歯に比べて弱く、「インプラント周囲炎」という重篤な病気にかかりやすいことも知られています。この「歯根膜」という、神様が作った精巧な組織を失うことの意味は、私たちが思う以上に大きいのです。
・歯根端切除術とインプラント、それぞれのメリット・デメリット
ここで、両者のメリット・デメリットを客観的に整理してみましょう。
【歯根端切除術】
メリット:
自分の歯(歯根膜)を残せるため、自然な噛み心地や食感が保たれる。
周囲の健康な歯を削ったり、傷つけたりする必要がない。
成功すれば、インプラントよりも身体的・経済的負担が少ない場合がある。
インプラントに比べて細菌感染への抵抗力が高い。
デメリット:
歯の状態によっては適応できない場合や、再発のリスクがゼロではない。
外科処置が必要であり、術後の腫れや痛みを伴う。
治療の成否が、術者の技術や医院の設備に大きく左右される。
【抜歯してインプラント】
メリット:
歯の根の問題(根管治療の失敗や歯根破折)を根本的に解決できる。
見た目や機能が天然歯に近く、審美的に優れている。
ブリッジのように隣の歯を削る必要がない。
デメリット:
かけがえのない自分の歯(歯根膜)を失う。
外科手術が必要であり、骨の状態によっては追加の手術(骨造成など)が必要になる。
治療期間が長く、費用も高額になる傾向がある。
インプラント周囲炎のリスクがあり、長期的なメンテナンスが不可欠。
このように、どちらの治療法にも一長一短があり、「どちらが絶対的に優れている」と言えるものではありません。
・長期的な観点で、どちらがあなたにとって良い選択か
最終的にどちらの道を選ぶべきか。その答えは、あなたの歯の状態、そしてあなたが何を最も大切にしたいかによって変わってきます。もし、歯根端切-除術によって長期的な予後が期待できる状態なのであれば、まずはご自身の歯を救う努力をしてみる価値は十分にある、と私たちは考えます。なぜなら、一度抜いてしまった歯は、二度と元には戻らないからです。インプラント治療は、どうしても歯を残すことができなかった場合の「次善の策」として、いつでも選択することができます。しかし、歯を残すチャンスは、今しかありません。私たちは、精密な診査・診断に基づき、「あなたの歯が、残すための治療を試みる価値のある歯なのかどうか」を正直にお伝えします。そして、もし歯根端切除術を選択された場合には、その成功のために全力を尽くします。もちろん、インプラントが最善の選択であると判断した場合には、その理由も誠実にご説明します。大切なのは、あなたが全ての情報を理解し、ご自身の価値観に基づいて、心から納得できる選択をすることです。
歯根端切除術の成否を分ける、最も重要な「医院選びの基準」

ここまでお読みいただき、歯根端切除術が非常に専門的で、精密さを要求される治療であることをご理解いただけたかと思います。そして、この治療の成否は、どの歯科医院で受けるかによって大きく左右されるという厳しい現実も存在します。では、あなたの大切な歯の未来を託すために、どのような基準で歯科医院を選べば良いのでしょうか。最後に、後悔しない医院選びのための、3つの重要なチェックポイントをご紹介します。これは、単なる宣伝文句ではなく、患者様ご自身の目で本質を見極めていただくための、私たちからの誠実なメッセージです。
・治療の質を担保する「設備」の重要性(CT・マイクロスコープは必須か)
現代の歯根端切除術において、「歯科用CT」と「マイクロスコープ」は、もはや”特別な設備”ではなく、治療の質を担保するための”必須のインフラ”であると私たちは考えています。CTがなければ、手術の前に正確な3次元の設計図を描くことはできず、闇雲な手術になるリスクを排除できません。マイクロスコープがなければ、術者の肉眼では決して見えない微細な感染源を確実に取り除くことは困難です。もし、あなたが検討している医院がこれらの設備を備えていない、あるいは使用を明言していない場合、それは「経験と勘」に頼った従来型の治療である可能性が高いと言えます。もちろん、熟練の技術は非常に重要ですが、その技術を最大限に発揮し、ヒューマンエラーを限りなくゼロに近づけるのが先進設備の役割です。あなたの歯を「おそらく治す」のではなく、「科学的根拠に基づいて確実に治す」ために、これらの設備が整っているかどうかは、医院選びの絶対的な基準の一つとしてください。
・歯内療法(根管治療)領域における歯科医師の専門性と経験
歯根端切除術は、歯内療法(根管治療)の延長線上にある、極めて専門性の高い外科処置です。したがって、この手術を成功に導くためには、術者である歯科医師が、歯内療法学に関する深い知識と豊富な臨床経験を持っていることが不可欠です。なぜ根管治療が失敗したのか、その原因を解剖学的・細菌学的に正しく理解し、それを外科的にどう解決すべきかを判断できる能力が求められます。医院のホームページなどで、歯科医師が歯内療法に関する学会に所属しているか、専門医や認定医の資格を持っているか、あるいは歯根端切除術の症例を多く手がけているかなどを確認するのも一つの方法です。また、カウンセリングの際に、あなたの質問に対して、論理的かつ分かりやすく、自信をもって答えてくれるかどうかも重要な判断材料になります。その歯科医師が、この分野にどれだけの情熱とこだわりを持って取り組んでいるか、その姿勢を感じ取ることが大切です。
・リスクや費用について、あなたが納得できるまで説明してくれるか
信頼できる歯科医院は、治療のメリットや成功例ばかりを強調するのではなく、起こりうるリスクやデメリット、そして費用についても、包み隠さず誠実に説明してくれるはずです。歯根端切除術は100%成功が保証された治療ではありません。術後の痛みや腫れ、神経麻痺のリスク(頻度は低いですが)、そして再発の可能性など、考えられる不都合な真実についても、事前にきちんと説明し、あなたの同意を得るのが医療機関としての責務です。また、この治療は多くの場合、保険適用外の自費診療となります。なぜその費用が必要なのか(使用する材料や設備、技術料など)、その内訳を明確に提示し、あなたの疑問が解消されるまで、時間をかけて丁寧に説明してくれるかどうかを見極めてください。「良いこと」ばかりを並べるのではなく、むしろ「悪いこと」も正直に話してくれる医院こそ、患者様のことを第一に考えている、真に信頼できるパートナーと言えるでしょう。あなたの不安な気持ちに寄り添い、対等な立場で対話してくれる、そんな歯科医院を選んでください。
最後の不安を解消。歯根端切除術に関するQ&A

ここまで、歯根端切除術における「取り残し」のリスクと、それを防ぐための精密治療について詳しく解説してきました。しかし、それでもなお、あなたの心の中にはいくつかの疑問や迷いが残っているかもしれません。
ここでは、カウンセリングで患者様からよくいただくご質問をQ&A形式でご紹介します。あなたの最後の不安を解消する一助となれば幸いです。
Q1.「話を聞きに行くだけでも大丈夫ですか?相談したら、すぐに手術を勧められそうで不安です…」
A. もちろんです。まずはお話をお聞かせいただくだけで全く問題ありません。当院では、患者様がご自身の状況を正確に理解し、心から納得して治療法を選択できることが何よりも大切だと考えています。レントゲンやCTの画像をお見せしながら、なぜ根管治療で治癒が難しかったのか、現在の歯の根の状態はどうなっているのかを丁寧にご説明します。その上で、歯根端切除術がどのような治療で、どのようなメリット・デメリットがあるのか、他の選択肢(抜歯やインプラントなど)と比較しながら客観的な情報をご提供します。私たちが大切にしているのは、治療を無理に勧めることではなく、あなたが最良の決断をするための「判断材料」を誠実にお伝えすることです。安心して、まずはご相談にいらしてください。
Q2.「結局、手術の成功率はどれくらいなのでしょうか?先生の技術によって変わりますか?」
A. 大変気になるポイントだと思います。歯根端切除術の成否は、お口の中の状態だけでなく、診断の精度や処置の精密さといった、医療技術に大きく左右されるのは事実です。そのため、当院では成功率を少しでも高めるために、本記事で解説してきたような取り組みを徹底しています。具体的には、①歯科用CTによる3次元的な診査・診断で病巣を正確に把握し、②マイクロスコープで術野を最大20倍以上に拡大して病巣の「取り残し」を防ぎ、③MTAセメントで根の切断面を緊密に封鎖し「再感染」のリスクを断つ。この一連のプロセスを高いレベルで実践することが、良好な結果に繋がると確信しています。特定の数字をお示しするよりも、こうした「成功のために何をしているか」をご理解いただくことが、信頼に繋がると考えています。
Q3.「自分の歯を残したいけれど、本当にこの手術がベストな選択なのか迷っています」
A. そのお気持ち、非常によく分かります。「自分の歯に勝るものはない」というのは歯科医療における一つの真理ですが、全てのケースで歯根端切除術が最善の選択とは限りません。例えば、歯の破折が疑われる場合や、支えている骨が大幅に失われている場合など、残念ながら予後が期待できないケースも存在します。大切なのは、あなたの歯が「残す価値のある状態か」を客観的に、そして精密に見極めることです。当院では、精密な診査・診断に基づいて、歯を残せる可能性と、仮に残した場合の長期的な見通し(メリット・デメリット)を正直にお伝えします。その上で、もし他の選択肢(例えば抜歯後のインプラント治療など)の方が、あなたの将来的なお口の健康にとって有益だと判断した場合は、その理由も正直にご説明します。一人で悩まず、まずは専門家としての客観的な意見を聞きに来る、という気持ちでお越しいただければと思います。
汐留駅から徒歩5分の歯医者・歯科
患者様の声に耳を傾ける専門の歯科クリニック
監修:《 オリオン歯科 NBFコモディオ汐留クリニック 》
住所:東京都港区東新橋2丁目14−1 コモディオ汐留 1F
電話番号 ☎:03-3432-4618
*監修者
オリオン歯科 NBFコモディオ汐留クリニック東京
ドクター 櫻田 雅彦
*出身大学
神奈川歯科大学
*略歴
・1993年 神奈川歯科大学 歯学部卒
日本大学歯学部大学院博士課程修了 歯学博士
・1997年 オリオン歯科医院開院
・2004年 TFTビル オリオンデンタルオフィス開院
・2005年 オリオン歯科 イオン鎌ヶ谷クリニック開院
・2012年 オリオン歯科 飯田橋ファーストビルクリニック開院
・2012年 オリオン歯科 NBFコモディオ汐留クリニック開院
・2015年 オリオン歯科 アトラスブランズタワー三河島クリニック 開院
*略歴
・インディアナ大学 JIP-IU 客員教授
・コロンビア大学歯学部インプラント科 客員教授
・コロンビア大学附属病院インプラントセンター 顧問
・ICOI(国際口腔インプラント学会)認定医
・アジア太平洋地区副会長
・AIAI(国際口腔インプラント学会)指導医
・UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)インプラントアソシエーションジャパン 理事
・AO(アメリカインプラント学会)インターナショナルメンバー
・AAP(アメリカ歯周病学会)インターナショナルメンバー
・BIOMET 3i インプラントメンター(講師) エクセレントDr.賞受賞
・BioHorizons インプラントメンター(講師)
・日本歯科医師会
・日本口腔インプラント学会
・日本歯周病学会
・日本臨床歯周病学会 認定医
・ICD 国際歯科学士会日本部会 フェロー
・JAID(Japanese Academy for International Dentistry) 常任理事